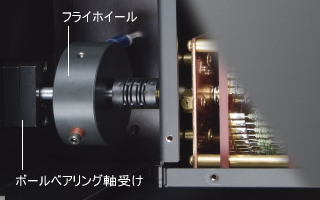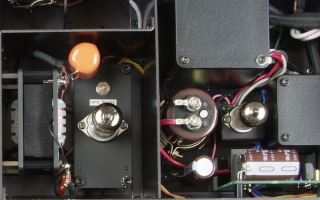�܂��v���A���v���g��Ȃ��g�f�h�̐��\�����ɏĂ��t���邽�߂ɁA�o�r�W�T�O�O�^�r�������������̂V�D�P�����_�C���N�g���͂̉����Ă݂��B
�V�D�P�����_�C���N�g���͂ɒ��ڂc�u�P�Q�r�Q�^�r�������������@�l�������Q���q�����Ƃ��̉�
����́A�ƂĂ����R�ɐL�тĂ���B
����ɂ́A�\���Ȍ��݂�����B
���́A�\���ȗʊ������邪���ɂ�����������B
���y���Ă����ہB
���ēx�͏\���B�ׂ��������������蕷�����邵�A�ׂ₩�Ȋy��̉��̕ω������j�A�ɍČ������B�����I�ɂ́A����ɏ\���Ȍ��݂�����{�[�J���̕\��⑧�Â������ƂĂ����R�ɓ`����Ă���̂��D��ہB�p�[�J�b�V������T�b�N�X�̉������R�B���y��⍂���I�[�f�B�I�̃J�`���I�Ƃ����I�[�f�B�I�I�Ȃ���ǂ��ꖡ�܂ł͖]�߂Ȃ����A���y�̗��ꂪ���R�Ŕ��Ɋy�����B
�V�D�P�����_�C���N�g���͂Ƃc�u�P�Q�r�Q�^�r�������������@�l�������Q�̊Ԃɂb�`�|�P���q�����Ƃ��̉�
�����́A�ꖡ�������Ă���܂ł͕������Ȃ������ׂ��������o�Ă���B
����́A�ш�o�����X���㉺�ɐL�т�����┖���Ȃ邪���͂Ȃ��B������Ƃ������肵���B
���́A�ш悪����ɐL�т�Ƌ��ɗ͊�����܂肪�o�āA������Ă������̒x�ꂪ�����ăO���O���ƑO�ɏo�Ă���悤�ɉ����o���Ă��銴�����S�n�悢�B
���y���Ă����ہB
���ēx�́A�n�b�L���Ƒ�������B����܂ŕ������Ă��Ȃ������ׂ�������\�����������悤�ɂȂ�B�{�[�J���������t�̊y��̉������N���[�Y�A�b�v����A�X�̃����f�B�[���C�������m�ɂȂ�B�Ƃ͌����A�ǂ����肪���ȁu�o���o���ȉ��v�ɕ��������̂ł͂Ȃ��A�X�̉��̐c���V�b�J���Ƃ��āA���݊����A�b�v���A��ʊ���������ƌł܂�����ŁA���ꂼ��̊y��̃p�[�g���Y��ȃn�[���j�[��t�łĂ���̂������ł���B
�I�[�f�B�I�I�A�g���e���I�ȗv�f�����߂ɏo�Ă��邪�A���y����������킯�ł͂Ȃ��B�����d���H���������ł��ǂ��������Ƃ������̃A���v�́u���v���̂��̂́A�n�b�L���Ɗ������邪���ꂪ���y���ז��ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�������AEGO-WRAPPINN�f�̌����Ă����ۂ͔����Ȃ�A������Ƃ����Ȃ܂��I����i�Ȋ�������⋭���Ȃ�B
�v���A���v���g��Ȃ��Ƃ��́A���y�𗬂�̐����Ŗ����I�ɕ������Ă���Ƃ�����ۂ����������A�v���A���v�����邱�Ƃʼn��̕i�ʂƉ𑜓x�A���ēx���傫���������A���C�u�Ƃ������̓X�^�W�I�̃��R�[�f�B���O���i���Ϗ܂��Ă���Ƃ����������o�Ă���B
CA-1��Accuphase�̂悤�ɓ����d���ʼn����ׂ����[���Ȉ�ۂ����邪�A�𑜓x�▾�ēx��CA-1�̕�����荂���A�����������g�N�[���i���\��j�h����Ȃ��̂��������BLuxman�̂悤�ȉ��₩����_�炩�������邪�A���̊p���������藧���Ă���̂�CA-1�̂ق����𑜓x�▾�ēx�͂�荂���BFM�A�R�[�X�e�B�b�N���́A���͍d�������d�����邱�Ƃ͂Ȃ��B���ēx�͂e�l�A�R�[�X�e�B�b�N�����������낤�B���Ԃ�A�}�[�N���r���\����No.26SL������Ɖ����͋߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���邪�A���ꂼ������ۂɌq���ς��Ĕ�r���Ċm���߂��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�܂������ۏ͏o���Ȃ��B�����܂œ��ōl�������Ƃ��B
�����I�ȃN�H���e�B�[�́A���y�I�ȗv�f�������Ă���B�ǂ��Ӗ��œ��{�l�I�Ȃg���e���T�E���h�̂悤�Ɋ�������B����́A���̃t�F�C�Y�e�b�N���i�Ƌ��ʂ���u�����h�Ǝ��̖��m�Ȍ����Ǝv���B
�ȑO���������ł́A�u�����������̃��{���g���[�V���[�Y�̍ō����f���̃X�s�[�J�[�̃f�����X�g���[�V�������v���o�����B�N�H���e�B�[�͔��Q�ɍ������A���@�I�Ƃ��L�@�I�Ƃ��`�e���������s�v�c�ȃT�E���h���������Ƃ������L���Ɏc���Ă���B��������̂͂����̃A���v��v�����i����Ă���̂́j�u�����������̃��{���g���[�V���[�Y������Ă������̐l�Ȃ̂��B
�f�W�^�����͂̉���
����́A���͋C���o�ď_�炩���Ȃ�B
����́A�Z�N�V�[�Ȗ��͂����Ă���B�{�[�J���̕\���͈�ԍׂ₩�Ő[���Ȃ�B
���́A�ʓI�ɂ�7.1ch�_�C���N�g���͂ƕς��Ȃ��̂����A�x�[�X��h�����̉��K��Y���̖��ēx�̓f�W�^�����͂̕��������A���ꂪ���R�Ŋy�������������B
���y���Ă����ہB
���Ɏ��R�ŃX���[�X�B�{�[�J���̕\����ɍׂ₩�Ńf���P�[�g�ɍČ������B�o�b�N�o���h���܂߂āA�g�[�^���o�����X�����Q�ŁA���|�I�Ɏ��R�Ȋ����B���Y���Z�N�V������������ł͂Ȃ��A���R�ɒe��Ŋy�����B�{�[�J���̑��g���A���̃g�[�����A�{���Ɏ��R�ł����ʼn̂��Ă���悤�Ɋ�����B���i���̃��C�u�A�S�ɉ��y���Ƃ�����ŁA���t�Ǝ������n�������Ĉ�̂ƂȂ��čs���悤�Ȋ���������B
�q���ł����A�T�[���W�b�N�̃T�u�E�[�t�@�[�̓d�������ăT�u�E�[�t�@�[���g���Ă݂�ƁB
�ቹ�̗ʊ��������āA���y���̂��ݍ��ނ悤�Ɋ���������قǂЂ��Ђ��Ɗ�������B��������B�̂��k����B�܂��o�����ɂȂ�B���y���O���ƃh���}�e�B�b�N�ɕ\��[���L���ɂȂ�B���ł͂Ȃ��u�̂���̐S�v���̂̒��ɂ��݂���ł���B���t�́A�{�[�J���ɗD�������Y���悤�ɁA�ޏ����x����悤�ɁA����グ��悤�ɕ�������B���炩�ŃX���[�Y�B����ł��ė͋����A�{�[�J�����ז����邱�Ƃ͂܂������Ȃ��B���y���u�ӑR��́v�ƂȂ��āA�̂̐c�ɗ��ꍞ��ł���B���܂ł������Ă������A�Z���Ă������T�E���h�B
���ł͂Ȃ��A���͋C�i����ȊȒP�Ȍ��t�ł͕\���Ȃ����j�����|�I�ɔZ���Ȃ�B���y�͂��悤�Ƃ��A�������Ƃ��A����ȋC�����͔��ł��܂��āA�����������̋Ȃɑ̂ƐS���ς˂Ă������Ƃ����C���ɂ�����B
�V�D�P�����_�C���N�g���͂Ƃc�u�P�Q�r�Q�^�r�������������@�l�������Q�̊Ԃɂ`���������������@2000���q�����Ƃ��̉�
����́A�F�ʊ��������đN�₩�ɂȂ�����ہB
����́A��ɗ����ꂸ�v���炵�����J�ɐS�����߂ĉ̂��Ă����ہB
���́A�_�炩���̂��ݍ��ވ�ۂŃf�W�^�����͂ɋ߂��B�N�I���e�B�[�͂��Ȃ荂���Ȃ�B
���y���Ă����ہB
�f�W�^�����͂ł́A��������Ȃ������u�N�₩���v���o�Ă���B���Y���Z�N�V�����ƃ{�[�J���̃n�[���j�[����芮���ɂȂ�B�f�W�^�����͂ł́A����ɗ������X���������������A�A���u���[�V�A�Q�O�O�O���g�����ƂŁA�v���̃{�[�J���炵���g���ܒ��ՁI�g�I�ɏ�̒��ɂ����R�Ƃ������̂��o�Ă��āA���{�[�J�����v�����ۂ��{���炵�����X��������������B
�����̌X����S�̂̈�ۂƂ��ẮA�f�W�^�����͂ƂƂĂ��ǂ����Ă���̂����A�͂���ꂽ�����̉����̗����オ�肪�����Ȃ��Ă���̂ƁA�G�R�[�̕����̋�C�������@�ׂœ����ɂȂ������Ƃʼn��y�S�̂̃X�P�[������\���͂��A�A�b�v���Ă���B
��{���y�̕\�������N�₩�ő傫���Ȃ�A�f�W�^�����͂ɔ�ׂĉ��y�I�i�A�[�e�B�X�e�B�b�N�j�Ȋ����x����荂���Ȃ�B
�����������Ԉ��ǂ͂܂������������Ȃ��B�����镔���ɂ����Ĉ�a�����قƂ�ǂȂ��A�{���Ɏ��R�ŁA�{���Ƀ��A���B
����ς肱�̃A���v�͑f���炵���I�����ω��Ƃ����Ӗ���WIREWORLD�̃X�s�[�J�[�P�[�u���ɂ́A�{���ɋ������̂����AAmbrosia
2000�́A���������I�ɕω�����������コ�����肷�邱�ƂȂ��Ɂi�����炱���A�ǂ������x����Ă���悤�Ȉ�a�������Ȃ��j���y�I�Ȋ����x�A�����x�A�[�������قڃ}�L�V�}���ƌ�����قǂɌ��コ����̂��������Ǝv���B
���̉����Ȃ�A���y�t�@�������߂邠���鉹�y�ɑ��Ď��R�Ƀ}�b�`����͂����B���ł͂Ȃ��A���y������̂�Ambrosia
2000�̖{���Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�CA-1�Ƃ̑Δ�ł�薾�m�ɂȂ�B���̃A���v�̂��Ƃ����́u������̃A���v�i���ꂪ�Ō�̃A���v�ɂȂ�Ƃ����Ӗ��j�v�ƌĂ�ł��邪�A����̎����ł���͂肻���������B�Ȃ��Ȃ�A���y�t�@�������߂�I�[�f�B�I�A���߂鉹�́A���]�Ȑ܂��������Ƃ��Ă����ǂ����֍s�������͂��Ȃ̂��B
�܂Ƃ�
�ŋ߂́A�u�V�A���R�[�h���t�Ƙ_�v�̉e���������āu�I�[�f�B�I�ʼn����ς��v�ƌ������Ƃ������Ɋy����ł���B�����O�ɁA�������ɂ�������Ă������������Đ��Ȃ����H�炦�I�i���t�������Ă��݂܂���j�Ƃ����قǂ̐������I�I
�m���ɂ��܂�ɉ���M��̂́A���y�Ƃɑ��Ď��炾�Ǝv���B�����炱���A����̎����ł́u�~���[�W�V�����v�������Ă��ꂪ�ԈႢ�łȂ����Ƃ��m�F�������B�������A����ł���l�̃I�[�f�B�I�t�@���Ƃ��ẮA�����ɉ���ς���y���ޕ������̕����A������ڍ��������y��������n���Ɉ����B�Ƃ͌����A���̓I�[�f�B�I�@������\�t�g��ꡂ��ɑ傫�Ȗ��͂������鎿�Ȃ̂ŁA���͂��������ŗǂ���������ǂ��\�t�g�����Ȃ��̂��ŋ߂̔Y�݂̎�ɂȂ��Ă���B
���q�l��F�l�ɒ��ɂ́A�����̃V�X�e���̋͂�����́u����v��T�������āA�����ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ��Ɩ����̂悤�ɃV�X�e����������A�����̃V�X�e�������L���A���邢�͔��������A�A�N�Z�T���[�Ń`���[�j���O���āA���D�̒��Ԃɂ������āu�ǂ�����I�H�v�O���ǂ��Ȃ����H�ƈӌ����f���A���ɂ́u�����Ă�?�v�A�u�����Ă�H�v�Ȃ�Ă���Ă���҂�����̂����i�����̂͂����������j�A�ŋ߂́A�V�X�e����M����Ԃ���������A�����̍D���ȉ��t���A�����̋C�ɓ��������Ŗ炵�A�����̗܂𗬂������B�ƍl����悤�ɂȂ����B
����́A�����ĔN������ăV�X�e����M��G�l���M�[���Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�R���ق̉����ǂ�ǂ�i�����āi�{�l�͂����v���Ă���j�A�{���ɐ��������Ƃ��Ė������Ɗ����̃G�l���M�[�ɖ������ӂ�Ă���Ɗ����Ă��邩�炾�B
�G�l���M�[���A�������A�F�ʊ��A�A�[�e�B�X�e�B�b�N�Ȃ܂ł̑N�₩�ȕ\���́BAmbrosia
2000��Ampzilla 2000�̑g�����́A���̑f���炵�������ɋ����Ă��ꂽ�B���y�����߂́A���y���y���ނ��߂́A�l����L���ɂ��邽�߂̃T�E���h���ǂ�Ȃ��̂ł��邩�H���́A���̃A���v���瑽�����w�Ԃ��Ƃ��o�����B
���������Ӗ��ł́A����e�X�g����CA-1�́A�������≹�y�ɑ��銴�o�Ƃ����Ӗ��ł́AAmbrosia
2000�Ƃ́A���Ȃ������ꏊ�ɂ���Ƃ͎v�����u�����i�u�̍����₻���Nj����Č����ɂ����p���j�v�Ƃ����Ӗ��Ɋւ��ẮA�������Ɗ����Ă���B�������A���ɂ́ACA-1�̉��i�ƃf�U�C���ƐF�ʂɂ́A�傫�Ȉ٘_�͂��邵�A����������̔����ȉ��̉��i�ŁAAmbrosia
2000��������̂�����A����CA-1�����Ƃ͍l�����Ȃ��̂����A�I�[�f�B�I�}�j�A���z������g�����̉��h���_�Ԍ����Ă����قǂ��̉����I�Ȑ��\�͑f���炵���B���y���Ƃ����u�����܂��v�ȕ����ɓ����邱�ƂȂ��A�^�����ʂ���u�����v�ɒ���Łu���y���v���]���ɂ����A�����������킸�A���Y�����i�ɂ��肪���ȁu�[���Ȃ����ł܂�Ȃ����v�Ɏd�オ��Ȃ��������Ƃ́A�S���獂���]���������B
�����d���Ƃ����Ă͌��Ă��A���̃A���v�ŕ����u���y�v�́A�����ė₽���͂Ȃ��B��╪�͓I�ŗ������ۂ��A���j�^�[�I�ȕ����͂��邩���m��Ȃ����A����͂���Ńv���X�̌��Ƒ����ėǂ��Ƃ���������قǂ��B����CA-1����Ambrosia
2000���D�ނ̂́A�����}�K�ɂ��������̂����A�|�p�̕\���ɂ����āu�ʎ��v�́u���ہv���z���邱�Ƃ͏o���Ȃ��ƍl���鎄�ɂƂ��āA���ɂ́u�ʎ��v��ڍ����Ă���悤�Ɋ�����CA-1�����ɂƂ��Ắu������̃A���v�v�ł͂Ȃ��Ɗ����邩�炾�B
CA-1���������Ă����̂́A���������Ă����͍̂ō��́u�ʎ��v���Ǝv���B������A�I�[�f�B�I�̒��_���u�ʎ��v�ɂ���ƍl������ɂȂ�A���̃A���v�́A�ō��̑I�����Ǝ��M�������Ă��E�߂ł��邾�낤�B�Ȃ��Ȃ�A�������������ʼnߋ����ĂȂ��قǁA���́u�ʎ����\�v�́A�ԈႢ�Ȃ��D��Ă���̂�������B���邪�܂܂��A���邪�܂܂Ɋ�����I�[�f�B�I��ڍ������Ȃ�A���̃A���v����x�����Ă݂���Ɨǂ��Ǝv���B�����ɕK���u��̓����i��̒��_�j�v��������Ǝv���B
�����āA�Ō�ɕt�����������̂����A���̓A���v���I���A���|�[�g�̍쐬�̂��߁gCA-1�̎����h�����Ĝ��R�Ƃ����I�Ȃ��Ȃ�A���̃A���v���g�^��ǃA���v�g���Ǝ��������ď��߂Ēm�������炾�B����́A�����m��A�����z������A�^��ǃA���v�̉��Ƃ͂܂�ňႤ�B�ǂ��炩�Ƃ����A�ō����̃g�����W�X�^�[�A���v�̉��ɋ߂��B�B�������Ȃ��A�X�g���[�g�ŁA�f���炵���g���h���ǂ��B����ȉ����g�^��ǁg����o����Ƃ́A���̋Z�p�͂́A�܂������Ȃ����Q�ɒl����B
�㏑��
����̃e�X�g�̖ړI�́ACA-1��Ambrosia
2000�̉������o�r�W�T�O�O�^�r�������������Ŕ�r���邱�Ƃɂ���āA3��̃A���v�̓�������薾�m�ɂ��邱�ƂƁA�����O�̂o�r�W�T�O�O�^�r�������������̉����̍ŏI���������̂ł����A���̖ړI�͏\���ɒB���ł����Ɗ����Ă��܂��B
�c�O�Ȃ���A�Ӑg�̏�M�����߂ă`���j���O��������̂o�r�W�T�O�O�^�r�������������̃f�W�^�����͂̉����́AAmbrosia
2000 +�@Ampzilla 2000�̐��E�ɋ߂Â����Ƃ͏o�����̂ł����A��Ƃ��Ă�����z���邱�Ƃ͏o���܂���ł����B������������`�u�A���v�̃`���[�j���O���f�����悤�₭������Ambrosia
2000 +�@Ampzilla 2000�̐��E�ւ���ȂɊȒP�ɓ��B���Ă��܂�����ʔ���������܂���B�ł��A���͏�������������Ȃǂ��Ă��܂���B���y���y���ނ̂ɂ��A�I�[�f�B�I���y���ނ̂ɂ��A���̈Ⴂ��m��̂ɂ��A�œK�̐��i�ݏo�����Ɗ����Ă��邩��ł��B�o�r�W�T�O�O�^�r�������������̂V�D�P�����_�C���N�g���͂́A�t�F�C�Y�e�b�NCA-1�Ɠ����u�ʎ��v�̐��E�������ɂ��܂��B�f�W�^�����͂́AAmbrosia
2000 +�@Ampzilla 2000�̎����x�ȁu���ہv�̐��E�������Ă���܂��BCA-1��Ambrosia
2000 +�@Ampzilla 2000�̉��y�Č��̕����̈Ⴂ���o�r�W�T�O�O�^�r�������������́A���ōČ��\���ƁA����̃e�X�g�Ŋm�M�ł�������Ȃ̂ł��B
�e�X�g���I���āA�Ō�ɂ�����x�o�r�W�T�O�O�^�r�������������̃f�W�^�����͂̉����Ă݂܂������A�g�����W�X�^�[�A���v�Ȃ̂ɂ�������炸�A�ǂ��Ӗ��Ő^��ǃA���v�I�ȁu�Â��v�����������āA�A�^�b�N�̋����y��̉��͏����݂��ĕ������邱�Ƃ����邩���m��Ȃ�����ǁA�{�[�J���̕\���͂Ɋւ��ẮA���镔���ł�Ambrosia
2000 +�@Ampzilla 2000�������X�����A�f���P�[�g�Ńh���}�e�B�b�N�ɂ��犴���邱�ƂɋC�Â��܂����B���ɉ��ʂ��i�����ꍇ�A���̍��͂قƂ�ǂȂ��Ȃ�̂ł��B����Ȏ��ɂ́A�����ʂł����y�������ĕ������Ȃ��悤�Ɉӎ����Ē��ቹ�̗ʊ��ɂ�������Ă���o�r�W�T�O�O�^�r�������������̗ǂ�����������邩��ł��B�������A�o�r�W�T�O�O�^�r�������������̉�H�\���Ɖ��i�ɂ́A���E�����邽�߁A�����ȃZ�p���[�g�A���v�Ƃ͉������������Ƃ́A���ꌾ���Ȃ��ł������Ȃ��Ƃ��ƒ���ʼn��y���g�y���܂���h�A�g�y������������\�́h�Ɋւ��ẮA���M�������ĕۏł��܂��B�o�r�W�T�O�O�^�r�������������́A����܂ł�AIRBOW���i�ɂ������ĉ��y�����������Ȃ�悤�ȁA�`���[�~���O�ȉ����Ɏd�オ���Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B
Ambrosia 2000 +�@Ampzilla
2000�̐��E��m��A���̑f���炵���Ɠ����ɁA����܂Ŕ|���Ă������������X�����Ƃ����I�[�f�B�I�I�C�����[�W�����̐��E��������ė~�����Ƃ����A�~����Ȏ��̊肢�́A�o�r�W�T�O�O�^�r�������������Ɍ������܂����B
Ambrosia 2000 +�@Ampzilla
2000��CA-1�Ƃ����A�f���炵���u��i�B�v�ɏo������Ƃ��A���̒��̕����������ɉ�t���A�����Ă����̑f���炵���������ƈ������i�Œ������Ƃ����C�������������Ă��܂��B���ꂪ�A�ŐV��AIRBOW�̉��ɐ�������čs���̂ł��B�������AAIRBOW�����ł͂Ȃ��A��i�ق̃I�[�f�B�I�V���b�v�Ƃ��Ắu���l���v���L���Ă����ł��傤�B
�����I�ȑf���炵���u��i�v�ݏo���Ă��ꂽ���[�J�[�Ƃ����͂��Ă��ꂽ���ʋƎ҂ɐ[�����ӂ��܂��B�����āA�ǂ�ȂɗD�ꂽ�I�[�f�B�I�@����A�f���炵�����y�ݏo���c���Ă��ꂽ�~���[�W�V���������Ȃ�������́u���v�ɂ����߂��Ȃ��ƌ������Ƃ������ĖY��Ă͂����܂���B���ɂƂ��ẮA�g�����h�����߂đ㉿��ɂ��܂Ȃ��f���炵�����q�l�Ə����邱�Ƃ��A�l���̉����̊y���݂ł��B���肪�Ƃ��������܂��I

�Ō�Ɍ��������邽�߂ɂЂƌ��t�����������Ǝv���̂����A�u���������v��各�����Ă���Ǝ��鎄�����R���قŖ炵�Ă��鉹�́A�u�������v���Ă��邪�̂Ɂu�����Ő��X�����R���T�[�g�̍ĉ��v�ɔ��ɋ߂��B���������Ă���̂ɃR���T�[�g�̍ĉ��ɋ߂��H���t�̏�ł́A�Ђǂ��������Ă���̂����A�l������_���Ƃ��ẮA���ʂ��Ă���̂��B
�����A�v���̉��y�Ƃ�A�}�`���A�ł��{���̒��_��ڍ����Ă���悤�ȕ��i���y�ɑ��ĕ��X�Ȃ�ʎv�������������j���R���قɗ�����ƁA���ɗ܂��������āA�����́g�����������h�Ƃ�������邱�Ƃ�����B�����܂ł��Ȃ��A�ނ�̖��Ƃ́A���łɋA��ʐl�ƂȂ����h�����鉉�t�Ƃ̃R���T�[�g���g�{���ɖڂ̑O�̉��t���Ă���h�Ƃ����v���Ȃ��قǂ̑f���炵�����X�����őh�点�邱�Ƃ��B���̒����Ȃ�Č��B���ꂪ�������Ă���Ƃ����̂ł���B�R���ق̉��́A���ɔ��Ɍ��������y�Ƃ������Ă����u�����t�v�Ɛ������Ȃ��Ƃ�������������قǂ́g���^�̃��A���e�B�[�h�Ŗ��Ă���炵���̂��B�������A�l�̎v���ɂ͍�������Ǝv�����A���ۂɊy������t����ނ�̈ӌ��ɑ傫�ȊԈႢ�͂Ȃ����낤�B
�u�����v��Nj����Ă��Ȃ��̂ɂǂ����āu�R���T�[�g�̒����ȍĉ��v���\�Ȃ̂��H�u�����v����ԏd�v�ȃ|�C���g�Ȃ̂ŁA�o�������킩��₷���H���������������B
���̌����u���������Đ��v�Ƃ́A�^������Đ����܂ł́u��̘c�݂����Ă��܂��v�Ƃ����l�����A���Ȃ킿�u�Q�C���A�I�u�A���C���[�v�Ƃ����l�����ł���B���̍l�����ɉ����āA�V�X�e���̘c�݂��\�Ȍ����苎���Ă��u�S�n�悢���y�v�́A�����ĕ������Ă��Ȃ��B�ߋ����牽�x���J��Ԃ��Ă��邪�A�I�[�f�B�I�ɂ�����R���T�[�g�̍ĉ��Ƃ����ړI�ɂ����āu�c�݃[���̐��E�v�́A�����s�\������Ȃ̂��B
�܂��u�^���v�Ƃ����v���Z�X���l���Ă݂悤�B�u�c�݂Ȃ��^���v�Ƃ����v���Z�X���������邽�߂ɂ́A�}�C�N���u�����v������̂܂܁u�d�C�M���ɕϊ��\�v���Ƃ����O�s�������A���́A�}�C�N�����𑨂������_�ł��łɁu���v�́A�C���s�\�Ȃقǁu���̉��v�Ƃ͈���Ă���i�Ǝ��͍l���Ă���j�B�Ȃ��Ȃ�A�}�C�N�̃G�������g�i�_�C���t�����A�U�����j�ɂ́A�ʐςƎ��ʂ�����A�ʐςƎ��ʂ����G�������g���u�c�݃[���v�ʼn���d�C�M���ɕϊ����邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ����炾�B�����A�}�C�N�����z�I�Ɂi�c�݃[���Łj���g��d�C�M���ɕϊ��ł���Ȃ�A���ׂẴX�^�W�I�̃}�C�N�́u����̃}�C�N�v�ɂȂ��Ă���͂����B�u�}�C�N�Ɍ�������v����́A���Ȃ킿�}�C�N���u�c�݃[���ʼn���d�C�M���ɕϊ��ł��Ȃ��؋��v�ł���B�������A�����̃I�[�f�B�I�Z�p�҂́A����ȊȒP�Ȏ����ɂ����u�^���v������Ȃ��B
�����āA�X�s�[�J�[�̃G�������g�i�����́j�����l�ɖʐςƎ��ʂ����邩��A�ǂ�������Ƃ��Ă��u�X�s�[�J�[�ɂ�鉹�̘c�݂͔������Ȃ��v�B����ǂ��낪�A�I�[�f�B�I�V�X�e���S�̂ł͐��\���ȏ�̘c�݂������Ă���̂��B�c�݂��炯�i�R������j�̋L�^�|�Đ����u�B���ꂪ�u�g���e���I�[�f�B�I�̐^���̎p�v�ł���B
���x�́A�u�����v�l�ԑ��̘b�ɓ��낤�B���_���猾���A�l�Ԃ́u���̒������v�͑����Ƃ͂܂���������āA���̂������u���I�v�ł���B�Ⴆ�A�l�Ԃ������̂́A�E�̎��ƍ��̎��́u�ۖ��v�ł��邪�A���ꂼ��́u�ۖ��v�ɂ́A���ȊO�̏����������ɉ��������Ă���B������u���`���v�ł���B�l�Ԃ������Ă���Ƃ��A��S�̂������Ă��邵�A�̂̍��������Ă���B�����̋������u���`���v�Ƃ��āA�ۖ���k�킹��̂��B���̉��ʂ͑����ɑ傫���B�����������ɂ����l�̂��߂Ɂu���`���v�𗘗p�����X�s�[�J�[�����݂��邭�炢�ł���B�X�s�[�J�[�͑O����ʂ��邪�A�w�b�h�z���͓��̒��ʼn�����B������u���`���v�̂���Ȃ����傫�Ȍ����ƂȂ��Ă���B�܂�A�E�̉����E�̎��ɂ�������Ȃ�����A�w�b�h�z���̉��́u�O����ʁv���Ȃ��̂��B
��������ăw�b�h�z���̉���O����ʂ�����f�W�^����̕��@���l�Ă���Ă���ƕ��������Ƃ����邪�A������������u�^���T���E���h�v���u�`�u�A���v�����o���������c�ݐ����v���������萶�X�����ł���Ƃ����ؖ��ł�����B�܂�u�f�[�^�[�I�Șc�݁v���A��Ɂu�l�ԂɈ���������v�Ƃ͌���Ȃ����A�t�ɂ����L���ɗ��p������@����l�Ă���Ă���̂��B
���i�A�������������Ă���u���v�́A������}�C�N�������Ă���悤�ȁu�������v�������Ă͂��Ȃ����A�����������߂�u�����v�����l�A����ȁu�������v�́A�K�v�Ƃ��Ȃ��B�t�Ɂu�������v�����߂���߂�قǁu���v�́A���X�����������₽���Ȃ�����A������ꂵ����A�Ƃɂ����u���ɍ���Ȃ��v�Ȃ��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A�A���v��b�c�v���[���[�̘c�݂���苎��ƁA�t�ɑ��̕����̘c�݁i�}�C�N��X�s�[�J�[�́j���A��薾�m�ƂȂ邩��ł���B����́A�����g���^���ƍĐ��̎������s������ꂽ���ʂƈ�v����B
�܂�A�^�����ꂽ�����u�l�ԂɂƂ��Đ��X������������v���߂ɂ́u�Ӑ}�����c�݁v��^���Ă��ق����u�c�݂���苎��v�����L���Ȃ̂��B�����āA���́u�Ӑ}�����c�݁v���ǂ̂悤�ɍ��o�����H���ꂪ�u�I�[�f�B�I���t�Ɓv�ɋ��߂��鎑���ł���A�Z���X�Ȃ̂��B���ꂪ�A���́u�I�[�f�B�I���t�Ɓv�́A�ʐ^���B��̂ł͂Ȃ��u�ʐ^���z����G��`���Ȃ�������Ȃ��v�Ǝ咣���鍜�q�ł���B
�����_�Ŏ��́A�u�R���T�[�g�̐��X�����ĉ��v����������I�[�f�B�I�̂�����ɂ��āA���̂悤�ɍl���Ă���B�I�[�f�B�I�V�X�e���͈�̊y��ł��肻�́u�S�̖̂�v���u�����āi�`���[���i�b�v�������j�v���Ă�邱�Ƃ��ł��d�v���ƁB�ǂ������ˏo���Ă͂����Ȃ��B
�����A���Ȃ��̃V�X�e�����S�̂ɃX���[�Ȃ�A����ɑ��Ă��Ȃ��͈�a��������Ȃ����낤�B�Ȃ��Ȃ�u���R�E�ŋN����̂Ɠ������̗i�����I�ɐ��������̕ω��^�j�v�ɑ��āA�l�Ԃ͋����قNJ��e�ł��邩�炾�B�܂�A�c�݂�������̂͂��܂�Ȃ����A�u���R�ɂ͋N���Ȃ����̕ω��v�����������Ă͂����Ȃ��̂��B�l�ԂɂƂ��āu�s�����ȉ����I�[�f�B�I�L���v���H�v�Ɠw�͂ɂ���ď����A�l�ԂɂƂ��āu�{���ɂ����������Ȃ����v���o���̂��u�I�[�f�B�I���t�v�̐^���ł���A�ړI�Ȃ̂��B�Ō�ɂ�����x�������A�I�[�f�B�I���t�ɂ����āu�Q�C���A�I�u�A���C���[�v�́A���_�I�ɂ��琬�����Ȃ��B����Ȃ��̂ɂ������I�[�f�B�I���[�J�[�́u�����H�炦�I�v�ł���B
���́A�����̃V�X�e���Łu�ʐ^�ȏ�v�ɖ{���Ɍ�����u�G�v��`�������B�����オ�����u�G�v���v���̉��y�ƁA���t�Ƃ̐R����Łu���X�����v�ƕ]������邱�Ƃ́A�ƂĂ��������A�����ĂȂɂ������h�Ɋ����Ă���B���̌h������A���͖S�����t�ƒB�ɂق�̏����ł��u��i���j�v��Ԃ����C�����ɂȂ�邩�炾�B