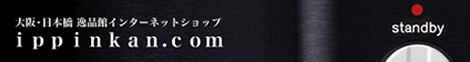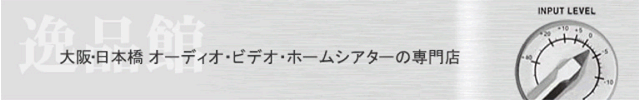
逸品館メルマガ バックナンバー 031
皆さまこんばんは、いかがお過ごしでいらっしゃいますか?先週より、体調管理のために自転車通勤を始めました。約5キロの道のりを30分弱かけてゆっくり通っています。通勤を車から自転車に変えると、視点が変わってなかなか興味深いです。空気の香り?街の臭いが変わるのを感じるのも新鮮です。最初は、自転車を漕ぐのに必死だったのですが、だんだん慣れるに従って走りながらいろんな事を考えるようになりました。走っているだけで、ストレスが発散し、前向きで明るい気持ちになれるのが不思議です。心なしか、頭の回転?も良くなるようで仕事もはかどる気がします。それにしても、今年は本当に暖かいです。ちょっと走るだけで汗ばんでしまいます。これから、春〜夏にかけて汗対策をどうするか?それが悩みの種です。
さて、年末より歪みのない再生を目差す「ゲイン オブ ワイヤー」という考え方は間違いではないか?という主張を続けていますが、リスニングルーム(再生環境)側から見た「ゲイン オブ ワイヤー」を否定する考え方は、菅野沖彦氏「新レコード演奏家論」で詳しく述べられています。しかし、菅野沖彦氏は著書の中でエンジニアによる編集の弊害については言及されているにもかかわらず(ルディー、ヴァン、ゲルダーの編集に疑問を感じるのは私もまったく同感)「マイクの歪み」に付いては、まったく言及していません。しかし、私は純粋に科学技術としてオーディオを考えた時に、歪みなく音を電気信号に変換できる「理想的マイクが存在しない」という観点からも「ゲイン オブ ワイヤー」という考え方は、偽理想主義だと感じるのです。
私が「究極のゲイン オブ ワイヤー=原音忠実再生」を目差していたとき、原音忠実再生の要となる「マイク」には、特に様々な改良実験を行いました。なぜなら、マイクが捉えた音が「真実」でなければ、それ以降のプロセスの忠実度をどれだけ上げたとしても「嘘の上塗り(嘘の増幅)」にしかならないからです。マイクの内部構成素子である抵抗、コンデンサーの変更から始まって、マイクケーブルやマイクスタンドの検討(何十万円もする業務用カメラ三脚をスタンドに流用したりもしました)、オーディオ用インシュレーターやボードによるマイクのインシュレーション(制振)テストに至るまで、何をやっても、どこをさわっても、マイクの音は変わりました。結論を先に述べるなら「マイクで音が変わる=マイクに個性が存在する」こと自体が「マイクは真実を収録していない」=「原音忠実再生を否定」できる証拠なのです。つまり、レコーディングエンジニアが楽器や音楽シーンに合わせてマイクを選び、ミキシングエンジニアが、好みのスタジオや編集コンソールを選ぶ時点で、すでに「情報は嘘である=原音は存在していない」と考えるのが当然なのです。
この重要な事実をないがしろにして究極の「ゲイン オブ ワイヤー」システムを完成させたとしても(そんなものは完成できるはずはないが)、それは「マイクの個性」や「編集の有様」をありのままに再現できても「原音を再現=まったく同じ音楽を再演」することは、できないのです。事実、私が最も「ゲイン オブ ワイヤー」に近づいた時の音は、自分が録音したソースを再現する限り「限りなく生演奏に近い=奏者や私が聞いても生演奏と聞き分けが付かない」レベルにまで到達しましたが、そのシステムで市販のソフトを聞くと、マイクの設置位置の不整合や編集時のボリュームの調整不足、奏者のミス、演奏の粗、などマイナス点ばかりが目について、とっても音楽を楽しめるものでは無くなったのです。その結果、私はオーディオを止めようとすら思ったのです。
これで話を終わらせても良いのですが、もうすこし技術的な説明を付け加えたいと思います。マイクの仕組みは、ご存じですか?マイクには「音を捉える振動膜(ダイヤフラム)」が存在します。このダイヤフラムが空気の疎密波(すなわち音)によって振動し、その振動が電気信号に変換されます。これが「音」を収録可能な「電気信号」に置き換える録音というプロセスです。一見、間違いがないと思える(みんなが信じ切って疑わない)この変換プロセスには、物理的に考えて「不可避な歪み(マイクによる特徴的な音の歪み)」が生じます。そして「原音の破壊」が発生するのです。
音を機械的な振動に変換する「ダイヤフラム」には、空気の圧力を受けるための「面積」が必要です。また「ダイヤフラム」にはある程度の強度も必要なため「厚みのある膜」が使われています。「面積」×「厚み」×「単位あたりの質量」がダイヤフラムの総質量となりますが、質量を持つ物体には「慣性」が生じます。つまり、ダイヤフラムには「慣性」による「よけいな運動」が常に生じるのです。この「慣性によるよけいな運動=歪み」を発生させないためには、ダイヤフラムの質量をゼロにしないとダメです。マイクに質量の存在するダイヤフラムが使われている限り、物理学の法則から考えて「原音をありのまま収録」することは不可能です。
ダイヤフラムの「面積」も、周波数の高い音声を収録するときに問題となります。音速は約340m/秒ということはご存じだと思います。周波数が1Hzの時には、1波長は音速と同じ340mですが、周波数が高くなると波長は周波数に反比例して短くなります。1KHzでは340m/1000=34cm、10KHzでは3.4cm、100Hzでの1波長はたったの3.4mmです。このたった3.4mmしかない長さの100KHzの音波を「位相のずれなく収録」するために必要なダイヤフラムの直径は、どれくらい小さければいいのでしょうか?
少なくとも3.4mmよりもずっと小さくなければなければ、ダイヤフラムによる位相のズレが生じるはずです。しかし、残念ながらダイヤフラムをそんなに小さくするとマイクの感度が低下して、使い物にならなくなります。とにかく、マイクに「物理的な質量や体積」が存在する限り、どのようにごまかそうとしても「物理的な歪み」が生じることは、避けられない事実なのです。
もし、録音しようとする空間の任意の一点に存在する1個の空気の分子の動きだけを電気信号に変換することが可能になれば、理想的なマイクとなるでしょうが、現在発売されている「ソフト」の収録には、そのようなマイクは使用されていません。
オームの法則、ファラデーの法則、シャノンの定理、それらのすべては「数学的」あるいは「電気的」に見て間違いのない事実です。それは、法則の中では「電気」が「質量」を持たないからであり「数字」は、机の上、設計図の中では「理想的」にしか振る舞わないからです。しかし、それを現実の世界(物質の世界)に出したとき「状況は一変」します。電子は導体の中でどのような動きをしているのかは、未だに解明されていませんし、物体には質量があり慣性を生じます。理論の世界では、つじつまが合っていることも、現実の世界では「つじつまが合わない=まったく通用しない」のです。この事実から目を背け声高に「理論」を振り回したところでそれは正に「絵に描いた餅」、なんの役にも立たないのです。
このように「オーディオ理論の完璧性」は、「ソフトの製作」という入り口のみならず、全体のどこを見ても「物理的に完全に破綻」しています。破綻している理論を信じて音を作っても、完全な音を再現することは不可能です。無理を押し通しているだけでは、オーディオという技術は、いっこうに向上しません。だから、理論的な説明ばかりしたがるメーカーの製品は音が悪いのではないでしょうか?
破綻している理論を補うのが「経験」です。マイクが捉えた音から、どのようにして「マイク臭さ=マイクの個性」を消してやるのか?あるいは、それをプラス方向に生かしてやるのか?アンプに必要なのは、そういう「経験による、確信を持った音作り」です。私は、デジタルアンプを評価しませんが、それはデジタルアンプでは「アナログアンプで出来るような音作り」が上手くできないからです。技術的に見れば、デジタルは理想のオーディオのように思えるかも知れませんが、実際にはアナログより音は悪い場合がほとんどです。音が悪いというのが言いすぎであれば、最高級のアナログほど「深みのある、芸術的なアンプは、フルデジタル回路では作れない(少なくとも現時点では)」と言い直してもかまいません。フルデジタルを目差すのではなく、アナログ回路を適度に組み込んだ、ハイブリッドデジタルアンプなら、アナログアンプのようなエレガントな音作りも可能になるかも知れませんが、そこまでしてデジタル回路をアンプに組み込む必要は、将来も生じないと思います。
つまり、オーディオ技術の最高峰に立てるのは、デジタルではなく「理論を経験によって補うことが出来るアナログ技術」を極めたメーカー(デジタル技術を信奉するメーカーではあり得ない)だけと断言できるのです。最近の高額製品の音質が芳しくないのは、アナログを軽視しすぎているからではないでしょうか?
「レコード」から「CD」に変わったとき「明らかに音が悪くなった=音楽性が低下した」という現実に目を背け続けている、現代のハイエンド・オーディオ機器やオーディオ・メーカーには、明るい未来はやってこないでしょう。すでに述べたように彼らが学ぶべきは「技術(デジタル)」ではなく「正しい音楽的な経験や体験(アナログ)」なのですから。
逸品館の3号館には、過去に試聴したカートリッジのコレクションとビンテッジの真空管を展示しています。それは、どんなに時代が進んでも逸品館は、決してオーディオが歩んできた素晴らしい道=アナログ文化を捨て去らない、忘れはしないという意思を表しているのです。 http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/shop_picture/3_AD.JPG
![]()