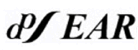 EAR 912 音質評価
EAR 912 音質評価

EAR 912 \1,980,000(税別) (製品のお求めはこちらからどうぞ)
製品の概要
EAR社の創立25周年を記念し、またEARのチューブ・テクノロジーの集大成として作られたプリアンプが912です。最高級プロ仕様のMCヘッドトランス付フォノイコライザーを搭載しLINE入力PHONE入力の双方で、最高の真空管サウンドを実現します。主な仕様は次のようなものです。
内蔵 チューブプリアンプ フォノイコライザー部
■入力:MM/MC 2インプット■インプットインピーダンス:MM=47kΩ ■オーバーロードマージン:28 ■MCセクション:40Ω、12Ω、6Ω、3Ω ■ゲインセッティング3ポジション:0、-6、12dB ゲイン:MM=2.4mV ゲインMC=0.24(70dB)、0.15(73dB)、0.1(76dB)、0.06(80dB)mV@1kHz ■RIAAアキュラシー:±0.2dB、30Hz-20kHz ■S/N比:68dB(2.4mVアンウェイト)
その他の仕様
■消費電力:30V ■使用真空管:PCC88×5 ラインアンプ部 ■最大出力:6V、 600Ω ■入力:2フォノ、3ラインレベルRCA/2ラインレベルXLRバランス、テープ ■ラインアンプゲイン:14dB ■S/N比:-90dB(1V) ■ディストーション:0.1%以下(1kHz 3Vアウト) ■周波数特性:20-20kHz、+0-0.3dB ■サイズ:W490×D135×H270(mm) ■重量:13kg
 ■リモコン付属
■リモコン付属
 |
 |
|
||||||||||||||||
|
<明るい>
- - - * - - - - - <暗い> |
<柔らかい> - - - * - - - - - <硬い> |
<総評> 試聴機が届けられる前と届けられたとき、正直これが「198万円」という印象がぬぐえませんでした。 しかし、その音を聞いた後ではその価格が「高い」とは思えなくなってしまいました。今回のテストではCDプレーヤーとトランジスター・プリメインアンプの間に繋いで音質をチェックした(プリアンプのテストでは、音質がどの程度"失われるか?”を確認するため、必ずこのチェックを行います)のですが、驚いたことにCDプレーヤーの価格が一桁上がった!?のではないかと思えるくらい音が良くなったからです。 単なる音量/音質調整器としてのプリアンプを超えた、「音を良くできる(失われた音を復元できる)」プリアンプ(アナログコンピューター)としての能力を兼ね備えプリアンプがEAR 912です。 |
||||||||||||||||
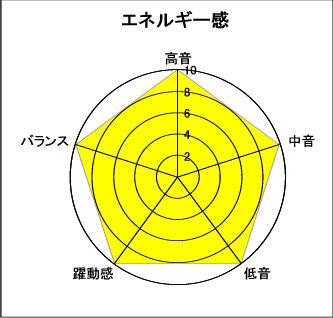 |
 |
|||||||||||||||||
|
これ以上の音はあるかも知れませんが、これ以上の音を望まないという意味ですべての項目を満点の10点としました。 |
||||||||||||||||||
使用機材
912のLINE入力の音質テストは、CD/SACDプレーヤーに AIRBOW X05 Ultimate、アンプにトランジスター方式の AIRBOW PM11S2 Ultimateを使い、912を使わずにX05 UltimateとPM11S2 Ultimateを直結したときの音質と、間に912を入れたときの音質を比較しました。Phono入力の音質テストは、アナログプレーヤーNottingdam Interspace HD(カートリッジは、Phasetach P-3)を912にダイレクトに接続して行いました。スピーカーは、Vienna Acoustic The Musicを使っています。
|
スピーカー |
レコードプレーヤー |
カートリッジ |
CDプレーヤー |
プリメインアンプ |

|
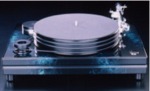
|
 |
 |

|
音質テスト結果
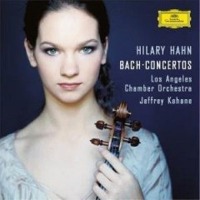
Hilary
Hahn Bach Concertos
|
912を通すと音が浄化されます。 デジタルとトランジスターの組み合わせでは、避けられない「粉っぽさ」や「とげとげしさ」が完全に消え、高域が透き通ってバイオリンの倍音が美しく伸びてゆきます。響きに潤いが出て、部屋の天井を取り払ったように大きく音が上に広がります。 電気的に感じられた倍音の硬さが取れ、弦楽器の高音がまるで生演奏のようにスムースでスィートになります。 どうすればこんな音が出せるのか?全く理解できませんが、アンプやスピーカーが消えて演奏会場に居合わせているような雰囲気です。 過去に数多くの真空管プリアンプを聴きました。驚くほど音が良い製品も沢山ありましたが、これほど「色づけを感じさせないプリアンプ」は今までに聴いたことがありません。優しく透明で、スムースな音。解像度感も抜群です。 |

Orange
Pekoe |
濁っていた響きが整理され、各々の楽器の音がクッキリします。ボーカルの定位が改善し、口元が引き締まります。 ボーカルと伴奏の前後関係が改善し、立体感が増しています。 中でもボーカルの明瞭感の改善は驚くほどで、CDをSACDに変えたくらい音が良くなります。最高の電源ケーブルとラインケーブルを奢っても、これほどまで音質が改善するか?俄には信じられないほど、音が良くなりました。 極端な例えではなく、20万円のCDプレーヤーを200万円のCDプレーヤーに変えたくらい、音が良くなります。 シンバルの切れ味や響きのリアルだけではなく、すべての音の実在感とリアルさが大きく向上します。クラスの違うシステムを聴いているようです。プリアンプだけでこれほど音が良くなるのは、驚きを通り越して衝撃ですらあります。 |
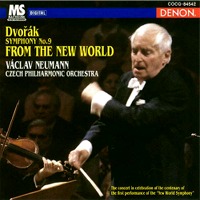
ドヴォルザーク
交響曲9番 |
響きの長さ、演奏会場のサイズがまるで変わります。 楽器の織りなすポリフォニックの構造の精度、大きさ、美しさは912を使う前とまるで別物です。現在使っているCDプレーヤーは58万円のX05/Ultimateですが、このプレーヤーをトップモデルのUX1SE/Limited+Antelope OCXの組み合わせにしても、ここまで音は良くならないかも知れません。 CDで聞き比べましたが、912の音質改善をたとえるなら「CDがSACDになったよう」ではなく、「CDが高音質レコードになったよう」という例えが正しいと思います。すべてにおいて改善が著しいので、どこがどうなどと個別に音を評価できません。 外観は素っ気なく少々安っぽい感じも受けますがその音は素晴らしく、メーカー希望小売価格を遙かに超える価値を感じます。真空管プリアンプでこれほど感動したのは、10年以上前に中古で入荷したAudio Research SP10を聞いて以来かも知れません。 同価格帯あるいは遙かに高額なトランジスター・プリアンプを聴きましたが912と比べれば、私にはそれがただの「音量調節器」としか思えないほど912が素晴らしい音に感じられました。 |
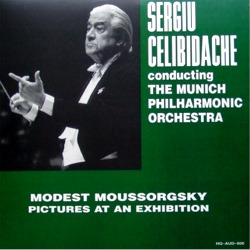 ムソルグスキー |
かなり高性能なプレーヤーとカートリッジを使ったにも関わらず、解像度はCDの方が少し高く感じられました。 響きの透明感や、ポリフォニックの分離もCDがレコードを上回ったように感じました。何よりも中低音の厚みでレコードはCDを大きく上回ります。30cm口径のウーファーが38-40cmにサイズアップした感じと言えば、それが伝わるでしょうか?レコードらしく低音がすこし緩く響きが残るのですが、そのパワー感、押し出し感からは、超大型パワーアンプを連想させます。その低音がAIRBOW PM11S2/Ultimateから出るのですから驚きです。また、少しの濁りやエッジの丸さは感じられるのですが、CDと比べ有機的に感じる”音の濃さ”は凄まじいものがあります。 しかし、最新デジタル機器の素晴らしい音に慣れた今となってはサーフェイスノイズやスクラッチノイズが音に入り、チャンネルセパレーションが悪く、定位も悪いレコードを聴こうとは思えません。音は素晴らしいですが、デジタルの音もすでにレコードを凌駕するほどに進歩したからです。 特別な日にノスタルジーに耽りながら、お気に入りのレコードに針を落とす楽しみは格別ですが、普段はCDで十分です。音も良いですし、音楽もきちんと伝わり、何よりもレコードを痛めるという心配から解放され、より深く音楽に集中することができるからです。 |
2011年 10月 逸品館代表 清原裕介
|
||||||||||||||||||||||||||
