■各種コンテンツ
■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部
オフィシャルサイト
HEGEL P30 H30 音質 比較 評価 販売 価格 テスト
北欧ノルウェーのオーディオメーカー HEGEL (ヘイゲル)新型セパレートアンプ
P30 H30 をテストしました。
2009年発売商品を含めで実施した、最新のHEGEL全製品音質テストはこちらからご覧頂けます。
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
試聴リポート |
||||||||||||||||||||||||||
|
試聴ソフト
試聴機材
最近懇意にしているエレクトリだが、意外に営業は積極的ではない。それは、逸品館がかなり頑固なセレクトショップだといことも理由だし、100万円を超えるような高額製品はそれほど数が出ないことも原因かもしれない。でも、私にとってそれは聞きたい製品だけを選んでじっくり試聴できるのでありがたいことだ。 年が明けて少し時間に余裕ができたので、これまで聞けなかった製品を順次聞いてみることにした。今回テストするのは、逸品館が自信を持ってお薦めしているノルウェーの新進高級オーディオブランドHEGELのセパレートアンプ。プリアンプ P30は80万円、パワーアンプH30は160万円というかなり高額な製品だ。 この高価な価格を考えるとHEGELの外観は、かなり素っ気ないと思う。事実、P30はHEGELのもっとの安いプリアンプH2A(30万円)との仕上げはほとんど同じだし、さらに言うならわずか4.8万円の小型DAC H10とも遠目では変わりなく見えるほど高級感は感じられない。同じ黒一色でも、初期のマークレビンソンのようなお洒落なレタリングでも入れてあげれば印象はがらりと変わるのだろうけれど、それにしてもHEGELの見た目は、高級オーディオの中でも地味だと思う。届いた試聴機を開梱し、オーディオボードに乗せても印象は変わらない。この黒い塊が80万円?160万円?、通常の感覚では到底理解できないだろう。しかし、その思いは音が出た瞬間にがらがらと音を立てて崩されてしまった。 スピーカーはいつも試聴に使うBEETHOVEN-CONCERT-GRAND(T3G)を繋いだのだが、出てくる音はそのお隣に設置しているThe Musicのものだったからだ。アンプでスピーカーの鳴り方ががらりと変わることは何度も経験しているが、今まで3号館のBEETHOVEN-CONCERT-GRAND(T3G)からこれほどの音を出したアンプは初めてだ。お気に入SST Ampzillaはもっと開放的で動的な音をBEETHOVEN-CONCERT-GRAND(T3G)から絞り出す。だから、躍動感からならば、Ampzillaを高く評価する気持ちは変わらない。しかし、P30 H30はその思いを軽く覆すほど「高性能」で「ぎっしりと詰まった音」を出す。BEETHOVEN-CONCERT-GRAND(T3G)から出る音が上位モデルのThe Musicと聞き違えるほど緻密でワイドレンジな音なのだ。あまりにもBEETHOVEN-CONCERT-GRAND(T3G)の鳴り方が違うので、試聴中何度もスピーカーの接続コネクターを確認したが、当然間違ってはいなかった。
最近のPOPSやROCKのソフトはお世辞にも録音が良いとは言えない。それは平均音量レベル(音の大きさ)を上げる目的で音源にコンプレッションが掛けられているためだ。小さなダイナミックレンジ(音量差)の間に音をぎゅうぎゅう詰めにされたソフトは、よほどきちんとした装置で鳴らさなければ、音が団子になってうるさい音になる。 この問題児のソフトをP30 H30は、見違えるような高音質で再現した。まず驚かされたのは冒頭のコーラスとシンセサイザーの重なる部分だ。これまで聞いていたアンプでは、BEETHOVEN-CONCERT-GRAND(T3G)では良好な分離感を得るのが難しかった。しかし、P30 H30はまるでスピーカーのグレードを大幅に上げたような「ほぐれた音」でこのソフトを鳴らす。音の数、楽器の数、高音の切れ味と低音の量感や押し出し感のイメージは、The Musicから出る音に等しい。だから、BEETHOVEN-CONCERT-GRAND(T3G)をThe Musicと聞き違えたのだ。 周波数レンジが広く、音が細かく、分離も素晴らしい。中域に固まっていた音を上下に伸ばし、それぞれの音の間に「隙間」を作る。「太い一本の線」だと思っていた音が、実は「細い線が複数集まって構成されていた」ことに気づく。濁った音が複数の細かい音に分解される。このドラスティックな変化は、通常スピーカーを大幅にグレードアップしなければ味わえない。CDプレーヤーやケーブルのグレードアップよりもずっと大きい変化をP30 H30はもたらすように感じる。 スピーカーを一回り大きくしたような量感と、エンクロージャーを強化したように引き締まった低音が出る。中音高音はユニットのグレードを大幅に上げるか強力なマグネットを使って、入力される信号を完全に音へ変換するイメージの鳴り方をする。テキスタイル・ドーム型ツィーターから、まるでホーンツィーターのように空気の揺れが直接肌に伝わってくるような音が出る。スピーカーとリスナーの間の空気の影響を消し去って、音が体に直接ぶつかって来る。スピーカーを完全にその能力以上に「鳴らし切っている」感じだ。 曲が進み、様々な音が入るとP30 H30の長所が「物理的な音質(聞こえるか?聞こえないか?)」だけでないことが聴き取れるようになる。楽音の「音色の違い」や「力の強弱」、「雰囲気の差」がきっちりと再現され、スーパーHiFiな音だが、同時にリアリティーも驚くほど高い。「味わい」に逃げるのではなく、「音質を高める」ことで直球勝負する、テクノロジーの進歩を感じさせる音だ。HEGELがこれほどまで技術水準の高いメーカーだとはこれまで気づかなかった。あるいは、P30 H30で大きく進歩したのだろうか?P30 H30が奏でる音楽をしばらく聴いていると、気に入らなかった黒い塊の外観すら控え目で魅力的に見えてくるから不思議だ。
この曲でも「しっかりした音」という印象が強い。バイオリンの音には張りと芯があり、金属振動板のツィーターを使っているような「強い音」がBEETHOVEN-CONCERT-GRAND(T3G)から出る。ピアノのアタックにも強い芯が感じられ、重量物が振動している重みのある感じがきちんと出る。 空気感や楽器を取り巻く空気の繊細なディティールの再現性は直接音ほどではなく、ホールの残響感や間接音の再現はやや苦手なようだ。クラシックを聴くには高域の艶、響きが少しドライ過ぎる嫌いがある。このソフトを鳴らすのはAmpzzilaがHEGELよりも上手だ。 送られてきた信号を淡々と音に変換し、余分な振動(エコー)を残さずユニットをぴたりと止めているイメージ。ユニットを無駄に動かさないから付帯音は非常に少なく、それが仇になってスピーカーの個性を少し薄めてしまう。このアンプが似合うのは現代版高性能スピーカーだろう。Tannoy Stirlingなどの「箱を鳴かせて音を作るスピーカ−」には、不向きだと思われる。 ちょっと演奏が窮屈に聞こえたが、このあたりはケーブルやボードなどでチューニングし、好みの音を作れば解決するだろう。とにかく、基本性能が抜群に高いことは疑いようがない。
ユニットがスピーカーから外れて飛び出すほどの勢いで、音がぐんぐん前に出る。ピアノの打鍵感、ベースの押し出し感、シンバルの飛んでくる音、まるで楽器がすぐ近くにあるような音だ。 しかし、やはり間接音成分は少なめで「ドライ」な印象は変わらない。もっと「熱い音」にしたくて、ここで少しケーブルやボードでチューニングを試みることにした。 その前に最初のセッティングをご紹介しよう。 CDとプリアンプは、AIRBOW MSU-Mightyで接続。
プリアンプとパワーアンプは、AIRBOW MSU-X Tensionで接続。
電源ケーブルは、プリアンプ、パワーアンプ共にAIRBOW KDK-OFCを使った。
※P30 H30に付属している電源ケーブルは、非常にお粗末なので「通電テスト用」と考えた方が良い。 まず、プリアンプとパワーアンプの接続をRCAからバランスに変えてみる。ケーブルは、X TensionからS/A lab HLBに変えた。
中高域に濁りが生じ、音の切れ味も大きく後退する。きりりと澄み切った水が、生ぬるく濁ってしまった。 バランス伝送は優れていると言われることが多いが、私はあまり賛成しない。プラスとマイナス(HOT と COLD)を個別のケーブルで伝送するため、ケーブルの変形や伸びによる「微妙なずれ」が音に反映し、今回のテストのように中高域を滲ませてしまうことがあるからだ。エネルギー感も消え、元気のないつまらない音になった。 プリアンプとパワーアンプの接続をRCAに戻し、音質改善を狙ってケーブルをX TensionからAET SIN/EVOに変える。
中高域の濁りが取れ音場の見通しと広がりが改善する。中低音の量感が増し、色っぽさも増す。でも、X Tensionで長く聞いていたせいか、SIN/EVOよりもX Tensionのさっぱり、きりりとした淡麗辛口のサウンドがP30 H30の良さをより強く引き出していたように感じられた。確認のためRCAケーブルをX Tensionに戻す。
う〜ん。困ったことにSIN/EVOよりかなり音が良い。レンジも広いし、音も細かい。これは今までのテストと結果と矛盾する。原因を考えたが3日間に分かって通電を続けたX Tensionと長く放置された後、たたき起こされたSIN/EVOが「寝ぼけていた」と考えしかない。ケーブルにもある程度の「ウォーミングアップ」は必要なのだ。 次にパワーアンプの電源ケーブルをKDK-OFCからAIRBOW CPSC-LV1に変更し、電源をAIRBOW PS-Stream4から取る。
丸まっていたピアノの倍音がすっきりと伸びやかになる。楽器と楽器の位置関係も明瞭になり、それぞれの音の濁りやにじみが激減する。音質は角が取れてマイルドになるが、密度とエネルギー感が向上するので緩くはない。ゆったりと、しかし深みと重みを持って楽器が鳴る。今まで不足すると感じていた色気が増し、場の気配が伝わるようになる。自動演奏の様だった演奏に血が通い、演奏者の心が伝わってきた。電源のチューンナップは大当たりだ。 プリアンプのボードをAB2000からWFB-0115-3に変える。
ミュートされ曇っていた様に聞こえた倍音が、美しく最高域まで伸びて行く。音が大きくなったように聞こえる。ステージの奥行きが深くなる。トランジスターアンプ特有の「圧迫感」のようなものが消えて、良質な真空管アンプのように「ストレスなく広がる音」へと変化する。楽器のアタック、特にピアノの出始めの瞬間(打鍵のごく初期)の聴き取れなかった細かい変化が聴き取れるようになる。ディスクを高音質録音に変えたような変化だ。電気的なストレスから解放されたという意味で、このチューニングもまた大正解のようだ。
チューニング効果確認のためFame Monsterを聞いてみた。音の広がりが大きくなるのと引き替えに、低音の押し出し感や音が固まって前に飛んでくるような「塊感」は後退した。ライブを基準に考えれば何もしなかった「素」の音、空間に音が凝縮された感じの鳴り方が正解だろう。しかし、コンサートを基準に考えるなら、空間が広がって壮大な鳴り方をする(当然音数も多い)チューニング後の音が正解だ。このあたりは好みの違いが反映されるかも知れない。
今回、試聴機の貸し出し中に客様からの依頼があり、PMC BB5と組み合わせてP30 H30を聞くことになった。 床にカーペットが敷き詰められている影響を低減するため、まず人造大理石ボードを敷いてその上にP30はAIRBOW WFB-0125-2、H30は熱研ダイハード(生産完了品)を使って設置した。 電源ケーブルはP30:AIRBOW CPSC-LV1、H30:AET SCR-EVOの組み合わせ。プリアンプとパワーアンプの接続ケーブルには相性の良かったAIRBOW X Tensionを使って音を出したが音が硬く、また音の広がりにも欠けた。思ったよりもかなり音が悪かったので確認のためパワーアンプをB1aに変えてみると、全く勝負にならないくらいいい音が出た。B1aは200万円(BTLx2)、H30は160万円という価格の違いはあっても、これだけ音が違えば勝負にならない。 そこでプリアンプとパワーアンプの接続をX TensionからMightyに変えると、適度な広がりと色気が出て見違えるように音が良くなった。 RCAケーブルのグレードを落とすことを考えたのは、試聴テストでX TensionからSIN/EVOに変えたことで音が悪くなった教訓からヒントを得ている。試聴テストではSIN/EVOのウォーミングアップ不足を疑ったが、P30 H30のような高性能HiFiアンプが上手く鳴らないときは、どこかに「わずかな遊び」を作るとうまくいくことがある。今回はプリアンプとパワーアンプを繋ぐケーブルに「わずかに緩い=聴感上、音の伝達に時間的なずれが生じる」MSU-Mightyをチョイスすることで小さな空間にぎゅうぎゅう詰めになっていた音がほぐれ、ストレスを取り除くことに成功した。 オーディオはバランス。すべてを理論通りにセットアップしてもそれが最良とは限らない。ケーブルのグレードを落としたのに音が良くなる。こんなことがあるからオーディオは面白し、チャレンジしがいがある。また、今回のケースを「グレート信仰」の教訓とし、やたらとアクセサリーを使いすぎないように注意して頂ければ幸いだ。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
後書き |
||||||||||||||||||||||||||
|
P30 H30は、まごう事なき現代的な高性能アンプだ。特にスピーカードライブ能力(入力された信号をそのまま音に変換する能力)は非常に高く、現代的なHiFiスピーカーとの組合せると抜群の性能を発揮できるだろう。しかし、キャビネットを鳴かせ「歪み」を聞かせるタイプのスピーカーと組み合わせると音がまとまらない可能性が高い。 エネルギーバランスは、明らかな中低音重視。特に低音の力が強く、ユニットの口径あるいはスピーカーのサイズを一つ大きくしたようなスケール感のある低音が出る。駆動力に見合って制動力も高く、ユニットはぴたりと止まって余計な音が出ない。 駆動・制動力の高さは、中高域にも当てはまり、テキスタイル・ドーム型ツィーターからメタル・ドーム型ツィーターのような張りと芯のある高音出る。ユニットは無駄に動かないから、付帯音も出ない。しかし、時にその制動力の強さが災いし、間接音(エコー)成分が少なくなって音質がドライになりすぎることがある。 プリアンプとパワーアンプの接続は、アンバランスがよい。バランス接続では、音場が濁ってややくすんだ印象(濁りは少ないが鮮やかなイメージではない)に変化した。また中高域がマスキングされたように曇って、高音が足りないもこもこした音になった。パワー感もなくなって、今回の環境でのバランス接続は、アンバランスよりもハッキリ悪かった。 接続ケーブル、電源ケーブル、ボードなどの影響はストレートに音質に反映される。今回は「エコー成分」、「情緒」をポイントに「インターコネクト・ケーブルをやや緩めにする」としたチューニングが成功したが、それは私の好みや組み合わせた機器とのマッチングの結果であり、あらゆるケースや万人に通用するものではないことをお断りしておく。 P30 H30は癖がなく、突出した特徴がないことが最大の長所だが、同時にそれは弱点でもある。ミネラルウォーターよりも蒸留水に近いイメージのこのセットは、わずかな色づけに敏感に反応する。見かけの「ごつさ」によらずデリケートな使いこなしを要求するアンプ。それがこのアンプだ。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2011年 1月 清原 裕介 |
||||||||||||||||||||||||||



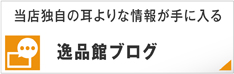
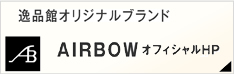

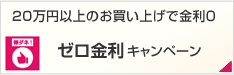
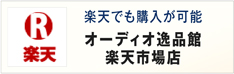
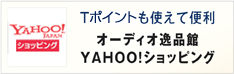
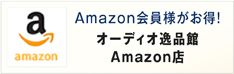
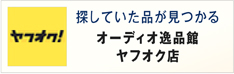
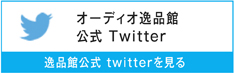

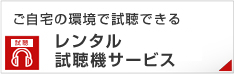

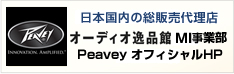












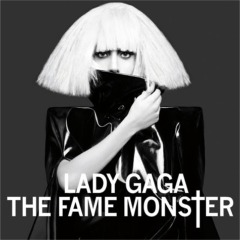
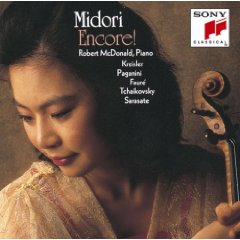
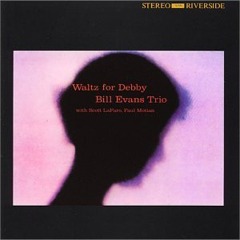








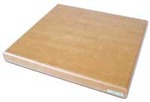 KRIPTON
AB2000(完了品) →
KRIPTON
AB2000(完了品) → 

