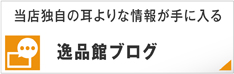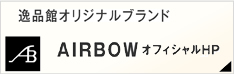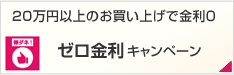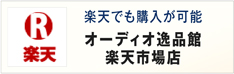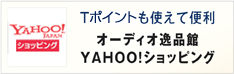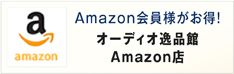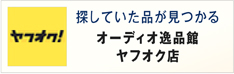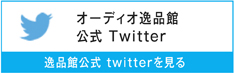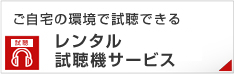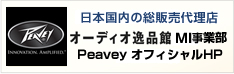■各種コンテンツ
■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部
オフィシャルサイト
HEGEL CDP2A CDP4A H2A H4A P2A P4A H1 H200 音質 比較 評価 テスト
HEGEL社のご紹介(輸入代理店 エレクトリのホームページより抜粋)
HEGEL社(Norway, Oslo)はミュージックラバーであり、ミュージッククリエーターであるベント・ホルター(Bent Holter)によって、音響機器の開発プロセスは弁証法的思考の上にあるべきと考え、正確な音再現のためにまったく新しい設計哲学を展開すべく設立されました。ヘーゲルにとってすべての開発プロセスを通じて、生の音楽の音響だけが唯一のリファレンスです。ヘーゲルの社名は、弁証法を提唱したドイツの革新的哲学者、G.W.F.Hegelに由来します。
開発スタッフはさまざまな分野の最新技術をマスターしたエキスパートたちで構成され、その成果はいくつかの特許を取得しています。最高水準の音響機器を作り出すには、前向きなアプローチ、最高の技術、熱心な研究者、十分な音楽的環境と音楽への理解を統合することによって可能であると考えます。
あのECMレーベルがプレイバックリファレンスとしてヘーゲルを選択したのもまたその開発姿勢に通じる「共感」によるものといえるでしょう。各製品ともノイズ成分に影響されないシグナルリファレンスシステムと高速広帯域なエラー補正システム(HEGEL SoundEngine テクノロジー)を採用しています。すべてのHEGEL製品は、HEGEL社(ノルウェー)で設計されています。本技術は、ミュージックシステムで通常見られるような技術をベースとしていません。デザインプラットフォームは、研究を重ねられ、ブロードキャストテクノロジー、通信技術、インテグレーテッド回路、高周波数テクノロジーの最新技術を活用しています。 HEGEL社は、その革新的なサウンドテクノロジー、受賞経験のあるスカンジナビア的なデザイン及び素晴らしいユーザーインターフェースに誇りを持っています。
|
|||||||||
| HEGEL CDP4A | HEGEL CDP2A | ||||||||
 |
|
||||||||
 |
|
||||||||
| メーカー標準価格 ¥500,000(税別) 生産完了 | メーカー標準価格 ¥300,000(税別) 生産完了 | ||||||||
|
主な特徴(エレクトリホームページより抜粋) |
|||||||||
|
CDP4A は、全く新しいデジタルフィルタを使用しています。これは非常に低いレベルにおいてもパルス波形を歪みから守ります。新デジタルフィルタにより、高解像度、細密なサウンドが得られます。これは以前と比べ極端に歪みが低くなっています。 CDP4A は、楽器の正確な位置、よりスムーズなミッドレンジ及び高音域をリスナーにお届けします。 たった2
つのコントロールボタンしか持たないCD
プレーヤを想像してみて下さい。 他のCD
プレーヤ同様、CDP4A は音楽を再生します。 し 真のバランス変換のためのマルチレベル24
ビット、352kHz DA
コンバータ(同期アップサンプリング付き)、HEGEL
社独自のアナログステー 左のコントロールボタン(加えて、オン/ オフボタン)は、プッシュ位置によってCD の様々なトラックをナビゲートすることができます。 右のボタン操作も同様に、再生を開始/ 停止し、さらにCD トレイをオープン/ クローズする機能を持っています。 これは非常に使いやすく、また他のHEGEL システムのコンポーネントと見事にマッチします。CD コントロールは、プリアンプコントロールを兼ね、17mm 厚のソリッドアルミニウムから切削加工されたHEGEL RC2 リモコンが付属しています。 CDP4A
は、デジタル/
アナログ出力を装備、トランスフォーマーバランスデジタル出力は、外部DA
コンバータ、MiniDisc
プレーヤに、またコンピュータもしくはCD
レコーダーへ音楽データを送信するのに最適です。
CDP4A
はどのようなタイプのミュージックシステムとも使用することができます。しかし、HEGEL
の画期的な音楽再生技術をトータルで最大限活用するため、弊社プリアンプ/
パワーアンプと組み合わせて 本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL 曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラストを施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つパールシルバー仕上げです。 このインダストリアルデザインは、Norwegian Design Councilにより優秀デザイン賞を受賞しました。 |
この素晴らしいハイエンドCD プレーヤは、HEGEL 社reference CDP4A プレーヤ同様、同じテクノロジープラットフォームをベースとしています。 これはCDP4A と同じパワーサプライ、プロセッサコントロールシステムを使用しています。また、完全なバランス マルチレベル24 ビット192kHz のDA コンバータ(同期アップサンプリング付き)を採用しています。 たった2 つのコントロールボタンしか持たないCD プレーヤーを想像してみて下さい。 他のCD プレーヤ同様、CDP2A は音楽を再生します、 しかし、より素晴らしく再生するのです! CDP2A は、この確約と気品をお届けします。 受賞経験のあるデザイン、シンプルなコントロール、際立ったサウンドを持つ優れた名品で、機能的な彫刻品ともいえます。 プレーヤにはRC2 リモートコントロールが付属しています。CD に録音されたアナログミュージックの体験を再現する、ということに関してこの価格帯でCDP2A 以上のCD プレーヤはありません。 真のバランス変換のためのマルチレベル24
ビット、192kHz コンバータ、HEGEL
社独自のアナログステージが高度なサーフェイスマウントオー CDP2A は、デジタル/ アナログ出力を装備、デジタル出力は外部DA コンバータ、MiniDisc プレーヤに使用する、またはコンピュータもしくはCD レコーダーへ音楽データを送信するのに最適です。 CDP2A は、どのようなタイプのミュージックシステムとも使用することができます。しかし、HEGEL の画期的な音楽再生技術をトータルで最大限活用するため、弊社インテグレーテッドアンプなどと組み合わせてご使用されることをお勧めします。 本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL
曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラスト |
||||||||
|
製品仕様 ■
DAC : 24 ビット352kHz マルチレベル DAC |
製品仕様 ■DAC
: 24 ビット192kHz マルチレベル DAC |
||||||||
| HEGEL H200 | HEGEL H100 |
 |
|
 |
|
| メーカー標準価格 ¥500,000(税別) 生産完了 | メーカー標準価格 ¥400,000(税別) 生産完了 |
|
主な特徴(エレクトリホームページより抜粋) |
|
|
H200
の企画は、P2A
プリアンプ技術の新しいデジタルコントロールデバイス
アクティブプリアンプステージ及びH2A / H4A
パワーアンプと H200 ハイエンドインテグレーテッドアンプは、パワフルな出力 2x200W(8 Ω )、2x350W(4 Ω ) を誇り、またデュアルモノパワーサプライを搭載、H1 以上にダイナミックなアンプとなりました。 可聴周波数レンジ全体にわたるダイナミックレンジの減少といういわゆる「トランジスタサウンド」を完全に排除、H200
サウンドは、細部まで H200
は、インテグレーテッドアンプH1
及びプリアンプP2A/ パワーアンプH2A
間のギャップを埋めます。 H200
の新機能は、外部サラウン 本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL 曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラストを施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つパールシルバー仕上げです。 |
H100 の企画は、Anniversary モデルP10 プリアンプ/H10 パワーアンプの新しいテクノロジーを取り入れ、SoundEngine のブラッシュアップ と特にFET トランジスターを導入することでした。 主なゴールは、1 つのシャーシにP10 / H10 のパワフルでダイナミックなプレゼンテーションを保ちつつ、非常に分かりやすいプリアンプステー ジをコンパクトに組み込む、ということでした。その結果、高調波歪みを極限まで減らし、よりスムースで繊細なサウンドとなり、特にスピーカーからのサウンドで作られる空間感の素晴らしさ は秀でるものとなりました。 H100 の機能的な最新フューチャーはUSB オーディオ入力です、Mac やPC からのUSB オーディオ出力をHegel サウンドでお楽しみいただけ ます。 H100 はパワフルな出力 2x120W(8 Ω ) を誇りH1 以上にダイナミックなアンプとなりました。可聴周波数レンジ全体にわたるダイナミックレ ンジの減少といういわゆる「トランジスタサウンド」を完全に排除、H100 サウンドは、細部までダイナミズムが損なわれることなく、高解像度 のサウンドステージを持ち、スムーズで温かく、また明解かつパワフルなサウンドを提供します。 H100 は、インテグレーテッドアンプH1 及びH200 間のギャップを埋めます。 H200 同様、外部サラウンドサウンドシステムとともに使用す るためのホームシアター用入力も装備しています。H100 はリレースイッチ入力ソースセレクタを採用しています。また、様々なタイプのミュージックソースからの接続が可能です。 ディスプレイ には、選択された入力ソースと、ボリュームセッティングが表示されます。 入力にはバランス、アンバランス双方を兼ね備えています。 H100 の入力ソース及びボリュームは、17mm 厚のソリッドアルミニウムから切削加工されたHEGEL RC2 リモコンでコントロール可能です。 本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL 曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラスト を施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つパールシルバー仕上げです。なお、オプションでBlack 仕上げ(下図)も選択できます。 |
|
製品仕様 ■周波数特性
: +/-0.2 dB 偏差以下 20Hz-20kHz |
製品仕様 ■周波数特性
: +/-0.2 dB 偏差以下 20Hz-20kHz ■質量:16 Kg |
| HEGEL H1 | |
|
|
| メーカー標準価格 ¥300,000(税別) 生産完了 | |
|
主な特徴(エレクトリホームページより抜粋) |
|
|
H1 は、H200 インテグレーテッドアンプの技術を基にしています。 H1は、H200 より新デジタルコントロール アクティブプリアンプステージ技術、並びに新しく改善されたSoundEngine アンプテクノロジーを取り入れています。 可聴周波数レンジ全体にわたるダイナミックレンジの減少といういわゆる「トランジスタサウンド」を完全に排除、H1 サウンドは、細部までダイナミズムが損なわれることなく、スムーズで温かく、また明解なサウンドを提供します。インテグレーテッドアンプH1 は、HEGEL 製品の中では価格的にエントリーレベルの製品ですが、 H200 アンプより新技術を取り入れ、アップグレードしています。 H1 のフロントパネルは、特徴的なHegel カーブとなっています。また、入力ソース及びボリュームは、17mm 厚のソリッドアルミニウムから切削加工されたHEGEL RC2 リモコンでコントロール可能です。 H1 は、リレースイッチ入力ソースセレクタを採用しています。また、様々なタイプのミュージックソースからの接続が可能です。パワーアンプ部は非常に高い出力 2x120W/8 Ω、2x200W/4 Ωを持ち、厳しいスピーカー負荷を適切に駆動します。 H1 は、70A を超える出力信号電流を伝えることができ、非常にダイナミック、パワフルなベース、高い解像度、精緻なサウンドステージ、スムーズなミッドレンジをスピーカーから提供します。 本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL
曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラスト H1入力には、バランス信号ケーブル用コネクタを装備しています。 スピーカーコネクタは、最高品質のバインディングポストとなっています。 |
製品仕様 ■周波数特性
: +/-0.02 dB 偏差以下 20Hz-20kHz ■質量:15 Kg
|
| HEGEL P4A | HEGEL P2A |
 |
|
 |
|
| メーカー標準価格 ¥500,000(税別) 生産完了 | メーカー標準価格 ¥300,000(税別) 生産完了 |
|
主な特徴(エレクトリホームページより抜粋) |
|
|
P4A (mk2) ハイエンド プリアンプ P4A はデジタルコントロールボリュームアッテネータを使用しています。 また、新ラインゲインステージ、出力ラインドライバステージも使用 しています。 これにより、楽器類の正確な定位、よりスムーズなミッドレンジ及び高音域をリスナーに届けます。 ラインナップの要である、P4A は、どのような入力ソースからでも信号に何も追加、削除することなくHEGEL 最高品質で増幅出力します。 P4A は非常にユーザーフレンドリーな製品です。そのため、高度なミュージックシステム、また同等製品に関するオペレーション知識は必要あ りません。 ボタンは3 つしかありません。 それは音楽ソースの選択ボタン、オン/ オフ ボタン、電動ボリュームコントロールの3 つです。 本機の入力ソース、ボリューム、ミュートは付属の17mm 厚のソリッドアルミニウムから切削加工されたRC2 リモコンで簡単に操作することが できます。この RC2 システムリモコンは、CD コントロールをはじめ全てのHEGEL 社製品のコントロールが可能です。 P4A は、CD プレーヤ、SACD プレーヤ、DVD オーディプレーヤ、MD プレーヤ、カセットレコーダ、チューナー、TV セットのようなミュージッ クソース入力からの接続が可能です。 P4A は入力から出力まで真のバランス内部シグナルプロセシングを採用しています。また、アンバランス、バランス入出力双方を有しています。 本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL 曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラスト を施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つパールシルバー仕上げです。 P4A は、ノルウェイの高級オーディオマガジン「Lyd & Bilde」により、2003 年度「High End Pre Amplifier of the Year」に選ばれました。 |
P2A (mk2) ハイエンド プリアンプ P2A ハイエンド プリアンプ は、デジタルコントロール ボリュームアッテネータ、また革新的なラインゲインステージ、出力ラインドライバステー ジを使用しています。 これにより、楽器類の正確な定位、よりスムーズなミッドレンジ及び高音域をリスナーに届けます。 プリアンプP2A は、HEGEL システムの要で、どのような入力ソースからでも信号に何も追加、削除することなく最新のアンプモジュールで増幅出力します。上級機のP4A と同じテクノロジープラットフォームをベースとし、P2A は、ハイパフォーマンス プリアンプラインステージと同じ機能、真の バランスシグナルプロセシングを提供します。 P2A は非常にユーザーフレンドリーな製品です。そのため、高度なミュージックシステム、また同等製品に関するオペレーション知識は必要あ りません。 ボタンは3 つしかありません。 それは音楽ソースの選択ボタン、オン/ オフ ボタン、電動ボリュームコントロールの3 つです。 ノブは3 つしかありません。 本機の入力ソース、ボリューム、ミュートは付属の17mm 厚のソリッドアルミニウムから切削加工されたRC2 リモコンで簡単に操作することが できます。この RC2 システムリモコンは、CD コントロールをはじめ全てのHEGEL 社製品のコントロールが可能です。 P2A は、CD プレーヤ、SACD プレーヤ、DVD オーディプレーヤ、MD プレーヤ、カセットレコーダ、チューナー、TV セットのようなミュージッ クソース入力からの接続が可能です。 本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL 曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラスト を施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つパールシルバー仕上げです。 P2A は、Audiophile.no により「Reference プリアンプ」賞を受賞しています。 |
|
製品仕様 ■周波数特性
: +/-0.05 dB 偏差以下 20Hz-20kHz |
製品仕様 ■周波数特性
: +/-0.05 dB 偏差以下 20Hz-20kHz |
| HEGEL H4A | HEGEL H20 |
 |
|
 |
|
| メーカー標準価格 ¥900,000 生産完了 | メーカー標準価格 ¥700,000(税別) 生産完了 |
|
主な特徴(エレクトリホームページより抜粋) |
|
|
H4A
の各チャンネルは、電圧ゲインと電流ゲインステージが完全に分けられています。
リスナーは、より高いダイナミックレンジ、よりよい楽 H4A
は、増幅ステージに独自の新しく改善されたSoundEngine
テクノロジー回路を使用しています。 |
HEGELが取り組んだ、高調波歪みを取り除くための5年間にわたる研究プロジェクトは2008年に終了しました。しかし、その技術を駆使して生み出されたパワーアンプH10は、生産に大きな労力を必要としたため30台しか作ることができませんでした。最終的に2009年に我々は通常の生産に高調波歪みをキャンセルする技術を取り入れる方法を開発することに成功しましました。 これらのノウハウを惜しみなく投入して生まれたH20は、ヘーゲルアンプ最先端技術の象徴です。 ■H20に投入されたFET技術はリズミカルな音を実現しますが、それはベースラインを作り直すよりも簡単で効果的です。もう1つの重要な要素は、高調波歪みをなくしたことです。高調波歪みが消えたことで、より滑らかで自然な音がもたらされます。 H20の基本回路はH10に基づいています。それは、特許取得済みの技術とレーザートリミングによって作られるSound Engine モジュールで構成されます。 時代を超えたヘーゲルのデザインは、近代的なあるいはクラシックなインテリアにもマッチします。ブラスト処理されたフロントパネルには、スイッチが一つあるだけです。このフロントパネルは、1.5Kgの肉厚のアルミが使われています。上部パネル、サイドパネルにもブラスト処理されたアルミパネルが使われ、H20の統一感のあるデザインが実現しています。 ヘーゲルH20は130アンペア以上瞬時供給電力を持つ、歪み率の非常に低いパワーアンプです。高いダンピングファクターを持ち、スピーカーを正確に駆動します。H20は、今日の市場における最も自然、リズミカルでダイナミックな音質を持つパワーアンプです。
本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL
曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラスト |
|
製品仕様 ■出力
: 300W+300W (8 Ω ) デュアルモノラル構成 ■質量:45 Kg |
製品仕様 ■出力
:200W+200W (8 Ω ) デュアルモノラル構成 ■質量:25 Kg |
音質比較
HEGELのフルラインナップは、2007年8月に一度試聴を行っていますが、H100、H20という新製品が発売されたのを機にもう一度全ラインナップのより細かな試聴を行いました。テストの完了後に前回の試聴リポートを読んでみましたが、今回と若干印象が異なっている部分が見受けられました。若干矛盾が感じられる所もありますが、双方のリポートを読み比べていただければ、HEGELの長所・短所がより明確になると考え、あえてどちらのリポートにも修正は加えず掲載しています。
スピーカーは前回のテストと同じ ウィーンアコースティック T3Gを使っています。
 Vienna
Acoustics T3G \580,000(ペア)
Vienna
Acoustics T3G \580,000(ペア)
スピーカーケーブルには、20年近く前から使っているACROTECのS1010(ACROTECのデビュー作)を使いましたが、このケーブルの音は癖が少なくオーディオ用スピーカーケーブルの標準的なサウンドだと思います。RCAケーブルにはAETのHCR/EVO 1.2m、XLRケーブルにはS/A LAB HSB-MK3/1.5mを使っています。
メーカーから送られてきた試聴機に付属する電源ケーブルの銘柄がバラバラだったため、電源ケーブルはAIRBOWのKDK-OFCに統一しました。念のため付属していた数種類の電源ケーブルと比較すると、付属品で音の広がりや色彩感で勝る事がありましたが、前述した理由で「どれがどの製品に付属していたのか?」分からないため、KDK-OFCで各製品の比較を行いました。電源ケーブルの選択でシンプルな回路構成をHEGELは、電源ケーブルの音質に非常に敏感だという結果が得られましたから、HEGELの使いこなしで「電源ケーブル」は一つのキーポイントとなるはずです。
![]()
HEGEL プリメインアンプとCDプレーヤーの音質を比較する
全機種を一度に!と行ってもさすがにこれだけ多くのモデルを相互に組み合わせてテストするのは非効率的なので、まず3機種のプリメインアンプと2機種のCDプレーヤーを組み合わせて音質をテストすることにした。まず最初に選んだのが新製品のH100である。
 HEGEL H100 + CDP2A-MK2
HEGEL H100 + CDP2A-MK2
HEGEL製品にはすべてバランス入出力が装備されているので、テストに際しバランスとアンバランスの音質比較を行った。H100とCDP2A-MK2の組合せでは、透明感・繊細さなどあらゆる部分でアンバランスがバランスを明確に凌駕したため、CDP2AとH100の試聴はアンバランスで行った。
カサンドラ・ウイルソン Belly
of the son TOCJ-66137
一枚目には、録音が優秀なカサンドラ・ウイルソンのJAZZを選んだ。カサンドラ・ウイルソンのソフトの多くは「空間表現」が非常に巧みで、楽器やボーカルの定位がコンパクトにまとまり、おるべき音があるべき場所から出てくる。音楽的には、やや前衛的で好き嫌いは分かれると思うが、少なくとも「音源」としては非常に優れていると思う。
このディスクに使われているパーカッション(多分コンガだと思われる)の皮がたわむ様子〜音が安定するまでの一連の物理的な流れが正確に音に反映され、まったく無理のない自然な音で鳴る。
パワフルだとか、細かいとか、低音がとか、高音がとか、そういう誇張感は、すべての音に一切感じられない。本当に無理のない自然な音だ。もちろん、ボーカルもとても自然に聞こえてくる。ずば抜けた自然さだ。輪郭の誇張感がないから、このソフトの持ち味である「立体感(定位)」も自然に出る。
この価格帯の他メーカーのプリメインと比べるならH100よりも音が細かい製品や、中高域に魅力的な艶を持つ製品もある。例えばLuxmanなどとの比較は面白いと思う。しかし、H100はそういう製品と対照的に「個性を持たない」ことが最大の「個性」だと思う。
その音は、撮像管時代のIKEGAMI通信の放送局用ビデオカメラの絵作りに通じるような、HR-10000を作っていたときのVicotrの放送局用ビデオデッキの絵作りにも通じるような、派手さのないいぶし銀のような"渋さ"と"深さ"が感じられる。車の乗り味に例えるなら、同じ北欧生まれの"VOLVO"に当てはまるだろうか。北欧家具のような質実剛健な落ち着いた雰囲気を持っているアンプだ。
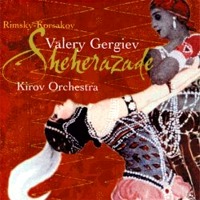 交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
弦の音はすこしくすんで湿り気が感じられ、ややウェットな傾向。ファゴットやクラリネットの音には、木管楽器らしい温かみと柔らかさが感じられる。ピッチカート?で奏でられる弦も耳あたりは柔らかいが、アタックの部分はきちんと再現される。コンサートマスターの音もオイストラフのように柔らかい。
演奏はとても静かで深みがあり、優しく聞こえるが、ほのかな色気も感じられる。カサンドラと同じように絶対的な性能は高いと感じられないが、それぞれをきちんと再現する能力、色づけなく音楽を隅々まで再現する能力は驚くほど高い。
この価格でシビアな音楽ファンや耳の良い演奏家のリクエストに答えられる性能を持つアンプは、ほとんど無いがH100は数少ないそういったアンプの一つだ。必要にして十分。必要にして十分以上。音楽の表現能力は抜群だ。
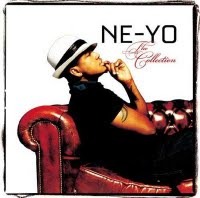 ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
H100の音を質実剛健と表現したが、ニーヨをかけるとどうしてどうして、なかなか色っぽいことがよくわかる。北欧美女の白く透き通る肌のような、何とも言えない色気が感じられる。優しさの中に秘められた、静かな色香。上手く表現できないが、これは間違いなく大人の色気だ。女優に例えるなら吉永小百合?そういうイメージになるのかも知れない。清楚で上品。控えめだけれど、時にはキュート。
ベースもぐんぐん前に出てくるのではないのだけれど、リズム感はきちんとある。音色は鮮やかなわけではないのだが、色彩の表現は素晴らしく細やかだ。音色表現のコントラストが高くないのでハーモニーの分離はクッキリしていないが、色彩が細やかなのでユニゾンの各パートの音色の違いは明確に再現される。
今までに知っている「デジタル」の音とは明らかに違って、刺々しさが微塵も感じられない。レコードのように鮮やかではないが、色彩の微妙な違い、陰影の微妙なグラデーションは驚くほど細やかに描写する。
オーディや音楽を知り尽くした玄人を唸らせる絶妙なバランスがH100の最大の魅力だが、色づけの少ないデリケートな音を持つこのアンプを使う時には細心の注意が求められる。そのデリケートな音色の表現を引き出せなければ、ただの性能の悪いアンプと誤解されかねないからだ。
HEGEL H100 + CDP4A-MK2
アンプをそのままにして、CDプレーヤをCDP4A-MK2に変える。
カサンドラ・ウイルソン Belly
of the son TOCJ-66137
まずはアンバランスで聞いた。音が出た瞬間からCDP2A-MK2よりもベールが剥がれて、クリアで細やかなサウンドが聞こえてきた。しかし、念のためアンバランスの音質もチェックする。結果は、CDP2A-MK2と全く同じ傾向でアンバランスの方が鮮明でレンジも広く、音場もクリアに広がった。特にパーカッションのアタックの切れ味は、アンバランスがバランスを大きく凌駕した。
結論を先に言うと、CDP2A-MK2とCDP4A-MK2の違いは「デジカメの画素数」に例えられる。ノーマル放送とハイビジョンほどの差はないが、すべての部分が着実にグレードアップしている。同じCDプレーヤーの電源ケーブルをグレードアップした感じにも似ているだろうか?音調は全く変わらないが、音の木目が約2倍くらい?細やかになった感じだ。音の広がりも大きくなり、それぞれの音もよりハッキリ聞き分けられるようになる。CD2A/MK2に比べ、ステージに一歩近づいてライブを聴いているようなイメージに音質が変化した。
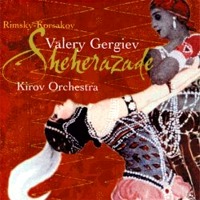 交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
低音の響きが数段大きくなり、中高音の分離感が一気に向上する。それぞれの楽器の音の特徴が明確になり、すべての音が美しくなる。音色のコントラストが一気に上昇し、鮮やかさを感じる音になる。
静けさは相変わらず素晴らしいが、CDP2A-MK2では感じとれなかった空気の動きのような部分が出てくる。楽器の数も数割以上増えたように感じられる。
音調は全く変わらず、情報量だけが増える。この音色の完全なコントロールはオーディオ的面白みは薄くても、音楽的にはとても素晴らしい。上級機を購入するだけで、後は何の苦労もなく音楽が良くなるからだ。
すこし高いチケットを買って、ホールの良い座席へ移動したようなイメージに音質が変化した。
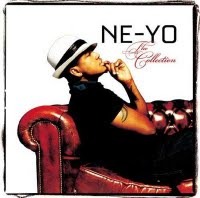 ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
低音のパンチ力、音のしっかりした感じが大きく向上する。しかし、この程度の音質ならばAIRBOW PM15S2/Masterで充分に超えることができる。CDプレーヤーのグレードアップで音が良くなった結果、ニーヨではH100の絶妙なバランス感覚の魅力が消えてしまった。今聞いている音は、価格をやや疑問に感じる「くぐもった緩い音」でしかない。
CDプレーヤーをグレードアップしたにもかかわらず、POPSが逆につまらなくなった原因はアコースティックサウンドとエレクトリックサウンドの「音の性質の違い」だ。同じ楽音でもアコースティックサウンドとエレクトリックサウンドは、水と油ほど性質が異なっている。一言で言えば「自然な音」と「人工的な音」の違いだ。アコスティックサウンドに必要なのは「質」で、エレクトリックサウンドに必要なのが「量」だ。「質」を高めても「量」が伴わなければエレクトリックサウンドは良くならない。HEGELの上級機では「質」が高められたが、低音の量感や高音の切れ味が質ほど向上しなかった結果、アコースティックサウンド(シェーラザード)に比べ、エレクトリックサウンド(ニーヨ)がよくならなったのだ。「質」と「量」のバランスが崩れると音が良くなっても、音楽が悪くなる。あるいはその逆も度々経験するが、これがオーディオの難しく面白いところではないだろうか?
最後にパソコンに取り込んだ「ニーヨ」のアルバムをH100に新設された「USB接続」で聞こうとしたが音が出ない。何度かやり直してもやはり音が出ないのも、もしやと思い「仕様」を調べるとやっぱり!対応しているPCは"MAC"だけ!私は"MAC"を持っていない。う〜ん、折角のUSB入力なのにWindowsに対応していないとは・・・。
![]()
 HEGEL H1-MK4 + CDP2A-MK2
HEGEL H1-MK4 + CDP2A-MK2
まず、ディスクをそのままにしてH100とH1-MK4を入れ替えて、CDP4A-MK2とH1-MK4をアンバランスで聞いた後に、接続をバランスに変えてそれぞれの音質をチェックしたが印象はH100と全く同じだった。H100でニーヨは、CDP2A-MK2との相性が良かったので、H100と似た傾向を感じたH1-MK4でもCDプレーヤーをCDP2A-MK2に変えて見るとどうだろう?ニーヨに色気が戻ったではないか。H1-MK4との相性はCDP2A-MK2が良しと判断し、H1-MK4の試聴はCDP2A-MK2との組合せで行う事にした。
カサンドラ・ウイルソン Belly
of the son TOCJ-66137
CDP2A-MK2とCDP4A-MK2の比較で感じた音調は全く変わらない傾向は、H100とH1-MK4との比較でもまったく同じだ。僅かに音の輪郭の鋭さや解像度感でH1-MK4がH100を上回る様に感じるが、それはウォーミングアップの差かも知れない。
ほんの少し厚みが後退し、リズムが軽快になった感じを受けるが、それもアンプを切り替えたと知らされなければ、気付かない程度の僅かな違いでしかない。カサンドラ・ウイルソンでは、H100と比較できる部分がほとんど感じられないので早々にソフトを変えた。
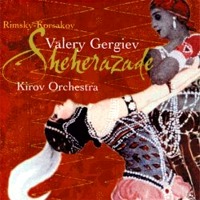 交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
H100よりも弦がやや軽やかで、曲調の雰囲気が明るくなった。シェーラザード姫が5才くらい?若返った感じを受ける。
各楽器の分離感はH1-MK4がH100よりも良好だが、厚みや味わいの部分はやや後退したようにも感じられる。
何れにしてもH100とH1-MK4の差は非常に僅かで、電源ケーブルなどのアクセサリーによって完全に微調整が可能な差でもあると感じられる。結論としてUSBが要らないのなら、アンプはH1-MK4で十分ではないかと思う。
H1-MK4ですでにHEGELの魅力は十分に極められている。
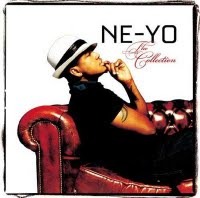 ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
H100よりも高域の鮮度感が僅かに高いので、英語の子音がより明瞭に聞き取れる。明瞭度が高いH1-MK4は、音量を下げたときH100よりも音がボケにくいはずだ。小音量で音楽を聞く機会が多いなら、H100よりもH1-MK4の満足度が高いのではないだろうか?しかし、明瞭度が上がったことでH100の独特なアンニュイな魅力がすこし薄れたかも知れない。
H100、H1-MK4と試聴したがHEGELのアンプは薄味を身上とするだけに、接続方法や組み合わせるCDプレーヤーを変えるほんのちょっとのスパイスが、大きく利きすぎ調理が難しい。こんなに少しの環境変化に敏感に反応するなら、他店の店頭や自宅でHEGELを聞いた場合、今回の試聴結果が容易に覆ることが予想される。とにかくH100とH1-MK4の本質は、癖のない自然な音とだけ覚えて頂ければ間違いないはずだ。
![]()
 HEGEL H200 + CDP4A-MK2
HEGEL H200 + CDP4A-MK2
H100/H1-MK4同様にまず、2台のCDプレーヤーとアンバランス、バランスの2つの接続の合計4通りの音質を比べてみる。CDP2A-MK2とCDP4A-MK2の2機種の比較では、音の細やかさ、品位、音楽的な表現力で明らかにCDP4A-MK4が勝っていた。アンバランスとバランスもH100/H1-MK4と同じケーブルを使って比較したにもかかわらず、バランスの方が透明度が高く音楽の表現能力や情緒でも勝っていると言う、全く逆の結果となった。そこで、H200はCDP4A-MK4をバランス接続で組み合わせて(以下H200と記述)試聴を行った。
カサンドラ・ウイルソン Belly
of the son TOCJ-66137
H100/H1-MK4と比べて音の数が圧倒的に違う。パーカッション、特にシンバル系の繊細さや切れ味が大きく向上する。ボーカルも芯がしっかりとし、楽器との分離が明確になる。一般的な「高音質」のイメージと一致する鳴り方になるが、癖のなさ自然さは、そのまま引き継がれている。
H100/H1-MK4では音の輪郭が僅かに不明瞭になることで「生演奏を聴いているような自然さ」が演出されていたが、H200では「生演奏以上に音が細かく聞こえる」というオーディオ的な醍醐味が感じられるようになる。パーカッションはより力強く、ピアノの音色はより鮮やかに、ボーカルの口元はより引き締まり、H200では演奏だけでなく、音も鮮やかで心地よい。とてもリアルなサウンドだ。
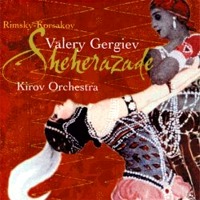 交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
ホールのサイズが大きくなり、空気も澄み切る。H100/H1-MK4では「綺麗にデフォルメされた演奏」を聴いているような感じがあって、それはそれで音楽再生の一つの完成形として魅力的だったが、H200では生演奏を聴いているようなリアルなサウンドが実現する。
雄大な海に向かってシンドバッドを乗せた船が出帆する第一楽章のイメージ、シェーラザード姫の悲哀をコンサートマスターのバイオリンの音色にのせて表現する、第2楽章の美しく儚い音、動と静のイメージが見事に描き分けられる。このダイナミズムはH200でしか味わえないものだ。
H100/H1-MK4で聞いたのがCDなら、H200で聞いたのはSACD。それくらいの違いを感じさせる、クラスが違う素晴らしいサウンドが出現した。
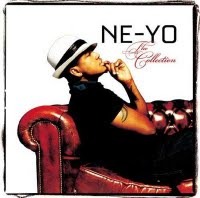 ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
すでに聞いた2枚のソフトで感じた印象と全く同じで、H100/H1-MK4で聞いたのがCDなら、H200で聞くそれはSACDやDVDオーディオの様に感じられるくらい音が良い。ハーモニーの分離、低音楽器の力感と引き締まり方。ボーカルの細やかさ、あらゆる部分が大きく向上し、この差であれば音が出た瞬間にその違いが分かるだろう。
しかし、それでもHEGELが基調とする癖のなさ自然さがH200にも完全に当てはまるから、H100/H1-MK4に桁外れに高いケーブルを電源に使ったら、同じくらいの音になる可能性はある。逆に言えば、それほど高いレベルで全モデルの音が統一されていると言えるだろう。
そしてHEGELの本当の良さは、その「統一性」にある。音色が統一されているからこそ「ラインナップされる高価な機器」に買い換えるだけで、何の苦もなく装置のグレードアップが実現する。簡単なようでいて、これがじつはなかなか難しい。HEGEL以外でそれを実現しているのは、スピーカーメーカーになるがPMCやウィーンアコースティックが思いつく。意外にCDやアンプなどのメーカーの名前は浮かばない。モデルを変えても音のイメージが変わらないというのは本当にすごいし、HEGELの技術力が高い証拠でもある。
HEGEL プリメインアンプとCDプレーヤーの音質比較 ・ 総合結果
セパレートアンプの比較を行う前に、まずプリメインアンプの試聴結果をまとめることにする。
H100とH1-MK4に組み合わせるCDプレーヤーはCDP2A-MK2をお薦めする。接続はアンバランスが良い。USB(MACにしか対応しない)を使わないのであれば、迷わずH1-MK4を選べば良いだろう。H100との音の差はほんの僅かでしかないからだ。両機とも音楽的には抜群の表現力を持っているが、あまり高価な(性能の高い)スピーカーを組み合わせた場合「音質」に不満を感じる(スピーカーが鳴りきっていないように感じる)ことがあるかも知れないから、組み合わせるスピーカーは50万円(ペア)程度までの製品がお薦めだ。
H200は、H100/H1-MK4とは音の品位が違う。組み合わせるCDプレーヤーにはCDP4A-MK2を選ぶべきで、接続はバランスがよい。このセットなら、組み合わせるスピーカーが100万円(ペア)を超える製品でも、その能力を余すことなく引き出してくれる。
HEGEL セパレートアンプの音質比較
セパレートアンプの試聴を行う前に、各機器の相性と接続による音の違いを確認した。
各2機種のプリアンプ、パワーアンプを交互に繋ぎ、アンバランスとバランスの音質を比較したが、すべての組合せで中域の厚みや透明感がアンバランスよりも勝り、バランスの音が良かった。特に決め手となったのが前後方向への立体感だ。CDプレーヤー〜プリアンプ〜パワーアンプのすべてをバランスで接続した時にボーカルと伴奏の前後方向への位置関係が最も深くなった。音質には好き嫌いが生じる場合があるが、立体感(位相の整合性)にこれだけの違いがあれば、明らかにバランスの音が良いと判断してよいだろう。
セパレートアンプの試聴を行う前に、H20との組合せでプリアンプP2A-MK2とP4A-MK2の比較を行った。その結果、本体価格20万円の差以上にP4A-MK2の音質が魅力的に感じられた。具体的には、楽器の運動(音の変化の様子)が2倍くらい大きく、またきめ細やかに感じられた。P2A-MK2とP4A-MK4の情報量の差はかなり大きく、P2A-MK2ではパワーアンプの能力を十分に発揮できないと判断し、比較試聴でプリアンプはP4A-MK4のみ使うことにした。CDプレーヤーも試聴の結果から、同様の理由でCDP4-MK2のみを使うことにした。
![]()
 CDP4-MK2+P4A-MK2+H20 (以下H20と記述)
CDP4-MK2+P4A-MK2+H20 (以下H20と記述)
カサンドラ・ウイルソン Belly
of the son TOCJ-66137
H200とH20で感じる音の違いは、H100/H1-MK4とH200で感じた変化と全く同じ変化だ。各々の楽音がより細やかになり、音場が一層澄みきって見通しが良くなる。もちろん音楽の表現も細やかになる。
ピアノの音は厚みを増し、ボーカルはより近くで聞いている細やかな雰囲気が出る。確かにH20以上に音が細かく聞こえる高級コンポは存在する。しかし、それらの多くが「何となく強調されたような(行き過ぎたような)音」に聞こえるのに対し、H20は目の前でライブが行われているのではないだろうか?と錯覚するほどの「自然なリアルさ」を持っている。この「自然なリアルさ」は、ある意味で比類がない断言できる高いレベルにある。本当に心地よく自然なリアルさで音楽を堪能できる。
プリメインアンプで感じた「音色の統一性」はセパレートアンプにも完全に共通する。繊細で透明感が高く、癖のない自然な音で突出した部分を持たない。物足りないと言う表現もできるが、こういう高い見識でまとめられた音ならどんなスピーカーを組み合わせても、どんな音楽を聞いても、どんな録音のディスクでも、安心して音楽に身を委ねることができるはずだ。プリメインアンプからセパレートアンプに変えても、HEGELはモデルを価格に応じてハッキリと音が良くなる。
超々高級な大人のコンポーネントという意味では、同じヨーロッパのBurmesterと共通するが、HEGELは価格も音質もより現実的だ。そういう意味で、やはり北欧で作られる車"VOLVO"や"SABB"との共通性を強く感じる。必要な部分だけを練り上げて行くその物作りの手法は、北欧独自の文化なのかも知れない。
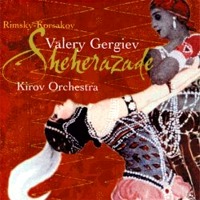 交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
H200と比較して情報量は増えるが、フォルテの部分ではディスクの限界(マイクの限界)のような?音の広がりの壁のような物が感じられるようになった。増えすぎた情報量にスピーカーが対応し切れていないのかも知れないが、フォルテの部分では音が完全に広がり切らず、楽音の密度が高くなりすぎて音場に僅かな濁りを感じることがある。その一点を除けば、音の細やかさ、表現力、楽音の美しさのレベルはかなり高く、こんな小さなCDプレーヤーから出てくる音だとは俄には、信じられないほど素晴らしい音が聞ける。
試聴したHEGEL全体に言えることだが、聞こえる音よりも「聞こえない音」の処理が上手いように感じられる。文章を書くときに、細やかにくどくど説明するのではなく、行間を読ませるやり方と同じで「音と音の間」を巧みに聞かせるような「鳴らし方」だ。ディスクに収録された音を真っ正直に出すこの方法なら、録音が多少悪くてもそれを気にせず音楽を聞くことができる。「音楽を楽しむオーディオ製品の音作り」は、そうでなければならないと思う。あとは、「どれくらいの部分まで聞かせるか?、聞かせないか?」のバランスが重要だが、HEGELはそのバランスも素晴らしい。
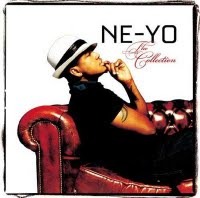 ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
スタジオのプレイバックモニターで録音をモニターしているような、しっかりとした音が出る。音の端っこ、隅っこまでがきちんと再現され、とても心地よく安心できる音だ。
ハーモニーの分離、音色の描き分けの能力も高く、細やかな音まで聞き分けることができる。高品位で心地よい音だが、同時に音楽的な表現力も高い。信号に対する忠実度は大幅に高まっているが、HI−FI基調になりすぎずその音調には、H100/H1-MK4で感じた「優しさ」や「柔らかさ」がしっかりと受け継がれている。
H20は支払う金額を超える極上の「癒し」をもたらしてくれるサウンドに仕上がっている。オーディオとの格闘をまだ続けたい方は、その低刺激にきっと満足できないと思うからお薦めしないが、これはこれでオーディオの「一つの上がりの音(一つの頂点に立つバランスを持つ音)」のように思える。
![]()

CDP4-MK2+P4A-MK2+H4A-MK2 (以下H4Aと記述)
パワーアンプをH20からH4A-MK2に変更して最後の試聴を行う。
カサンドラ・ウイルソン Belly
of the son TOCJ-66137
H20と比較すると中低音の厚みや空気の揺らぎ感がでてきたように思えるが、その差はさほど大きいとは感じられない。少なくとも、一気にこれだけの機器を試聴してきた「疲れ」を吹き飛ばすほどの変化ではない。じっくりと聞けば確かな差が感じられるが、同時にH20でも十分ではないか?という感覚を持つ。
低音の響きはH20よりも明らかに増大しているが誇張感はなく、あくまでもHEGEL全体に通じる「楽器の動きが見える」ような自然な音。ボーカルは、H20よりもやや湿り気が多くなっただろうか?ピアノの重量感はH20と大きく変わらないように感じる。高域は伸びたが、やや細く金属的になったようにも感じられる。ボーカルの子音も心なしか、ざらついて聞こえる。
結局、H4A-MK2とH20には大きな差が感じられなかった。20万円の価格差とボディーのサイズの違い(H4A-MK2はあまりにも巨大でラックには入りにくい)を考えれば、パワーアンプはH20で十分なのではないか?というのが、カサンドラを聞き比べた感想である。
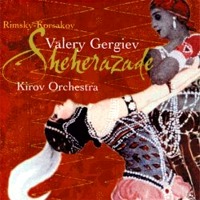 交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
交響曲“シェーラザード” PHILIPS 470 618-2 CD/SACDハイブリッド盤
H20では感じられなかった「サラウンド的」な音の広がりが感じられる。スピーカーが前にあるのにも関わらず、背後からも音が回り込んでくるようだ。
スピーカーのユニットが余計に動かずしっかりと「止まる」ので、静けさも抜群だ。プリメインアンプでの音楽を「聞きに行く感覚」がH20では、「音楽からやってくる感覚」に変化し、H4A-MK2では「音楽に引き込まれる感覚」になる。シンフォニーのような音数が多く、周波数レンジもダイナミックレンジの広い音楽でアンプを聞き比べると、H20とH4A-MK2の違いはやはり出る。シンフォニーを堪能したいとお考えなら、パワーアンプにはH4A-MK2を選ぶべきだ。
P4A/H4Aの組合せは2年ほど前に聞いて詳しい試聴記事も書いた。今回の試聴ではその時に感じられなかった「色気」が出て来て、前回よりも音楽をより情緒的に聴かせてくれた気がする。バイオリンの繊細さ、張りのある感じも良く出たし、フォルテも厚みも素晴らしい。わき出すようなエネルギー感も十分だ。この印象の違いは、前回アンバランスで今回はバランス接続で試聴を行ったことによるものだろう。
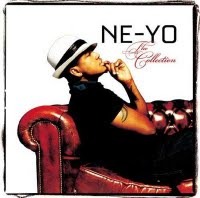 ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
ニーヨ THE
Collection UICD-9062 HM-CD盤
ベースの音が数段力強いが引き締まった感じではH20が勝っていたように思う。H4A-MK2の低音はH20よりも止まるのが遅い感じがする。交響曲で感じた「ブレーキの強さ」とは正反対の感覚だ。
しかし、その低音の「サービス」がすこしプラスに働いて、リズムセクションがより弾んで感じられる。ハーモニーも太くなり、音場が文字通り「濃く」なるのがわかる。超弩級!パワーアンプ、例えばつい最近テストしたTAD M600のように力ずくでスピーカーを抑え込むような鳴り方はせず、適度にルーズにウーファーを動かしているが、それが音楽を開放的に演出してくれる。
HEGEL 音質比較 ・ 総合結果
HEGELのすべてのモデルを聞き終えた。全体的に「高域が控えめな印象」を持つHEGELを“ハイエンドショウトウキョウのような試聴会”で使いたいか?と問われるなら"NO"と答える。その理由を説明しよう。
試聴会では、ほとんどの場合中高音が吸収されすぎるから、かなり高音がうるさいアンプでないと音楽が上手く鳴らない。逸品館が行うイベントで「サーロジックのパネル」を沢山使うのは、足りない響きを補うためだが、あれくらい多くのパネルを使わないと中高域が明るく響かない。

それでも会場が満員になると十分なプレゼンスが得られない事がある。それを一番強く感じたのは、2009年春のハイエンドショウトウキョウのデモンストレーションだった。
しかし、最大でも20畳程度しかない一般家庭で音楽を聞くなら、HEGELのやや控えめくらいの高音がちょうど良い。その方がソフトの嫌な部分も出ないし、デジタルの刺々しさも緩和される。トレードに「瞬間芸のような音の良さ」は、失われてしまうがそんなものはどうせすぐに飽きてしまうから、長く付き合うにはどうでも良い。「美人は飽きる」というやつだ。HEGELの持つ「性格の良さ」は、長く付き合っも飽きが来ないし、長く付き合えば付き合うほど味が出る種類のものだ。HEGELはそう言う「良い音」に仕上がっている。
南国に住む人間は「いい加減で自己中心的」な傾向が強く、逆に北国に住む人間は「親切な人」が多いように感じるが、この差は気候(環境)と密接な関係がある。南国は暖かく暮らしやすいから、誰の助けもなしに一人で生きて行ける。家がなくても凍えないし、食べ物はそこら中に生えている。それに対し、北国の厳しい自然環境の中で人は「助け合わなければ」生きて行けない。「助け合い=親切」は、北国の気候から生まれた「土着の文化」なのだ。
北欧の厳しい自然が育んだHEGELは、誰が聞いても心地よい、適度な距離感を持つ「聴き疲れ」しない音に仕上げられている。一定の距離を感じるけれど「優しく心が癒されるサウンド。オーディオ的な魅力は控えめだけれど、ずば抜けた音楽表現能が、それを補って余りある魅力に感じられた。
2009年11月 逸品館代表 清原 裕介