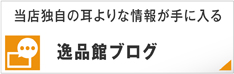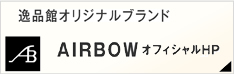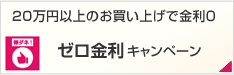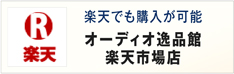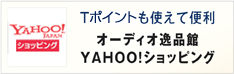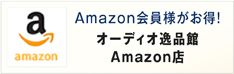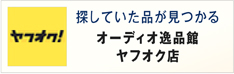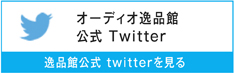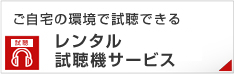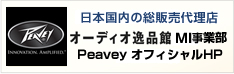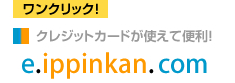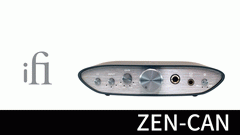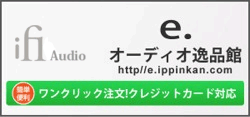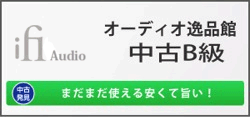■各種コンテンツ
■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部
オフィシャルサイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifi ZEN ゼン DAC BLUE CAN PHONO 比較 試聴 評判 レビュー 音質 評価 販売 価格 展示
ifi Audio ZENシリーズ(ZEN-DAC/Blue/CAN/PHONO)音質チェック
超高級カートリッジ「朱雀/青龍」の製造発売元「TOP WING」が取り扱う、中国生産のハイ・コストパフォーマンス・オーディオ製品メーカー「ifi audio」から発売されている低価格・小型オーディオ・コンポーネント「ZEN シリーズ」の4モデル、D/Aコンバーター「ZEN-DAC」、ブルートゥース・レシーバー「ZEN-Blue」、ヘッドホンアンプ「ZEN-CAN」、フォノイコライザーアンプ「ZEN-PHONO」をテストしました。
![]()
製品の概要
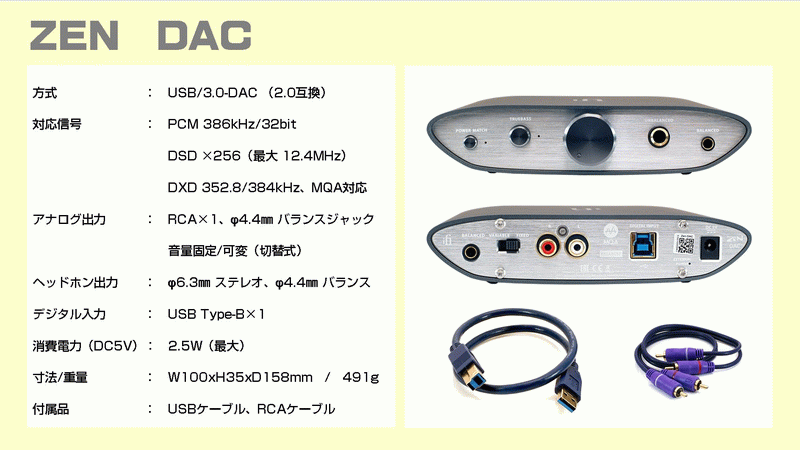
ZEN DAC メーカー希望小売 18,000円(税別)
ZEN-DACは、USB-BUSパワー、もしくは別売の5V ACアダプターで動作する、USB(Type-B)デジタル入力のみの小型DAC/ヘッドホンアンプです。
フロントパネルに12Ω〜300Ωのヘッドホンに対応する6.3mm標準フォン端子と、12Ω〜600Ωのヘッドホンに対応する4.4mmバランス端子が装備されます。音量は、
RCA(アンバランス)とφ4.4mmフォン(バランス)の2系統アナログ出力を装備し、背面のスイッチで音量の固定/可変の切替が可能となっています。
ZENシリーズに共通するアルミ製の筐体には、バーブラウン製DACに自社プログラムのXMOSチップを組み合わせ、PCM 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz/24bit、DSD 2.8/3.1/5.6/6.2/11.2/12.4MHz、DXD 352.8/384KHz/24bitに対応するほか、MQAのデコードもサポートしています。この価格にもかかわらずアナログ回路はバランス方式が採用され、フロントパネルにあるボタンでON/OFFできる、低域増強機能「TrueBass」が備わります。
![]()
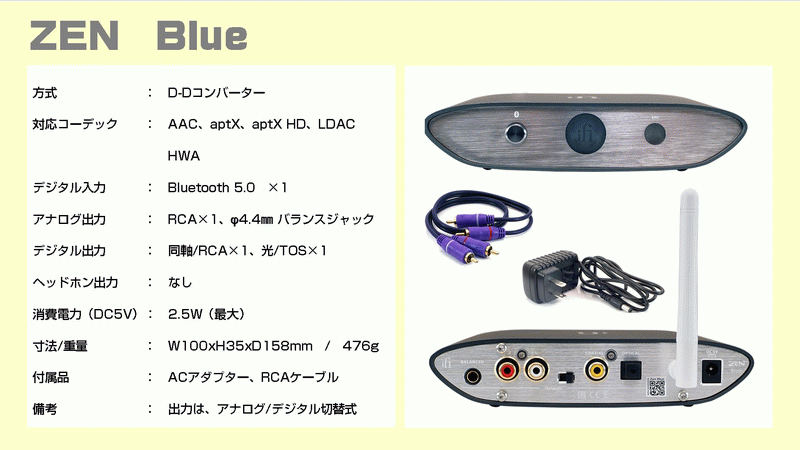
ZEN
Blue メーカー希望小売 18,000円(税別) 生産完了品
ZEN Blueは、最新のハイレゾオーディオワイヤレスに準拠したコーデック(aptX/aptX HD/LDAC/HWA/AAD/SBC)を全てをサポートするBluetoothレシーバーです。対応するフォーマトは、aptX:48kHz/24bit、LDACとHWA:96kHz/24bitまでとなっています。BluetoothチップセットにはQualcomm QCC 5100 seriesが使われ、無線でのアップデートにより、将来的に新しいBluetoothコーデックを追加することも可能とされています。
受信したBluetooth信号は、搭載されるESS製Sabre DACチップでアナログ変換され、RCA(アンバランス)とφ4.4mmフォン(バランス)の2系統アナログ出力されるほか、D-D変換が行われて同軸(RCA)/光(TOS)各1系統でデジタル出力が行われます。
![]()
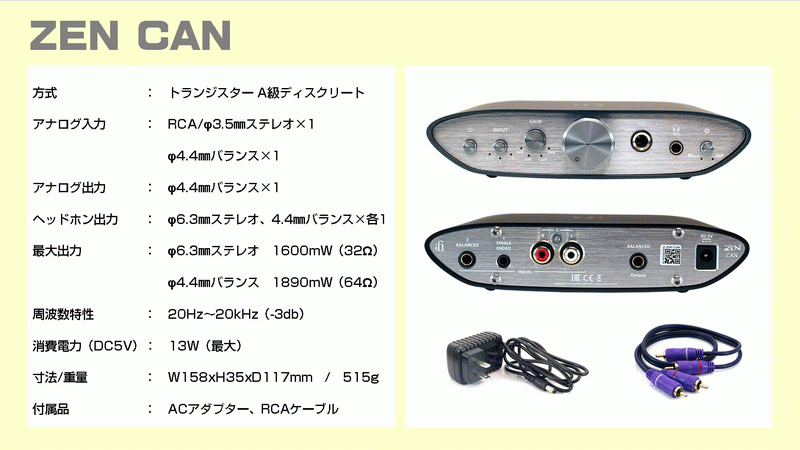
ZEN CAN メーカー希望小売 24,000円(税別)
「ZEN CAN」は、エントリークラスながらデュアルモノ・バランス構成・ディスクリートAクラスの増幅回路を搭載します。
出力ゲインは4段階の切り替えが可能で、さらに低域ブースト機能「XBass」、音場補正機能や豊富な入出力を搭載し、さらに「頭の外で」音楽を聴いているという体験を可能にする「3D Holographicデュアル・アナログ・マトリックス」機能も搭載します。
アナログ・ライン入力は、RCA/Φ3.5mmアンバランス端子各1系統とΦ4.4mmバランス端子1系統が備わり、ヘッドホン出力としてΦ6.3mm標準アンバランス、Φ4.4mmバランス端子書く1系統が搭載され、さらにΦ4.4mmバランスのライン出力が備わり、プリアンプとしても使えるようになっています。
![]()

ZEN Phono メーカー希望小売 22,000円(税別)
ZEN-Phonoは、エントリークラスでありながら、デュアル・モノラルバランス回路を搭載し高級機に匹敵する「ローノイズ」を実現しています。不要な低音をカットするサブソニックフィルターや4段階のゲイン調整を備え、MM/MCのどちらのカートリッジにもに対応します。
入力はRCAアンバランスが1系統、出力はRCAンバランスとφ4.4mmバランス出力各1系統が備わります。
iFi製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |
||||||
|
![]()
音質テスト
デジタルトランスポーターに「AIRBOW Enterprise-S」を使い、記録しているPCM信号をリアルタイムで8倍オーバーサンプリング24bitに変換してZEN-DACに入力しました。YouTubeの音質サンプルは、ZEN-DACのRCAアンバランス出力から録音していますが、試聴レポートは、ZEN-DACのアンバランス出力をAIRBOW PM12OSE MASTERに入力、モニタースピーカーは、Focal SPECTRAL 40thとAIRBOW CLT-5の組み合わせで書きました。
 AIRBOW Enterprise
S 販売価格 750,000円(税別)〜(現金で購入)・(カードで購入)
AIRBOW Enterprise
S 販売価格 750,000円(税別)〜(現金で購入)・(カードで購入)
 AIRBOW CLT-5 販売価格 175,000円(ペア・税別)〜(現金で購入)・(カードで購入)
AIRBOW CLT-5 販売価格 175,000円(ペア・税別)〜(現金で購入)・(カードで購入)
 AIRBOW PM12
OSE MASTER 販売価格 450,000円(税別)〜(現金で購入)・(カードで購入)
AIRBOW PM12
OSE MASTER 販売価格 450,000円(税別)〜(現金で購入)・(カードで購入)
![]()
ZEN-DAC / ZEN-BLUE 聞き比べ(YouTube)
![]()
音質評価 「ZEN-DAC」 USB-BUS電源
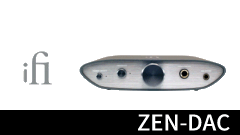

 せせらぎ
せせらぎ
価格が信じられないほどS/Nに優れ、細やかな音質に驚かされる。空間もきちんと広がり、近くで消える水泡の音と、少し離れた水面を揺らす波の音も混ざらず分離する。鳥の声は、ほんの少しだけ硬質だが、距離感やニュアンスはきちんと再現される。
特に大きな不満なく、また特有のクセもなく、価格を遥かに超える高音質に驚かされた。
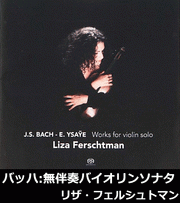 バッハ・バイオリンソナタ
バッハ・バイオリンソナタ
この曲も出だしから音が細やかで、S/Nも優れていることに驚かされる。さすがにバイオリンの子音は、ややざらざらしてしまうが、バイオリンそのものの音は素直で奏者が弓を動かすイメージ、体の動きもきちんと伝わってくる。
やや太めの音だけれど暖かく心地よく、十分に演奏を楽しめる音質だ。
この曲の持つ「憂いのフィーリング」まで再現されるのには、正直舌を巻かされた。
 新世界より
新世界より
低音がしっかり出て、弱音の再現性も十分。ハーモニーも前後左右、上下方向に正しく広がり、ホールの形状までイメージできる。
ほんの少しだけ、高音部に「ざわざわした感じ」を覚えるかもしれないが、それはかなり高性能なスピーカーやアンプを組み合わせたときでなければ、聞き取れないだろう。
この価格でここまで細やかな音楽表現が実現しているのは驚きだ。
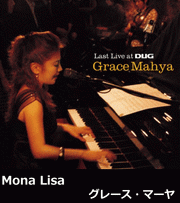 モナリザ
モナリザ
いつも聞いているよりは音が太いが、それは「良い方向」の味付けで、ギターの甘さがうまく醸し出されている。
確かに「高域の透明感」は、高級機には明らかに届かない。けれど音楽表現は、決してスポイルされていない。
ボーカルとギターの分離にも優れ、どこかで音が混ざったり、空間が濁ったりしないから、心地よくこの曲をきいていられる。
高性能なパーツを組み合わせただけの低価格DACは、いくらでも存在するが、たいてい「そういう製品」からは「音楽」が聞こえてこない。Zen
DACは、この価格でも十分に聴くに耐えられる「モナリザ」を再現する。
今のところZEN-DACで唯一の不満は「安すぎる」ことだけかもしれない。
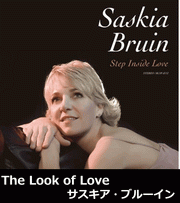 ルック・オブ・ラブ
ルック・オブ・ラブ
平均音量が大きいこの曲では、低音が少し膨らみ気味。原因は、高音の切れ味が僅かに鈍いことだが、価格を考えるとこれはこの程度だと十分納得できる。
中音域は、アナログ的な滑らかささえ感じさせるほど、きめ細やかで自然。バックに流れるストリングスの響きも硬くならない。前後方向の立体感、分離感も十分だ。
組み合わせている「デジタルトランスポート」が85万円もする、AIRBOW
Enterprise Sなので、この実力が一般的なPCと組み合わせて容易に得られるとは思えないが、底力は十分だと感じる。
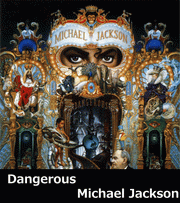 デンジャラス
デンジャラス
すごい低音が入っているこの曲は、USB BUS電源5Vだとパワー感や低音の押し出しに不満を感じることが多い。けれど、Zen DACには十分吟味した電源系が使われているのだろう。USB-BUSパワーのみで聞いていても「エネルギー不足」は感じられない。
けれどこの曲でも高域に、ほんの少し「ザラザラした荒れ」が感じられる。すべての曲で感じられる「高音のざらざら感」をどのようにコントロールするかが、Zen DACの使いこなしのポイントになると思う。
総合評価
流石に10万円を超えるような製品には届かないが、たった「18,000円のDAC」がここまでの音を出すとは、正直驚かされた。
ZEN-DACは、販売価格を考えると間違いなく望外の高性能だけれど、実は再生音質に与える影響は「DAC」よりも「デジタルトランスポート」の方がずっと大きいことは、あまり知られていない。だから、今回のZEN-DACが実現した高音質は、AIRBOW Enterprise Sの力添えによるところも大きいだろう。
果たしてこのDACを購入する人達は、どのような「デジタルトランスポート」を使うのだろう?そこはすこし割り引いて考えなければいけないとしても、この外観、この機能、この音質で「この価格」は、恐ろしいことは疑えない事実だ。
購入する、しない、の分かれ道は、このDACをどのように位置付けるかに尽きる。そもそも「HiFi」を求めるなら、この「価格」で満足できるはずない。また、DACに「これくらいしか支払わない人」が、このDACを十分に生かし切るだけの「環境」を準備できるとも思えない。
ヘッドフォンアンプとして使うならともかく、アンプへの入力ソースだと考えるなら、結局、どのような人に向けられた製品なのか?私の今までの常識や経験からは、全く見えてこない。逆に言えば、私たちが知る「HiFi」という世界がそれだけ、歪んでいるのかもしれないと、オーディオの根っこを考えさせられる製品だった。
![]()
音質評価 「ZEN-Blue」 付属ACアダプター・RCAアナログ出力
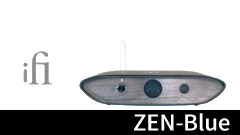

 せせらぎ
せせらぎ
音質の印象は、Zen DACとEnterprise SをUSB接続で聴いていた時とほとんど変わらないどころか、高域のざらつきが消えて音質がより滑らかになっているようにすら感じられる。接続がBluetoothになっているのにこれは驚きだ。
じっくり聞いても鳥の声の自然さ、水の音の清々しさ、アンプとスピーカーで150万円のシステムと組み合わせても全く問題ない音質が実現している。
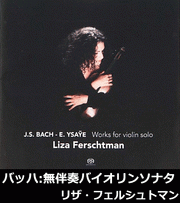 バッハ・バイオリンソナタ
バッハ・バイオリンソナタ
バイオリンの倍音もかなり高い部分まで再現され、デジタルチックな硬い音とは無縁の滑らかさも兼ね備えている。とても、スマートフォンからBluetothで飛ばしているとは信じられない音質だ。
電源が、ZEN-DACのUSB-BUSからACアダプターに変わったことによる効果もあるのだろう、低音も実にしっかりとしている。
ワイヤレスというネガティブを全く感じさせない、十分な音質にとても驚かされた。
 新世界より
新世界より
イントロ部分のハーモニーは綺麗に分離し、微弱音の再現性にも優れている。けれど、わずかに高音に「サー」というノイズが聞こえる。スマートフォンの限界なのか、あるいはBluetoothの問題なのか?今回の機材では原因を解明できなかったが、静かな音楽を聴くときには、大きな問題になるかもしれない。
そのノイズを除いては音質的には十分納得できて、楽器の音色の変化、立体感、どれもが十分に演奏を楽しめるレベルに達している。
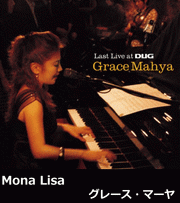 モナリザ
モナリザ
やはり高音にZen DACで聞こえなかった「サー」というノイズが出ている。自宅で使っているBluetoothスピーカーも、音声が出ているときは「サー」ノイズが出ているので、Bluetoothの接続問題なのかも知れない。けれど、marantzのオーディオ機器では、Bluetoothでも高域ノイズは出なかったように思うので、やはりZEN-Blue固有の問題の可能性も残されている。
ギターの音色の透明感は、Zen
DACよりも優れているほど美しく、ボーカルとギターの分離や関係の濃密さもきちんと再現される。
引き付けられる音質だが、耳を澄ますと高域ノイズや細部のディティールの不完全さにやや興醒めるときがある。
上級機と比較すると物足りない、けれど同価格帯の中ではすごいデバイスという評価になると思う。
コストパフォーマンスは抜群だが、同時に「中途半端な高音質」でもある。
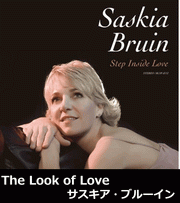 ルック・オブ・ラブ
ルック・オブ・ラブ
音質や音色は、見事にZen DACと統一されている。単純にパーツを組み合わせただけでは、ここまで音調は整わないと思うから、Zenシリーズはきちんとしたヒヤリングも行われているのだろう。サウンドマネージャーが、mark-levinsonに在籍したあの「JC」だと聞かされて腑に落ちた。
最初は良くても、しばらく聞くとその音質に「やや不満」を感じるところもあるのだが、接続が「Bluetooth」であると思い出せば、とても驚くことになる。つまり、専門家が聞いても「Bluetooth」とはにわかに信じられないほど良い音が出ているということなのだ。
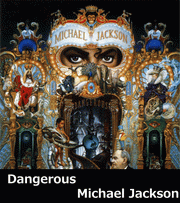 デンジャラス
デンジャラス
イントロの弱音部には、もう少しの細やかさが足りない。 けれど、音量が大きくなるとそういう不満は完全に消えてしまう。
ZEN-Blueの長所は、音が混じらず、空間が濁らないことだ。 どれほど音が細やかでも、音色が分離しなければ、ハーモニーの重なりが混じってしま。 ハーモニーが美しく重なってこそ、音楽が心地よく聴けるようになる。その点で、ZEN DAC、ZEN-Blueは、きちんと基本を押さえている。
この曲でもZEN-DACよりも低音がしっかり出るのは、ACアダプターの効果なのだろう。中低域の力感や量感に不満が出ない。
もちろん、さらに高音質な機器と聴き比べれば、色々と不満も出て来るだろうが、Bluetoothでここまでの音が出るとは、技術の進歩はすごいことだ。さらにその価格を知れば、経験豊富なマニアであればあるほど、口数が少なくなるだろうと思う。
![]()
音質評価 「ZEN-Blue」 付属ACアダプター・同軸デジタル出力・AIRBOW SACD 30n Replay
ZEN-Blueのもう一つの使い方、「D-Dコンバーター」としての性能を探るため、開発が完了したばかりの「AIRBOW
SACD 30n REPLAY」を同軸デジタルで繋ぎ、音質をチェックしました。
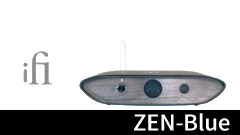

 せせらぎ
せせらぎ
より遠くの鳥の声まではっきりと聞こえ、水の粒子もずっと細やかだ。立体的な音の広がりも、数段、いや数倍良くなっている。
CDと大差ないと感じさせるほど、本格的な高音質な音に変わった。
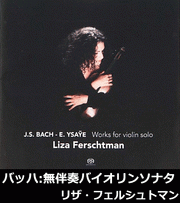 バッハ・バイオリンソナタ
バッハ・バイオリンソナタ
演奏会場の透明感、バイオリンのきめ細やかさが全く変わってしまったが、高域の少しざらざらした感じや、ほんの少しの空間の濁りには、まだ納得できない。CDのクオリティーにはすこし届かないが、それと知らされなければ気づかないかも知れない。
高域の「サー」ノイズは出なくなった。
 新世界より
新世界より
徐々に聞き慣れてきたのか、SACD-30n ReplayとZEN-Blueのアナログ出力との違いがそれほど大きく感じられなくなってきた。
けれど音が良くなった結果、逆にBluetoothの圧縮の問題だろうか、音がある程度音が小さくなっても気配が残っているはずなのに、そこが「完全に無音」になってしまうことが気になるようになってきた。
音が消える問題は全域で発生したのではなく、再生中数回感じただけだったが、弱音部の「間」も大切にしなければならない交響曲では、演奏が途切れてしまうこの現象は、致命的になってしまった。
今回は、スマートフォンにasus Zenfone 5、再生アプリにはVLCを使ったが、送り出しのシステムを変えると、この問題は解決するのだろうか。
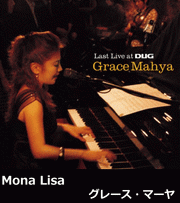 モナリザ
モナリザ
SACD-30n ReplayをDACに使ったことでギターが強くなり、奏者の指使いまで見えるようになった。ボーカルは抑揚が大きくなり、声質の魅力も増ししている。
けれど、交響曲で感じたように弱音部に「圧縮されて端折られたような音の消え」を感じるようになった。これは、アナログ出力では感じられなかったので、再生系の精度が上がった結果、見えてはいけないところまで見えてしまったということなのかも知れない。新世界でも書いたように、この問題が「再生系(ワイヤレス送り出し)」で解決することが望まれる。
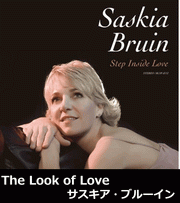 ルック・オブ・ラブ
ルック・オブ・ラブ
高域がしっかりと伸びたことで、低音の膨らみがかなり解消された。ギターやピアノの音、ドラムなどの伴奏とボーカルの分離も向上している。温度感も上昇し、より暖かく、情緒のある演奏に変わってきた。弱音部がほとんど存在しないこの曲では、音消えの問題も全く起きてこない。
コンプがかけられて、平均音量が大きくなっている録音では、全く問題のない良い音を聞かせてくれるが、ZEN-Blueが「積極的に音楽をより楽しく聞かせること」はない。その点、同じジャンルの製品でもaudioquest製品は、高級ケーブルでの音作りの経験が生きているのか、音楽をよりおいしく聞かせてくれる方向に絶妙な味付けがされていると思った。
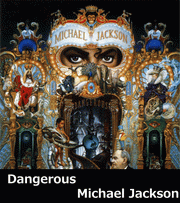 デンジャラス
デンジャラス
エネルギー感が一気に向上し、リズムが弾み、普段聴いているのと同じ感覚で「デンジャラス」が聴けるようになる。
交響曲やバラードでは弱音部の再現性に若干問題を感じさせたが、平均音量が大きいPOPSでは、全く問題ない音が出る。
繊細さを敏感に感じ取れる「鍛えられた耳」でなければ、問題なく「高音質機器」として通用するだろう。
![]()
音質評価 「ZEN-Blue」 強化電源 iPower 5V・同軸デジタル出力・AIRBOW SACD 30n Replay
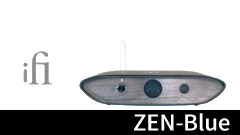
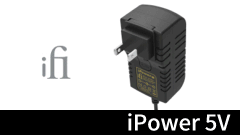

ZEN-Blueの電源を「付属ACアダプター」から、別売の「iPower」に変えて見ました。
 せせらぎ
せせらぎ
音質がよりきめ細やかになって、全体的に数割ほど「上乗せ」された感じだが、劇的な変化というほどではない。
電源の価格を考えると、まあ順当なグレードアップだろう。
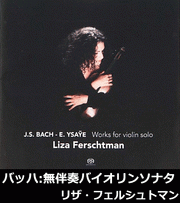 バッハ・バイオリンソナタ
バッハ・バイオリンソナタ
バイオリンの音色に、木質的な「甘さ」が感じられるようになってきたが、やはり「弱音部」が端折られているように聞こえる。
あるところから音がなくなったように感じられるため、ホールの悪い席で演奏を聴いているような雰囲気になる。
悪い音ではないが、クラシックを聴くには、少々物足りない。
 新世界より
新世界より
音が大きいと「端折られた感じ」はほとんどなくなるが、イントロの弱音部などでは情報量が、音量に伴って少なくなっていることを感じる。そして、弦楽器の音のつながりが「断続的」に聞こえる問題も解決しない。
さらに外部DACの追加で音が良くなった結果、ZEN-Blueのアナログ出力ではなかった「バックグランド」に何らかのノイズが入り、空間が濁るのも気に入らない。
この曲を「普通」に聞き流すなら何も問題はないが、名演奏として聴こうとするなら、D-Dコンバータとして使うZEN-Blueにはそこまでの能力は望めない。今回は試せなかったが、より高音質なBluetoothコーデックを選べば解決するのだろうか。
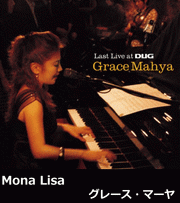 モナリザ
モナリザ
この曲も背景に何らかのノイズが付き纏う。アナログ出力では、それほど気にならなかったノイズが、DACを高性能化したことで目立ってきたのだろう。ギターやボーカルの表現は向上しているだけに、もったいない。
電源の強化は、音質を改善すると同時に、ZEN-Blueの問題点も拡大してしまった。
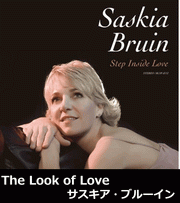 ルック・オブ・ラブ
ルック・オブ・ラブ
平均音量が大きいこの曲では、全体のボリューム感が向上し音が前に出るが、やや前に出過ぎる気もする。
バランスは、付属ACアダプターの方が好ましかったかもしれない。電源アップグレードの是非判断は少し難しい。
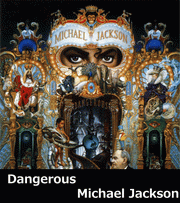 デンジャラス
デンジャラス
空間の広がりや、パワー感には問題がない。音質もかなりのレベルだ。
けれど、音質が向上した結果、聞こえなくてもよい問題点まで聞き取れてしまう。
一度その問題点に気付いてしまうと、よい音さえ耳に届かなくなるが、それは「よい音を知り過ぎた」私の耳の問題なのかも知れない。普通の人がこの音を聞けば、間違いなく「びっくりするくらいよい音」と判断するはずだ。
総合評価
今回組み合わせた「asus Zenfone 5」と搭載する通常のBluetoothコーデックでは、音質を改善すればするほど弱音部が消えてしまうという問題が顕著になった。電源をアップグレードすると、音質と共に問題点も拡大した。
絶対的な性能では、ifi audioのZEN Seriesは驚くほどのパフォーマンスを持っていると判断できる。価格の限界内で音を纏めず、あえてその壁を破った努力は素晴らしいし、その技術もすごい。よくぞこの価格で、外観や機能、そしてこの音質を実現できたものだ。けれどオーディオ専門店とすれば、価格は2倍程度になってもよいから、完全に納得できる音質を望みたい。それが率直な感想だ。
![]()
音質評価 「CAN」比較対象として、asus Zenfone5 ヘッドホン出力を試聴

 (再生ソフトは、VLCを使用)
(再生ソフトは、VLCを使用)
 せせらぎ
せせらぎ
高音が強く、子音がやや耳につく。遠くの鳥の鳴き声はよく聞こえるが、立体感はそれほどでもなく、ヘッドホンで聴いている音とすぐにわかる。左右の音は、それぞれ耳から聞こえ、スピーカーで聴くときのように中央や前方に音像は広がらない。
いずれにしても、高音の輪郭が強すぎる。
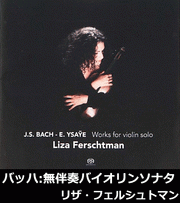 バッハ・バイオリンソナタ
バッハ・バイオリンソナタ
スピーカーで聴く時に比べると、音は細やかで明瞭度もとても高い。音色や音質には大きなクセがなく、高音の隈取りの強さが緩和されれば、モニターとしてきちんと聞けそうだ。
スマホの出力でさえこの音質というのは驚きだが、ホールトーンや楽器の豊かな音色、響きの余韻までは再現されない。バイオリンを間近で聞いている印象だ。
 新世界より
新世界より
低音は聞き取れるが、体では感じられない。首から上だけをコンサート会場に突っ込んで音楽を聴いているような印象。演奏者が体を動かしたときの物音や、楽器の軋みまで聞き取れ、臨場感や緊張感はビシビシ伝わるが、演奏を感じている、何かが伝わってくる感覚は薄い。指揮者の唸り声もはっきりと聞き取れるが、全ての音が音源が近すぎる。
音場の広がりや、楽器のサイズが小さすぎる。
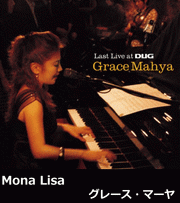 モナリザ
モナリザ
完全に左右が分離して録音されているこの曲をヘッドホンで聞くと、ギターの音が左側からしか聞こえなくなる。
細やかな響きまではっきりと聞き取れるが、量感が不足して楽器のサイズが小さくなっている。
ボーカルも同様、胸の音や体の響きが皆無なので、口先だけで歌っているように聞こえてしまう。
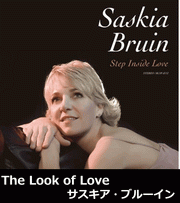 ルック・オブ・ラブ
ルック・オブ・ラブ
スピーカーでこの曲を試聴したときに低音が膨らんで聞こえたのは、明らかに低音過多で録音されているからだと、ヘッドホンで聴くとすぐにわかる。声も中音が不自然に盛り上がっていて、ラウドネスがかかっているような帯域バランスだ。
楽器とボーカル、伴奏の楽器が個々に完全に分離していて、複数のトラックが合成された演奏だともすぐにわかる。
「不自然な所」、「ミキシングの未熟さ」が強調されるだけで、ちっとも音楽は聞こえてこない。
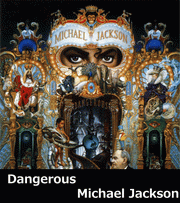 デンジャラス
デンジャラス
打ち込みの低音はすごくよく出て量感も十分なのに、持続する重低音が圧倒的に不足している。スケール感が引き出されず、イントロの効果音がまるでおもちゃのようだ。そして高音は耳に痛い。長時間はとても聴いていられないハードな音。
マイケル・ジャクソンの声には、不自然な「電子エコーの癖」が聞き取れる。
スピーカーで聴くと見事なミックスだと唸らされるこの曲が、バラバラになってしまった。
とにかく高音が強すぎて、耳から血が吹き出してきそうなほどだ。
![]()
音質評価 「ZEN-CAN」 強化電源 iPower 5V
イヤホンで音楽を聴くだけなら、スマホ内蔵アンプで音量的にも音質的にも十分だと私は感じているから、Zen Canの用途は「大型ヘッドホンをスマホと組み合わせて聴く場合」と考えて、今回Zen Canをテストしている。
ヘッドホンに「Sennheizer HD-25-1」を選んだのは、より高価なヘッドホンを愛用するヘッドホンマニアがこの程度の価格のアンプを求めるとは思えなかったからだ。
試聴は、asus Zenfone 5のヘッドホン出力とZEN-CANのRCA入力をAIRBOWのケーブルで繋いで行ったが、ZEN-CANは豊富な入出力に加え、0/6/12/18の四段階のゲイン切り替え、さらに低音を増強する「X
Bass」、スピーカーで聴いているような広がりのある音場を生み出す「3D
Holographicデュアル・アナログ・マトリックス」が搭載されている。すべての曲を聞き比べる前に、まずそれぞれの機能と音質を簡単にチェックしすることにした。
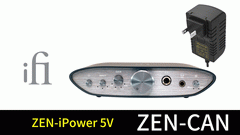


まず、電源は付属のACアダプターを使い、それぞれのゲインで音質がどのように変わるのかをざっと聞いてみた。
ゲイン:0
スマホから出力される音を増幅せずにそのまま出力するモードだが、気になっていた高音の強調感が消え、バランスが整うばかりではなく、音の滑らかさや広がりも改善する。ヘッドホンを数倍価格の高級品に変えて聴いていると感じるほど、素晴らしい音質改善が実現したが、高音の
これは音質チェック以前に、不良を疑うほど大きな問題だ。ACアダプターの極性を変えてみたが、ノイズは変わらない。
ノイズの種類から、その原因は「ACアダプター」とわかっているので、付属ACアダプターを諦め別売の高音質ACアダプター「iPower 5V」に変えてみると、気持ちよくノイズが消えた。ACアダプターの安価なスイッチング電源から、アンプにノイズが混入していたようだ。こんなことなら、価格は上がっても標準で「iPOWER 5V」を付ければいいと思う。
とにかく、別売の「iPower 5V」を使うことでノイズからは解放された。
音質は少し細やかさが増したかな?と感じる程度で、それほど向上はしていない。逆に高域がまた強くなり始めた。
音のバランスは、付属アダプターの方が好ましかったように思えた。
4段階あるゲインをすべて聴いてみたが、音質にはほとんど変化がない。
たいていの場合スマホのアナログ出力は「デジタルボリューム」が使われているので、音量を絞ると「ビット落ちによる音やせ」が引き起こされる。Zenfone 5のボリュームがどのような方式かは調べなかったが、音量を絞るとやはり音が悪くなる気がしたので、スマホのボリュームを最大の90%程度にして、ZEN-CANをゲイン12、別売電源「iPower」で試聴を開始した。
X Bass
通常のヘッドホンで聴く限り、ON/OFFで低音の量感はそれほど大きくは変わらなかったが、せせらぎでチェックすると、ONで空間のスケールがやや大きくなったことで、ローエンドの低音が増強されたことがわかる。
多分、イヤホンで聴くともっと大きい変化が出るだろう。
3D
ONにすると高音のエネルギーが強くなり、響きの成分も少し増える。
AVアンプの「擬似サラウンド」に似た効果だが、帯域バランスが高音によってしまうのが気になる。
そこで、定温を伸ばす効果のあるX Bassと合わせて使うと、低音と高音の両方に帯域が伸びて、空間も広がった。
特に嫌な癖もないので、音楽に合わせて使える機能だと感じられた。
しばらく両方ONで聞いた後、OFFにすると空間が狭まってちょっと寂しい感じになったから、ifiの主張する「3D効果」は、それなりにあるのだろう。
 せせらぎ
せせらぎ
スマホダイレクト出力では感じられなかった「空間」が生み出される。耳のすぐそばで音が鳴っているだけではなく、ヘッドホンの外側にも空間が広がる。高域はまだ強めだが、嫌な強調感は消えている。
川の流れる音はより滑らかに、鳥の声の質感や、声色のバリエーションも多くなった。かなりの向上を感じる。
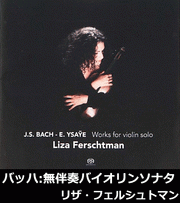 バッハ・バイオリンソナタ
バッハ・バイオリンソナタ
バイオリンの音が「本物」になった。音の細やかさや滑らかさも向上している。たった、22,000円+円でここまで音質が向上するのは素晴らしい。
スマホダイレクト出力では聞こえなかった「演奏」がしっかりと再現される。この曲は、ZEN-CANなしでは聞けない。
 新世界より
新世界より
イントロの低音の厚みが全く違う。高域の余分な隈取りはすこし邪魔だけれど、それを除けばスピーカーでこの曲を聴いているときの感覚にかなり近づいてきた。
ハーモニーの複雑さ、ホールの豊かな響きが再現される。何よりも「聴いていたい演奏」になったことが大きく違う。
私はこのヘッドホンを「生録時のモニター」に使っているが、生音をモニターしている時のバランスにかなり近く、スマホで再生されている音楽を聴いている感覚は完全に消えている。素晴らしい音質だ。
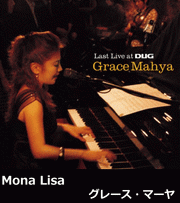 モナリザ
モナリザ
スマホダイレクト出力では、左からしか聞こえなかった「ギターの響き」が「右側から」も聞こえるようになったことで、左右が完全に分離している印象が緩和される。もちろん、スピーカーで聞いている時ほど「中央定位」は濃くないが、少なくとも演奏を聞ける程度には改善された。
ボーカルの子音はまだ強いが、アンプが無理に強調している感じではなく、録音の癖と割り切れるようになった。
グレース・マーヤさんの「唇の濡れた感じ」も出てきて、この曲もスマホダイレクトとは比べられないくらい良い音になった。
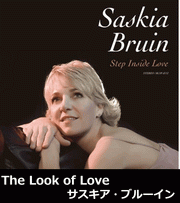 ルック・オブ・ラブ
ルック・オブ・ラブ
今まで聞いた曲では「大きな改善」があったが、この曲ではボーカルの子音がめくれあがって耳に突き刺さる。
中低音の膨らみは、ZEN-CANを追加してもどうしようもなく、演奏以前の問題で、ミキシングがめちゃくちゃだと感じてしまう。
スピーカーで聞いても「癖の強い録音」だとは思ったが、ヘッドホンで聴くとそれがとても聞けたものではなくなる。
唯一の救いは、中低音の量感が増して音が暖かく、滑らかになったことだろう。
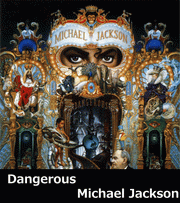 デンジャラス
デンジャラス
スマホダイレクト出力では、感じられなかった「空間・立体感」が創出される。
打ち込みの低音はより太く、響きも長い。
高音はあいかわらずとても強いが、ヘッドホンを投げ捨てたくなるような「嫌な感じ」はなくなった。高音のざらつきが消え、その切り口がノコギリからナイフで切ったように鋭いが滑らかなものに変わったからだろう。
音質にこだわったマイケル・ジャクソンらしい「録音・ミキシング機材の音の良さ」がはっきりと聞こえてきたが、それでもこの曲はヘッドホンで聴くには「高音が強すぎる」ようだ。
聴き続けていると、ヘッドホン難聴になりそうだった。
![]()
音質評価 「ZEN-Phono」 付属ACアダプター(ヤマハ GT-5000、Goldring EROICA GX、AIRBOW BV-33)




上記のかなり高価なレコードシステムで「ZEN-Phono」 を付属ACアダプターで試聴した。
 とまどうペリカン
とまどうペリカン
中低音はよく出ているが高域の抜けが悪く、音もそれほど細やかでなく、滑らかさも不足している。解像度もイマイチ物足りない。電源投入直後はそんな音だったので、LP片面20分ほどウォーミングアップしてから聞き始めることにした。ウォーミングアップで音質は激変、高域の抜けが良くなり、細やかさも滑らかさも向上した。
この曲は、様々なシステムで何度も聞いてきたので違いがわかりやすい。
ZEN-Phonoの音は、アナログでけれどややデジタルチックな趣がある。響きが少なめで、高域の滑らかさやレコードらしい透明感はそれほど高くはない。それに対して、中低音の膨らみは少なく、ストレートな音質というイメージだ。
伴奏とボーカルの分離は、程よい感じ。井上陽水の鼻にかかった声の感じもよく出ている。
これでもう少し「色鮮やかさ」が出てくればいうことはないのだけれど。
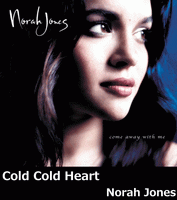 コールド・コールド・ハート
コールド・コールド・ハート
このレコードの録音は、あまり「アナログ」らしくない。あたかもデジタル音源をレコードに記録したような音だ。けれど、久しぶりに聞いてみると、滑らかさや、中域の厚みや暖かい感じ、響きの良さに、やはり「レコードは良いなぁ」と感じてしまうから不思議だ。
価格の問題、限界だから仕方ないとは思うが、やはり高域の透明感や質感が物足りない。逆に言えば、中低音が価格を上回る音質だとも言える。
ZEN シリーズ全体のテイストは、音楽を心地よく聞かせるというよりは「音質向上」にポイントを置いているように感じられた。
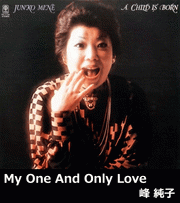 マイ・ワン・エンド・オンリー・ラブ
マイ・ワン・エンド・オンリー・ラブ
私は嶺純子というボーカリストが大好きだ。20代の頃、初めてそのレコードを聴いてから虜になっている。中でもこの曲は大好きだ。ボーカルにはムードがあって、ピアノの音も良いし、録音も素晴らしい。
それをZEN-Phonoで聞くと、もちろん音は悪くない。けれど、このレコードの実力はこの程度ではない。
本物の音を知っているだけに物足りなさが残るが、価格を考えるとピアノの低音は素晴らしいし、ボーカルの滑らかさや質感も十分だ。ただ、レコードを聞かせるというテイストでは、プレーヤーも作っている「porject製品」の方が一枚上手なような気がする。
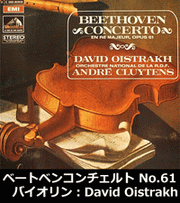 ベートーベン バイオリンコンチェルト
ベートーベン バイオリンコンチェルト
このレコードでは「音色の薄さ」が致命的となって、良いホールで行われた素晴らしい演奏の「色彩の美しさ」が再現されない。
絶対的な音質はそれほど悪くはないが、交響曲の決め手であるハーモニーがうまく引き出されない。オイストラフのバイオリンもかすれた寂しい音だ。壊れたバイオリンのような音。これはいただけない。
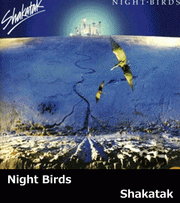 ナイト・バーズ
ナイト・バーズ
リズムが重く、曲が弾まない。ピアノは高音がくぐもっていて、音が細く寂しい。
低音はベタベタして、リズムがバラバラになっている。
この曲も、ZEN-PhonoではNGだ。
![]()
ZEN シリーズ総合評価
価格が信じられないほど仕上げがよく、機能も豊富なことに驚かされる「ZEN シリーズ」だが、音質は音楽を心地よく聞かせるという方向ではなく、より高音質を求めて作られているように感じられる。デジタル系のプロダクツでは、その音質傾向がピタリとマッチして、思わずハッとするほどの音を出してくることがある。
アナログ系のプロダクツでは、ヘッドホンアンプが信じられないほどまとまりが良く、その価格を疑うほどだ。
シリーズで唯一、私がダメだと思ったのが、フォノイコライザー(ZEN-Phono)だ。十分に温めたにもかかわらず、レコードの美味しいところが引き出せなかった。
ZENシリーズをおすすめに順に並べるなら、
1.Zen Can 、 2.Zen DAC 、 3.Zen Blue 、 4.Zen Phono
の順になる。
ZEN-CANは、とてもおすすめだが付属のACアダプターだとノイズが発生することがあるので、別売の「iPOWER」が必須になる。
ZEN-DACは、良い音だが製品としての「立ち位置」が私にはイメージできなかった。良い音を求めるなら、いくらなんでももう少しお金を出せるはずだからだ。
ZEN-Blueは、音質を欲張りすぎたのか、今回の試聴ではBluetoothの悪い部分まで出してしまったように感じられた。けれど、ハイレゾに対応するような高音質コーデックで接続すれば、例えばLDACなどを使えば印象はグンとよくなるかも知れない。
実力派のD/A・D/Dコンバーターだと思える。
ZEN-Phonoは、個人的にはあまり好みではなかった。中低音は素晴らしいものの、アナログの美味しいところがうまく引き出せていないように感じられたからだ。project Phono Boxの方が、よりアナログらしい音を出してくれると思う。
最近の「中国製品」の出来栄えは素晴らしい。仕上げもよく、品質にも優れている。工業製品として「コピー」すべきところは、完全にコピーしているどころか、下手をすればオリジナルさえ上回るほどのレベルに達していると思える。
けれど、「味わい」という数値化できない仕上げは完全ではない。「JC」をもってしても、そこは価格の限界なのだろう。けれど、もしこの価格で味わいまでコピーされると、完全なオーディオ製品の価格破壊が起きるだろう。
とは言え、ハイエンドオーディオ製品を購入する人たちが、こんな価格の製品の音質に耳を傾けるとは思えないから、問題は起きないか!
![]()
2021年2月 逸品館代表 清原 裕介