■各種コンテンツ
■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部
オフィシャルサイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer ネットワークプレーヤー NA70A 音質 比較 プリアンプ 新製品 試聴 音質 価格 販売 比較 marantz airbow NA6005 Live NA8005 Studio TAD C2000 試聴 音質 価格 販売 比較
 N70A ネットワークプレーヤー
N70A ネットワークプレーヤー
 NA6005
Live 、 NA8005 Studio 、 MSS-i3/MSHD
NA6005
Live 、 NA8005 Studio 、 MSS-i3/MSHD
 C2000(内蔵USB-DAC)
音質比較テスト
C2000(内蔵USB-DAC)
音質比較テスト


※ネットワークプレーヤーとPCは、AIRBOW ウェルフロートボードに乗せて試聴しました。
Pioneer(パイオニア)から本格的な機能と内容を持つネットワークプレーヤー"N70A"が求めやすい価格で発売され、このジャンルのベストセラー製品になっています。今回は、そのN70Aの音質を徹底的にチェックするべく、AIRBOW NA6005 LiveとNA8005 Studio の2機種のネットワークプレーヤーと比較しました。
ネットワークプレーヤーは接続できる機器が多く、再生できるフォーマットも豊富です。今回は、その中から基本的な音質を探る目安として媒体やソフトによる変化が比較的少ない接続として「USBメモリー直接接続」を選択し、最も音の良い接続として「ネットワーク接続(機種により有線と無線接続を使い分け、サーバーには高音質なAIRBOW オーディオ専用PC MSS-i3/MSHDを使いました。)」の2つを選びました。
再生に使うアンプとスピーカーは、音質をしっかり比較するため、高音質なハイエンド・オーディオシステムTAD E1、M2500、C2000を使用し、USB入力の音質リファレンスとして、C2000に搭載される内蔵DAC(USB)を2つのPC(Mac Book、AIRBOW MSS-i3/MSHD)で試聴しました。
 TAD
C2000 M2500 (お問い合わせ・ご注文はこちらから)
TAD
C2000 M2500 (お問い合わせ・ご注文はこちらから)
 AIRBOW
MSS-i3 MSHD (お問い合わせ・ご注文はこちらから)
AIRBOW
MSS-i3 MSHD (お問い合わせ・ご注文はこちらから)
最新のAIRBOW デジタル機器のご購入お問い合わせは、こちらからどうぞ。 |
||||||
|
テスト概要のご紹介動画
![]()
試聴ソフト
CDリップWAV(44.1kHz/16bit)に加え、ハイレゾ(88.2kHz/24bit)とDSD(2.8MHz)を試聴
今回の試聴は回数が多いので、いつも使う5曲から2曲を省き、E.ONKYOサイトから発売されている「What a Wonderful World / Mathias Landaeus Trio / MA Recording」のDSD 2.8MHzとWAV 88.2kHz/24bitの2曲(2ファイル)を加えた5曲を聞きました。
![]()
音質テスト
Pioneer (パイオニア) N70A メーカー希望小売価格 \142,000(税別) お問い合わせはこちら 生産完了 |
||
|
||
|
音質試聴動画へのリンク
せせらぎ 癖のない音だが高音が少し丸くなり(音の角がほんの少し丸い)、輪郭がぼやけるので音場の広がりがやや平面的に感じられる。また、高音のメリハリが弱いため明瞭度に影響が出て、細かな音の再現性が完全ではなく、空気感までは出ないが、細かい音は十分聞き取れる。 多くのネットワークプレーヤーには、音が硬く、冷たく、ざらざらしているが、N70Aは一切そんなことはなく、暖かい音でせせらぎが鳴った。 モナリザ ボーカルはきめ細かいが、少し粉っぽく感じられるところがある。ギターは、高次倍音が少し伸びきらない。 癖のない音だが、やや演奏が単調に感じられた。 新世界 低音は良く出て、音は太く、弦楽器の柔らかさも出るが、弦楽器の倍音構造がややぼやけている。また、前後方向への音の広がりもやや浅い。 コンサートホール後方の壁際で演奏を聴いているようなイメージで、やや濁りを感じるが実売10万円という価格を考えれば十分な音質だ。 What
a Wonderful World (88.2kHz/24bit) CDリップの再生と比べるときめ細かくなったが、ピアノの倍音はやはりそれほど伸びてこない。高音には、まだ薄くベールがかかっている。 フォーマットを変えてもベール感がなくならないのは、N70Aの高域再生に限界があるためだろうか。 What
a Wonderful World (DSD/2.8MHz) PCMハイレゾとほとんど音は変わらないが、僅かに滑らかで柔らかくなったイメージがある。 多くのDSDソースは、PCM録音をDSD変換したものだから、変換しないPCMの方が音が良いことがある。このソフトもそういう感じで、メリハリのあるPCMハイレゾの音が好みだった。
せせらぎ USBメモリー再生に比べて高音が伸び、音の角が立つ。気になっていた薄いベール感もほとんど消えて、空気感も再現されるようになった。 USBメモリーに比べて明らかに音が良く、USBメモリーをCDに例えるなら、LAN接続はSACDにアップグレードしたくらいの差は感じられる。 モナリザ ギターの倍音が綺麗に伸びるようになり、ボーカリストの唇の濡れた感じ(潤い感)も伝わるようになってきた。 ライブ会場のホールトーンも再現されるようになり、USBメモリー時とは音質が全然違って感じられる。 USBメモリーの音を10万円だとすると、LAN接続では20-30万円くらいの音質にアップする感じだ。 新世界 USBメモリーとは音の細やかさ、空気感が全く違っている。弦楽器の音色の違いもきちんと再現され、エコーが消える所まで綺麗に聞きとれるようになった。 USBメモリーが後方の席なら、LAN接続はS席。十分に納得できる良い音で新世界が聞けた。 What
a Wonderful World (88.2kHz/24bit) CDリップよりも明らかに楽器の音が細かく聞こえ、楽器を取り巻く空気の振動も感じられるが、高音が出たため相対的に低音が不足して音が軽くなった。 What
a Wonderful World (DSD/2.8MHz) PCMハイレゾよりも音が明るくなるが、高音の特定部分にピーク感が出て、ピアノの右手のタッチが粗く(雑に)感じられるようになった。 少し聴き疲れする音で、あまり良いとは思えない。 総合評価
USBメモリーの音とLANの音は全く違っているが、それにはサーバーとして使用した場合一般的に使われているNUSやQNAPと比較して音の細やかさ、高域の透明感に優れているAIRBOW
MSS-i3(5) MSHDの効果が大きいと思われる。しかし、そうでないサーバを使用した場合もUSBメモリーよりも音が良いことが多いので、ネットワークプレーヤーはネットワーク(LAN)で接続するのが本来の使い方だろう。USB接続を使うのであれば、わざわざ高価なネットワーク機能を搭載する必要はなく、USB-DACで十分だ。 Pioneer
N70Aは初期のUSB-DACやネットワークプレーヤーのような高音が硬くてざらついた音ではない。またPioneerがこれまで発売してきたCD/SACDプレーヤーと比較するのであれば、その価格以上の音質には十分達している。けれど10万以下で購入できる響きの良いCDプレーヤーと比較した場合、高音の響き(広がり感)が少し物足りないかもしれない。また、同じ価格帯のmarantz
NA8005と比べ、よく言えば癖がなく、悪く言えば面白くないという印象を持った。しかし、NA8005の音はもっと元気で個人的には好みだが、N70Aを基準にするならば高音が少しざらつく印象があるかも知れない。 楽しさのmarantz
NA8005、質感のPioneer
N70Aと、選択は非常に悩ましいが、型フロントパネルに再生曲のジャケットを含めた豊富な情報が表示される、本格的なXLRバランス出力が装備される、など機能面を含めて評価するなら、実売価格の10万円強は十分お買い得に感じられる。 |
![]()
AIRBOW (エアボウ) NA6005 Live メーカー希望小売価格 \127,778(税別) お問い合わせはこちら |
||
|
||
|
音質試聴動画へのリンク
せせらぎ N70Aよりも高音が細やかで滑らか。鳥の声も細かい部分までハッキリと聞き取れるが、高音が伸びすぎて少し耳に付く時がある。 けれど、全体的には暖かく肉付きの良い音で、N70A/USBメモリーよりは明らかに音が良く、N70A/LANの音に近いクォリティーでせせらぎが鳴った。 モナリザ ギターの音が太く、力強い。ライブ会場のホールトーンも消えゆくところまでハッキリと聞こえる。ボーカルは柔らかく、雰囲気が濃い。 ライブを聴いている説得力を感じる、充実感を覚える音でモナリザが鳴った。 新世界 低音部の音階がきちんと聞き取れる。金管楽器は力強く伸びやか。交響曲に独特なハーモニーやユニゾンがきちんと聞こえる。 音がスッと立ち上がり、スッと無に還る。何のためらいやストレスもないその音は、生演奏を聴いている感覚に近い。 本格的なオーディオ機器の音質で新世界が鳴った。 What a Wonderful World (88.2kHz/24bit) CDよりも音は良いが、PCMハイレゾのフォーマットが持つ良さが十分に発揮されていないように感じられた。 What a Wonderful World (DSD/2.8MHz) marantzの製品でPCMハイレゾとDSDを比べると、DSDの音が小さい。たぶんDACの仕様なのだろうが、そのため聞き比べが難しい。 その点を考慮してもDSDの音は癖がなく、高域の透明感も高い。
せせらぎ N70AではUSBメモリーの音とLANの音には大きな差が感じられたが、NA6005
Liveでは双方の接続で音質やバランスにほとんど変化がない。 ただし情報量は増え、USBメモリーのせせらぎが「小川」なら、LANのせせらぎは「大川」に感じられる。川の水量に違いがある。 モナリザ ギターの音に高級感が出て、良い木が響いているように伝わる。ボーカルも質感が向上した。 ギターとボーカルの関係性が密になり、演奏の精度と雰囲気が向上し、プロっぽい聴き応えのある演奏になった。 新世界 USBメモリーよりもS/Nが向上し、会場の静けさやホールの澄み切った空気感が感じられ、ノイマン/チェコフィルらしい精緻なイメージが出た。 What
a Wonderful World (88.2kHz/24bit) 肝心のピアノの音がそれほど良いとは感じられないが、ピアノ後方に展開されるシンバルの高音の抜けの良さ、バスドラムの低音の空気感などにCDをこえるハイレゾの良さが感じられるようになった。USBではその良さがあまりでなかったが、LAN接続ではCDリップの音から2倍くらいの価格のプレーヤーに変えたくらいの違いはある。 What
a Wonderful World (DSD/2.8MHz) NA6005
Liveとの組み合わせではDSDの音質が好ましく、ライブ感が出てとても聞きやすくなった。伴奏とピアノの音量やエネルギー感のバランスに優れ、目の前で演奏されるライブを聴いている雰囲気が醸し出される。 総合評価
NA6005
LiveはN70Aよりも全体的に音が細かい。また高域の透明感が高く、中低域のエネルギー感も強く、ダイナミックレンジや周波数レンジが広く感じられる。また、一般的なネットワークプレーヤーが感じさせる「ネットワークプレーヤー特有の悪癖」がほとんどなく、高級CD/SACDプレーヤーと同じ感覚で音楽が聞ける。 USBメモリーとLAN(無線)の違いはN70Aほど大きくはないが、それはUSBメモリーの音が良いためで、LANが無線だから音が悪くなっているという印象はない。本体重量も軽くカジュアルな外観と機能の製品なので、Webで見ているとN70Aの比較対象になりそうもないが、音楽再生プレーヤーとして求められる音に関しては、価格相応以上の性能を持っているように感じられた。 |
![]()
AIRBOW (エアボウ) NA8005 Studio V2 メーカー希望小売価格 \192,593(税別) お問い合わせはこちら 生産完了 |
||
|
||
|
音質試聴動画へのリンク
せせらぎ NA6005
Liveと比べ水の透明感が高い。NA6005
Liveが普通の清流なら、NA8005 Studioは山奥の清流のように感じられる。 鳥の声はきめ細かく羽数が多く、水の粒子も細かくなる。NA6005
Liveとは、音の質感に違いが出る。 モナリザ NA6005
Liveと比べてNA8005は音がスピーカーより前に出る感じがあり、ステージ袖で演奏を聴いている雰囲気だ。 ギターはさらに太く、響きの美さが磨かれ、余韻に甘さが出る。ボーカルは抑揚が大きくなり、弱音部での声のデリケートなコントロールが感じられるようになった。かなり高級なCD/SACDプレーヤーでこの曲を聴いている感覚に近い音でモナリザが鳴った。 新世界 音質が生演奏に非常に近く、コンサートホールの大きさが拡大して実物大により近くなった。 楽器の音は非常に細かく再現され、それぞれの楽器が持つ質感の違いもきちんと再現される。シンフォニーを本格的に聴ける音質に達している。 NA6005
Liveで聞く新世界は親しみやすく、NA8005
Studioで聞く新世界は神々しい。音質はよりニュートラルに近づいている。 What
a Wonderful World (88.2kHz/24bit) ピアノの質感が大きく向上し、密度感も高まっている。右手の音域も改善しているが、左手の音域(低音部)の改善が著しく、グランドピアノらしい深みと重みの感じられる重厚なサウンドでピアノが鳴った。また、ドラム、シンバル、ウッドベース、ピアノの分離が向上し、それぞれの関係性も密になった。 ただ鳴っているだけだった演奏が、じっくり聴いていたい演奏に変わった。 What
a Wonderful World (DSD/2.8MHz) やはり音量が小さくなるのでPCMハイレゾと比べ、音が良くなった感じはしない。実際、双方にあまり違いはないのかも知れない。
せせらぎ NA6005
Liveでもそうだったが、NA8005
StudioではUSBメモリーとLANの音質差がさらに小さい。 せせらぎは非常に細かく自然な音で再現され、接続してるハイエンドシステム
TAD E1/C2000/M2500に負けないクォリティーの音が出るようになった。 モナリザ USBメモリーよりも音が、力強く感じられる。音の密度感も向上し、音がより「本物っぽく」なった。 ギターは切れ込みの鮮やかさが印象的で、ボーカルは声を長く伸ばすところと声を消すところのボーカリストの微妙なコントロールがキチンと出るようになった。下手な50万円クラスのCD/SACDプレーヤーよりは確実に「良い」と感じられる音でモナリザが鳴った。 新世界 USBメモリーよりも音質が向上し、メロディーやリズムが生き生きと語りかけてくる。 ノイマン・チェコフィルが描く「新世界の景色」が見える。本格的な音だ。 What
a Wonderful World (88.2kHz/24bit) NA8005
StudioのLAN接続で聞くこの曲は、USBメモリーよりも音が良くなりすぎて、色々気になってくる。 2分目くらいの「ピアノの2度打ち」がミスタッチに聞こえ、演奏が下手に感じられ、再び聞くのが嫌になってきた。 What
a Wonderful World (DSD/2.8MHz) これという印象はなく、PCMハイレゾとそれほど大きな差がない。 総合評価
NA8005
StudioはUSBメモリーとLANの音質差がNA6005
Liveよりもさらに小さい。しかし、ソフトの録音が良ければその差がきちんと再現されるようになる。 N70AのUSBメモリー再生は、高域にノイズが原因と考えられる「高音の曇り感」が発生していた。SDメモリーなどの再生でも発生するこのノイズは、メモリーアクセス時のノイズが少ない音楽専用高音質メモリーを使うと小さくなり、音が良くなると言われているが、AIRBOWのネットワークプレーヤー(デジタルプレーヤー)のように本体側にノイズ対策を施せば、メモリーの種類による音質差はかなり小さくなる。一般的なネットワークプレーヤー、USB-DACでそれができないのは、ノイズ低減の工程とパーツにかなりコストがかかるためだろう。AIRBOWはそれを実現してるが、その分価格が高い。 今回試聴に用いた「MA
Recording」のソフトには、いくつか問題(録音の癖)があり、そのために演奏そのものの評価が再生機器や方法によって大きく左右される結果となったが、それについては「試聴後感想」で詳しく触れることにする。 |
![]()
TAD (ティー・エー・ディー) C2000 メーカー希望小売価格 2,300,000(税別) お問い合わせはこちら |
||
|
||
|
音質試聴動画へのリンク
せせらぎ AIRBOW
NA8005
Studioに比べて音の細やかさが少し失われたが、水の流れる音が柔らかくなり、音質がより自然になった。 バランスに優れた音質で、PC+USBの音とは思えない心地よい音質で「せせらぎ」が聞けた。これは、USB-DACをプリアンプに組み込んで「一体型」として音を作った成果だろう。 モナリザ ギターの音に芯がある。響きの消え方を含め、非常に力強くギターが鳴った。ボーカルにもしっとりとした艶と、表情の豊かさが感じられる。 TAD
D1000+C2000と比べると、音が少し乾いていて細部の細やかさに欠けるがとても自然な良い音で、さすがに内蔵DACは良くできていると感じられた。 新世界 弦楽器の音にもうすこし「艶」が欲しいが、立体感は良く出るし、低音も驚くほど厚みがある。 弦楽器の弾力が感じられる音は、説得力に富んでいる。 What
a Wonderful World (88.2kHz/24bit) 音が細かく、密度感も高い。低音にはどっしりとした安定感があり、ドラム、ベースの音はまったく揺らがず、音が地に着いている感じがある。 音色の変化もキチンと出て、PCMハイレゾの良さが感じられた。TADらしい「本物」の音が出る。 What
a Wonderful World (DSD/2.8MHz) 再生不可。
せせらぎ 水量が多くなり、音が明るくクッキリする。高域の透明感と見通しの良さがアップした。 モナリザ ギターの音が細かくなり、エコーの余韻が長くなった。ボーカルは声の抑揚が大きくなり、表現の躍動感が増した。 ギターの音とボーカルに「艶」が出る。音の「出(スムースにスッと音が出る感じ)」が、早くなった感じ。 新世界 楽器の抑揚が大きくなって、低音の厚みが増す。ホールにもさらなる広がりが出て、生演奏らしくなった。 高域の立ち上がりの早さが改善し、高域を邪魔するデジタルノイズ感がほぼ完全に解消した。 What
a Wonderful World (88.2kHz/24bit) 今まで聞いたこの曲の中で一番良い音が出る。音のバランスが良く、演奏が上手に聞こえる。 空気感も再現され、場の雰囲気が見えるように(聞こえるように)なった。CDを超える音が出た。 What
a Wonderful World (DSD/2.8MHz) 再生不可。 総合評価
TAD
C2000の内蔵DACが、「おまけ」ではなく、きちんと作られた「本物」だと言うことがよくわかった。 |
![]()
試聴後感想
今回のテストに選んだソフト「What a Wonderful World」は、再生装置によって演奏の評価が激変しましたが、機器の評価にいつも使う「5曲」では、このようなことがなかったので、それに強い「戸惑い」をすら感じました。さらに驚いたことに、この試聴の後に「1/10価格のシステムで聞いたこの曲」が、TADシステムよりも好ましく感じられたのです。
その雰囲気の違いを感じるキーポイントになったのは「2分前後」に収録されている、演奏の終わりの場面での「ピアノのキーの2度打ち」の部分です。同じ音が二度聞こえる原因は、ピアニストが「キーを軽く叩いた」ために、ハンマーが弦で弾かれ、弦を2度打ってしまったために、同じ音が2度鳴ることです。
この「2度打ち」が、ある装置では「ミスタッチ」に感じられ、ある装置では「テクニック」に感じられました。
これまでも装置によって演奏がうまく聞こえたり、そうでなかったことはありますが、音そのものの印象が「ミス」と「テクニック」ほど大きく変わるのは、あまり経験したことのない現象なので、この点をプロの指揮者に確認しました。
彼の返答は次のようなものです。
ピアノのキーは強く叩けば音色が単調になってしまう。しかし、キーが弦に触れるか触れないかのところでキーを叩けば、ハンマーが弦に弾かれて結果として、2度打ちが発生する。けれどそれはピアニストが「繊細に楽器を操作している証」であって、そういうタッチで演奏ができるピアニストが「下手」なはずがない。もしその演奏が「下手」に聞こえるならば、それは「マイクを楽器に近づけすぎたため」、本来客席では聞こえないはずの音まで、録音されてしまったためではないか。
この返答を得て、今回の試聴結果に合点がゆきました。
システムの音が良くなったことにより、「マイクが拾った本来聞こえては鳴らない音」まで聞こえてしまうので、演奏が雑であったり、下手に聞こえたのです。
逆にシステムが低価格になったことで、「マイクが拾った音が過剰に再現されなくなり、本来聞こえてはいけない音が聞こえなくなった」ので、客席で聞いている「良い演奏のバランス」に再生音が近づいたのでしょう。
つくづく「録音(ソフト)」と言うものは、演奏者とエンジニアのどちらもが録音という技術を熟知してこそ(特にエンジニア)、歴史に残るような名録音が生まれるのだと感じました。
2015年6月 逸品館代表 清原裕介



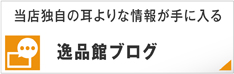
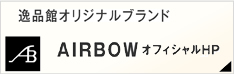

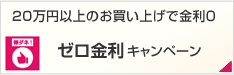
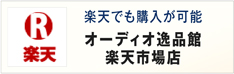
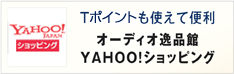
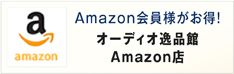
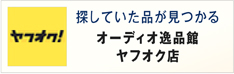
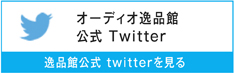

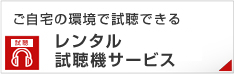

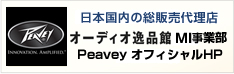




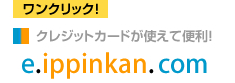


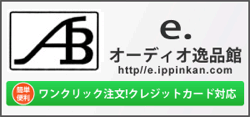
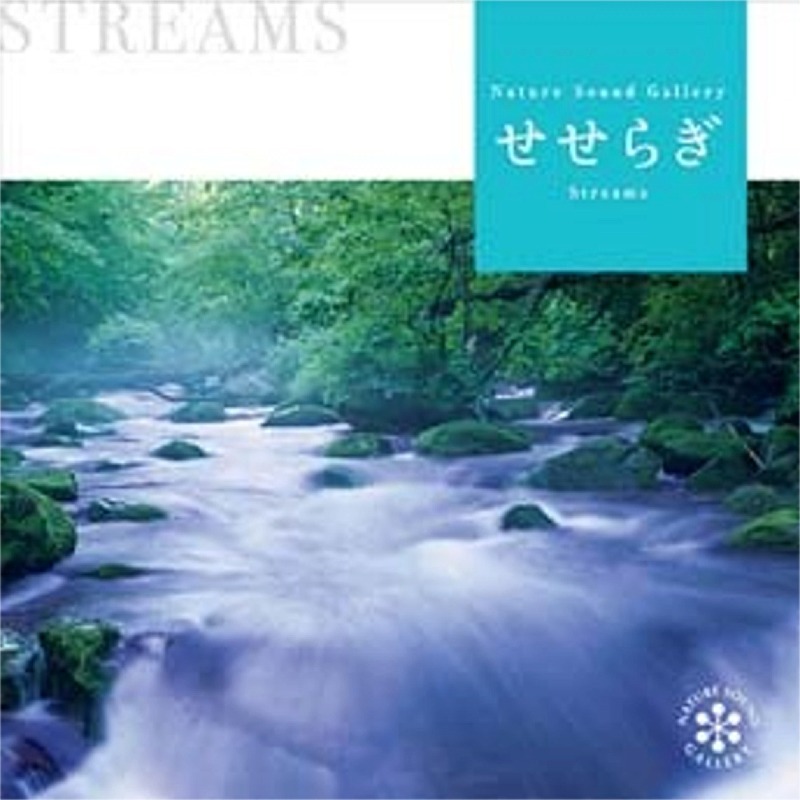
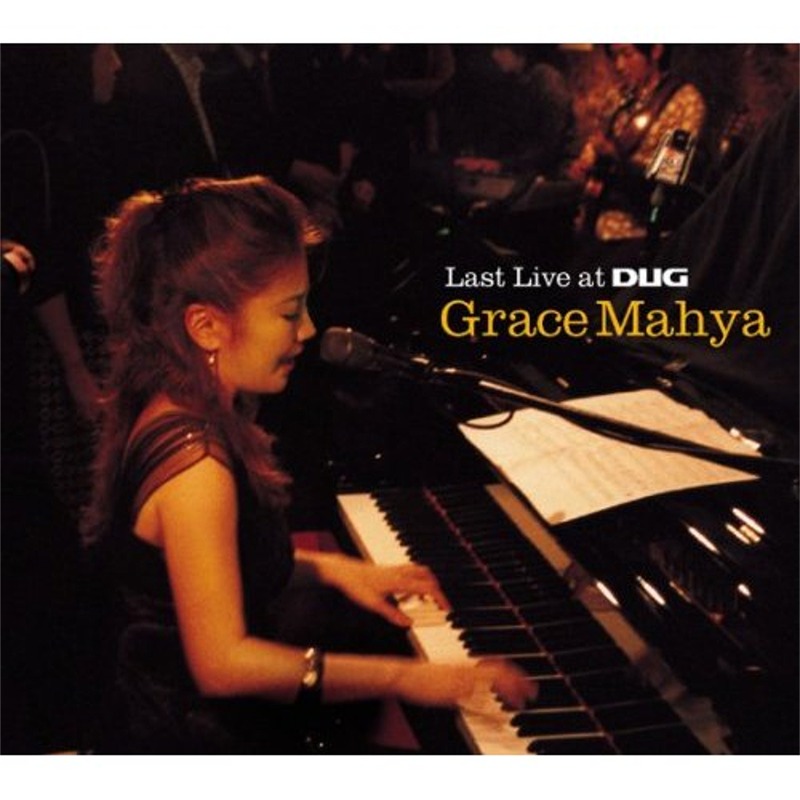
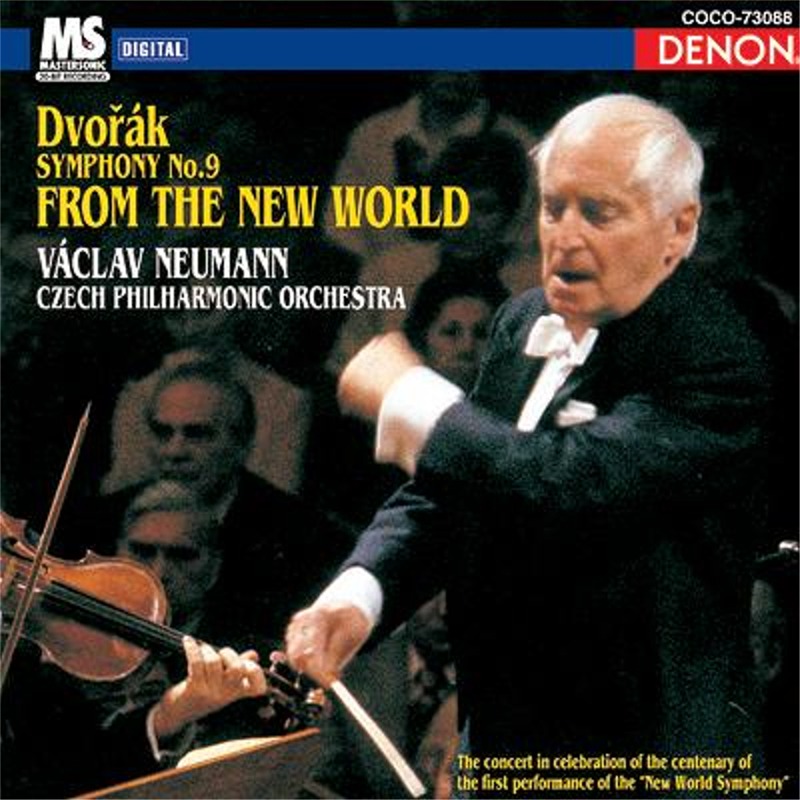
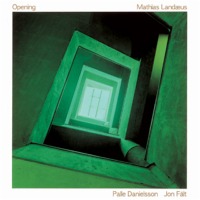

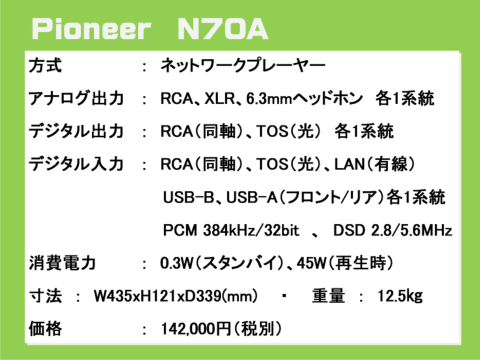
 C2000とはXLR/バランスで接続
C2000とはXLR/バランスで接続


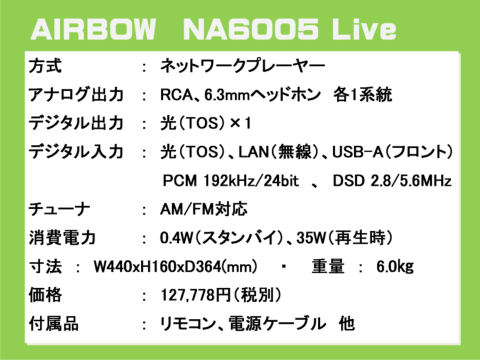



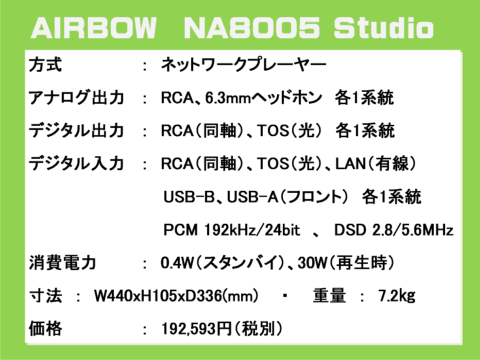




 (再生ソフトは、Audirvana
Plusを使用)
(再生ソフトは、Audirvana
Plusを使用)
 (再生ソフトは、標準搭載のHQ
Playerを使用)
(再生ソフトは、標準搭載のHQ
Playerを使用)