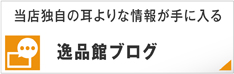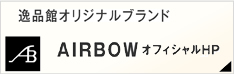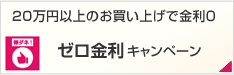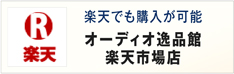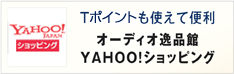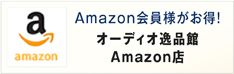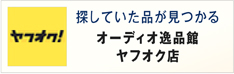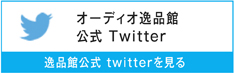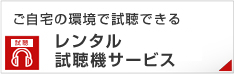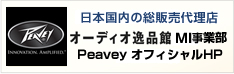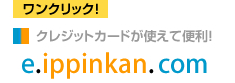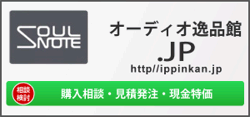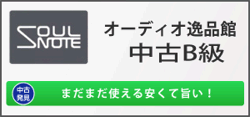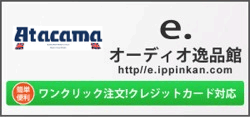■各種コンテンツ
■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部
オフィシャルサイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOULNOTE USB-DAC D-2 TEAC CG-10M atacama アタカマオーディオボード 試聴 音質 比較 評価 レビュー 評判
Soul Note (ソウルノート) D-2 にクロックとオーディオボードを使って音の違いを比べてみた。
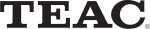
 TEAC
CG-10M
TEAC
CG-10M

 EVOQUE
ECO SE
EVOQUE
ECO SE
![]()
SOULNOTEから発売された、60万円(税別)の「D-2」から、最良のサウンドを引き出す方法を探るため、「デジタルフィルター設定による音質比較」に続いて、TEACの10MHzクロックジェネレーター「CG-10M」をクロック入力に接続したときと、高音質オーディオボードを使ったとき、それぞれで「どれくらい音質は改善するのか?」を聞き比べました。
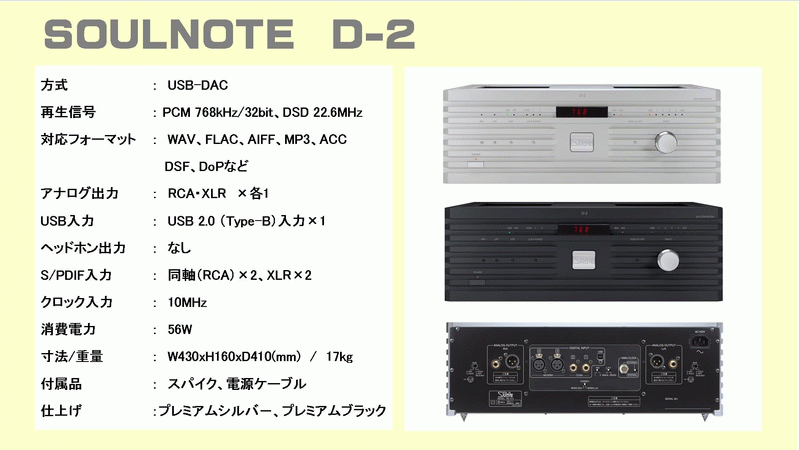
SOULNOTE(ソウルノート) D-2 メーカー希望小売 600,000円(税別) (メーカーホームページ)
SOULNOTE(ソウルノート)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |
||||||
|
![]()
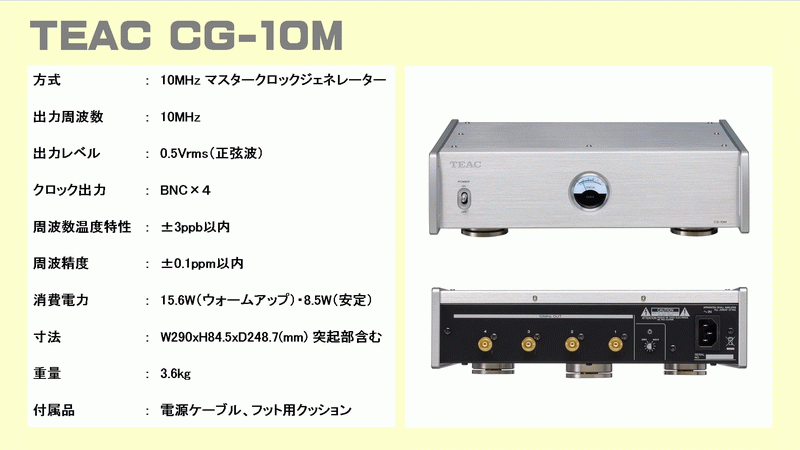
TEAC(ティアック) CG-10M メーカー希望小売価格 OPEN (メーカーホームページ)
Teac(ティアック)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |
||||||
|
![]()
Atacama(アタカマ) オーディオボード

エレクトリが取り扱いを開始したatacama(アタカマ)社のオーディオボードは、振動を制御する「ダンピングガスケット」を採用する特殊な支柱と、振動を最適化するための幾何学デザインの溝「V.R.D.C.」が刻まれた「竹製」の極厚ボード(棚板)で構成されるオーディオラックです。
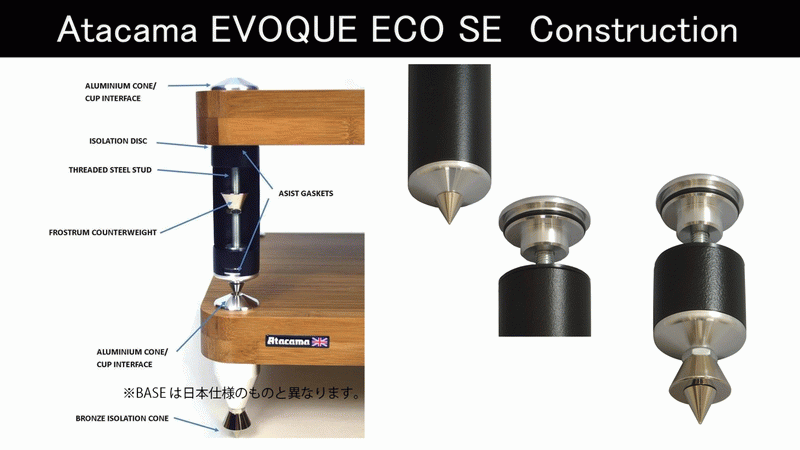

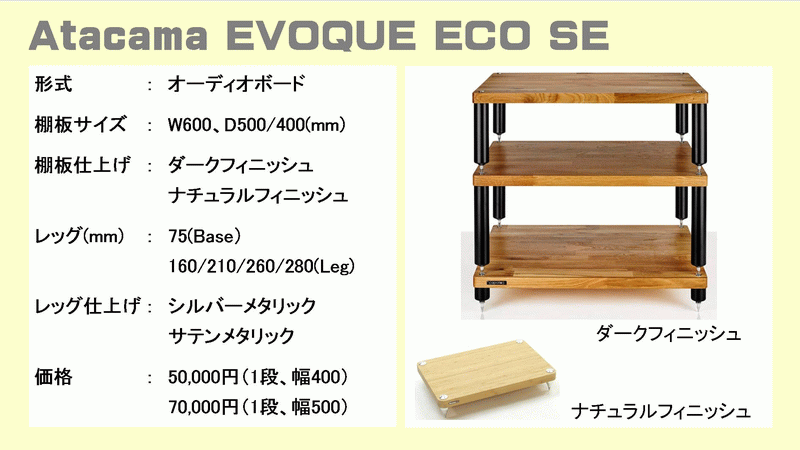
Atacama(アタカマ) EVOQUE EVO SE メーカー希望小売価格 70,000円(税別) (メーカーホームページ)
Atacama(アタカマ)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |
||||||
|
![]()
試聴テスト
比較したのは次の3通りです。
・「NOS」、クロックなし、オーディオボード KRIPTON 「AB-333」
・「NOS」、クロックあり、TEAC CG-10M、オーディオボード KRIPTON 「AB-333」
・「NOS」、クロックなし、オーディオボード atacama 「EVOQUE ECO SE 60/50」
試聴は、Vienna Acoustics LisztにAIRBOW プリメインアンプ PM10 Ultimateを組み合わせて行いました。YouTubeの音声は、すべてXLR(バランス)出力から録っています。
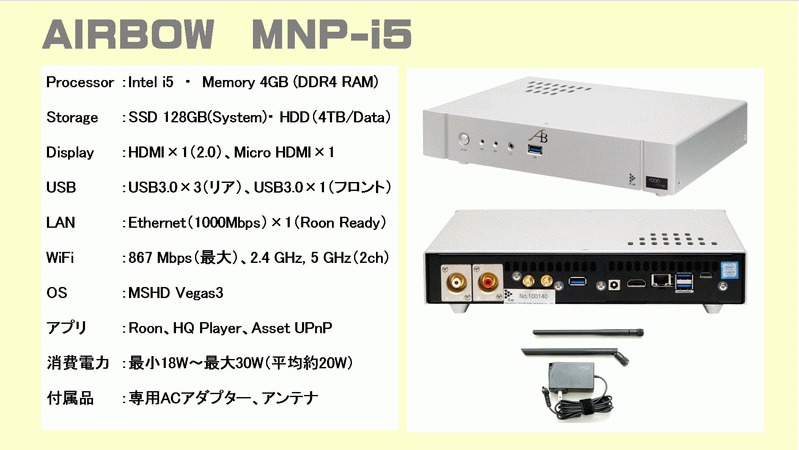
 AIRBOW MNP-i5
Roon 販売価格 460,000円(税別)(現金で購入)・(カードで購入)
AIRBOW MNP-i5
Roon 販売価格 460,000円(税別)(現金で購入)・(カードで購入)
 AIRBOW PM10
Ultimate 販売価格 780,000円(税込)(現金で購入)・(カードで購入)
AIRBOW PM10
Ultimate 販売価格 780,000円(税込)(現金で購入)・(カードで購入)
 Vienna
Acoustics Liszt (現金で購入)・(カードで購入)・(中古で探す)
Vienna
Acoustics Liszt (現金で購入)・(カードで購入)・(中古で探す)
この比較試聴は、YouTubeでご覧いただけます。
![]()
音質テストに使ったソフト
 |
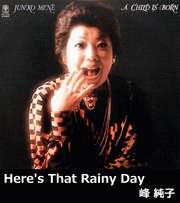 |
 |
![]()

 NOS
NOS
水の流れの滑らかな感覚や、水泡一つ一つの弾ける感じが実にリアルに再現される。
目の前「せせらぎ」があって、その向こう側に「森林」が広がるイメージが、音を通じてしっかり伝わってくる。
 NOS +
NOS + 
水音の「角」が立って明瞭度が上がるが、それはやや誇張されたイメージで、自然で無理のない表現力が長所の「NOS」の良さが消えてしまう。フィルターを「FIR2」に変えたような変化が感じられた。
 NOS +
NOS + 
ボードをクリプトンの「AB-333」から、Atacama EVOQUEに変えると高域がスッキリ伸びて音が細かになり、リアルなイメージに磨きがかかる。とてもすがすがしい音。
ボードを変えたことによる音の変化は、ハッキリと分かる。
![]()
 NOS
NOS
音は細かすぎず、どこにも誇張感や癖がなくとても自然で無理がない。
ボーカルは滑らかで、艶っぽく、厚みも十分にある
目の前のライブを聞いているような雰囲気の音が心地よい。
 NOS +
NOS + 
クロックジェネレーターの接続で音は細かくなり明瞭度も上がるが、「見えすぎる感じ」が出てくる。
細かな音からミュージシャンの緊張が伝わり、ライブ演奏がスタジオ録音になったような変化がある。
オーディオ的には改善しているが、生演奏からは少し離れてしまう。
 NOS +
NOS + 
音の「感じ」は一切変わらず、細やかで上質になる。通常盤を録音の良いディスク、高音質ディスクに変えたような変化。
D-2+NOSの良さが全く損なわれずに音質が改善するので、CG-10Mを追加するよりも好ましい変化に感じられる。
![]()
 NOS
NOS
D-2で聞くと、パイプオルガンの響きが僅かに「太い」感じがする。
パイプオルガンらしいエッジの鋭さ、切れ味も足りない気もするが、聞いていて心地よいからこれはこれで良いのだろう。
 NOS +
NOS + 
高域が伸びた割には中低音の厚みがすこし足りないので、若干楽器の音が「チープ」に感じられることがあるが、オルガンの音の「エッジ」が立ち、金属的の鋭い感じが出てきて、音質が俄然本物っぽくなる。
この楽曲では、CG-10Mの接続で音質は確実に向上して感じられる。
 NOS +
NOS + 
D-2+NOSで避けられないと感じていた、「甘ったるさ」が消える。
輪郭が自然に「立って」、奏者が「キーを押す感じ」が伝わるようになる。
余計な「響き」も消えて、素晴らしい音になった。
![]()
試聴後感想
D-2で「NOS」を選択すると一切の誇張感がなくなり、機器の存在が消えてとても心地よく「音楽に浸れる」ようになります。それは、オーディオ機器としての「基本」がしっかりと磨き込まれているからでD-2だからこそ、細部のピント感を無理して持ち上げなくても「解像度感(きめ細やかさ)」を実現しているからです。これは、高音質オーディオコンポの多くが「音の輪郭を強調することによって明瞭度、解像度を向上させている」ことへの「アンチテーゼ」のようにさえ思えます。
そこに輪郭の強い感じ(オーディオ的傾向の強い)を持ち味とする「TEAC CG-10M」を接続すると、折角のD--2の良さが失われてしまいます。CG-10Mの接続でD-2の音は輪郭がきりりとして細かな音がハッキリと聞き取れるようになりますが、あの「不思議なほどリラックスできる感じ」が失われてしまうのです。
D-2の音作りは、写真におけるソフトフォーカスのように「音を全部見せる」のではなく、「見えない部分を僅かに残して、そこはリスナーの想像にゆだねる」ような鳴り方を旨とします。苦労してそういう「出しゃばりすぎない音」を目指して作られているD-2に、それを「見せてしまう」CG-10Mはミスマッチのようです。
だからといって、CG-10Mが「悪い音」なのかというと、それは違います。例えばTEAC NT-505やそのカスタムモデル AIRBOW NT505 Specialでは、CG-10Mを一度繋ぐと外したくなくなります。音の方向性がマッチすれば、「CG-10Mはなくてはならないアイテム」になるのです。
そういうCG-10Mに対して、エレクトリが取り扱いを始めた「atacama(アタカマ)」のオーディオラック(オーディオボード)」は、自然に音が良くなるのを持ち味としています。この音作りは、同じ思想で作られた「AIRBOW Beat Rack」とよく似ていて、ラック(ボード)の響きを生かし、オーディオ機器に「楽器的な響き」を与えるものです。
AIRBOWとAtacamaの違いは、棚板に竹を使うAtacamaの方が高域が強く、スッキリと透明な印象なのに対して、棚板に白樺材を使い、支柱に真鍮を奢るAIRBOWは、音の厚みや色彩感が濃い印象です。どちらもその効果は非常に大きく、下手にコンポやケーブルを弄るよりも、ずっと「音が良くなり」ます。
今回、AIRBOWのラックは聞いていませんが、Aatacama EVOQUE ECO SEをD-2に使うと、良い方向でD-2の過剰な甘さや響きが軽減され、アクリルをガラスにしたようなイメージ、透明感と密度感が向上させる効果がありました。クロックジェネレーター CG-10Mのように「電気的に接続しない」ラックやボードの効果は、それらよりも低いと感じられるかも知れませんが、D-2にAtacamaのボードを使ったときの音質改善幅は、CG-10Mよりも大きく、方向性もマッチするので、私ならD-2の相棒には、CG-10Mではなく、atacama EVOQUE ECO SEを選びます。そして、価格もCG-10Mよりも安いのです。
過去から現在までオーディオの世界ではメーカーと雑誌社、そしてそれに迎合する音楽を知らないオーディオマニアが一体となって「技術信仰」が作り上げられています。私はそういった「フェイクニュース(彼らの情報こそが本当のフェイクです)」によるお客様への不利益を止められず忸怩たる思いです。
WEBや雑誌など「実際の音を伴わない情報」に頼ると、どうしても「目で見られる情報」に洗脳されます。けれど、実際には「非電気的」な、ボードやインシュレーターでも「アンプやプレーヤー」の音は大きく変化します。逆に、どんなによい機器を使っていても、ラックやボードを適当にしていると、性能がしっかりと発揮できません。
今回に関わらず、私が「YouTube」に、実際の音声をアップロードするのは、「目ではなく耳」でその変化を確認していただいて、後悔しないお買い物をしていただくためなのです。
2018年8月 逸品館代表 清原裕介