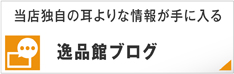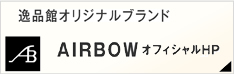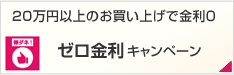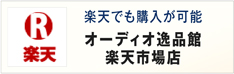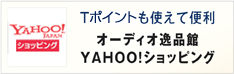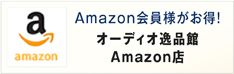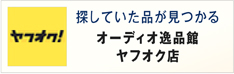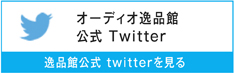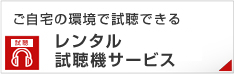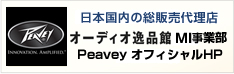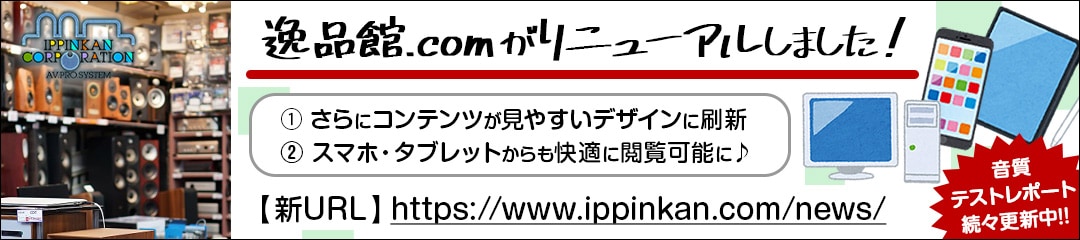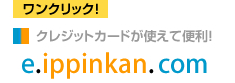|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音楽の力、オーディオの力
オーディオがあるから音楽が聞ける 音楽は、人間が持つ豊かな感情をより多くの人々と分かち合うために発達してきた芸術であり、現代社会においては生きるための様々なストレスから、心を解放するためにも大きな役割を果たしています。音楽は私達の生活と共にあり、感情を豊かにし、心を癒してくれる大切な存在です。音楽を豊かに深く伝えるために「オーディオ」はなくてはならない大切な存在です。 | |||||||||||||||
オーディオが音楽のあり方を変えて行く 20世紀に私達は音声を記録し、それを「望むときに、望む場所で再現する方法」、「オーディオ」を実用化しました。発明当初は、ただ音楽を聴くための「手段」に過ぎなかったはずのオーディオですが、たゆまざる技術革新が続けられた結果、20世紀後半には「音楽を聴く」という語意がコンサートへ行くことではなく、「録音された音楽を聴く」という意味に変えてしまうほどの大きな改革を私達と音楽の関わりにもたらしました。
電気的に音声を記録増幅するという手段を得たことで、オーディオは当初の目的であった「演奏の再演(記録)」という枠を超えて音楽鑑賞のありかたに大きな影響を与え、ついには「オーディオ(ステレオ)で聴く音楽」が「生演奏」を越える文化に育ったのです。
| |||||||||||||||
|
言語と音楽の違い 本来は、このように「抽象的なイメージ」を「音の変化」に置き換えることで発展してきた音楽ですが、最近では「ラップ」などのように「言語」を使って「直接的にイメージを伝える音楽」も発達してきました。しかし、あまりにも「言語」に頼りすぎることは、音楽そのものの「抽象性」を損い、イメージの広がりや深さを損います。最近の音楽が「すぐに飽きられる」のは、そういう理由なのかも知れません。
| |||||||||||||||
|
音楽の力、オーディオの力、 | |||||||||||||||
|
音楽は難しくない 1. 人間はみんな音楽の天才だ 2. 本物の感動とは |
人間の音の聞こえ方 1. 聞こえ方には個人差がある 4. 音のバランスを考える |
究極の音質を目指して |