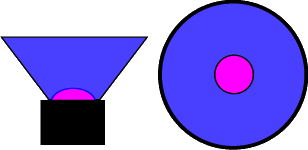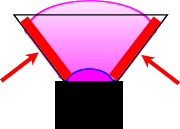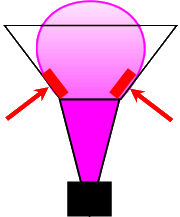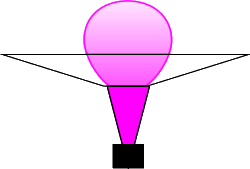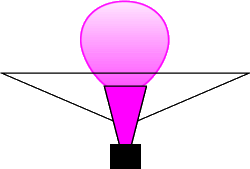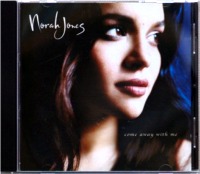TANNOY(タンノイ) Revolution Signature
DC6T DC4T + AUTOGRAPH MINI
音質 比較 評価
 |
 |
|
メーカー希望小売価格 ¥125,000(税別) |
メーカー希望小売価格 ¥100,000(税別) 生産完了 |
|
タンノイからミドルクラスのトールボーイ型スピーカー「Revolution Signature Series」が発売されました。搭載されるユニットは、逸品館での評価が高いAUTOGRAPH-MINIに搭載されているのと同じ本格的なコンプレッションドライバーを採用したホーン・ツィーターに、表面が銀色にコーティングされたペーパーコーンのウーファーが組み合わされた同軸2Way型ユニットです。 今回音質テストを行ったのは、ウーファーサイズが100mmの小型モデルDC4Tとウーファーサイズが150mmのDC6Tです。 合わせて、すでに発売済みのAUTOGRAPH-MINIの音質も比較してみました。 |
|
 |
 |
|
メーカー希望小売価格 ¥300,000(税別) |
|
|
DC6T DC4T の特徴 |
|

|
 |
|
150mmのウーファーを採用したDC6T(左)と100mmのウーファーを採用しているDC4T(右)のユニット。写真から、コンプレッションドライバーを使った本格的なホーンが採用されていることがよくわかります。ウーファー・コーンの材質は、紙ですが銀色にコーティングされています。 |
|
 |
 |
|
スピーカーターミナルとジャンパープレート。スピーカーとしては珍しく銀色のメッキが施されています。本体とのカラーコーディーネーとのためだと思われます。スピーカーターミナル右一番下の「緑色」の端子は、アース接続用端子です。この端子とアンプのボディーを繋ぐことでS/N感の向上などの効果があると説明されています。 |
|
 |
 |
|
サランネットは「埋め込まれたマグネット」で固定されます(写真左)。外したときにネットを固定する「穴」が無く、スッキリとまとまっています(写真右)。 |
|
|
技術解説 |
|
|
同軸2Way方式というユニットの特徴について簡単に解説します。同軸2Wayユニットとは、ウーファーの中央にツィーターを配置する(図1)ことで、音源からリスニングポイントまでの「距離誤差」を減少し(音源を点音源に近づける)、ピントの合った(定位に優れた)音像イメージを実現する方法です。
(図1) ウーファーの中央部にツィーターを配置することを同軸2Way方式と呼ぶ。 この考え方は、理論的には申し分のない方式なのですが中央部に配置したツィーターから出る高音が、周囲のウーファー・コーンに反射し(図2)、それが定位に悪影響を及ぼすという欠点を持っています。
(図2) ツィーターから出る音が赤い矢印の示す部分でウーファーと干渉する。 この同軸2Wayユニットの中で、中央部の高域ユニットに「ホーン型」が採用されたものが「ホーン型同軸2Wayユニット(図3)」です。「ホーン型(ホーン・ツィーター)」とは、ドライバー(振動板)の音をホーン(朝顔の用な形状の筒)によって囲い込んだ形状の高域ユニットでホーンを持たないツィーターに比べて音が遠くまでハッキリ伝わるという特徴を持っています。しかし、同時にユニットの横側に音が届きにくい(広がりにくい)という欠点も合わせ持っています。スピーカーではありませんが、声を遠くまで伝えるために使う「メガホン」も同様の原理なので、ホーン型とは、「メガホン」の付いているスピーカーだと考えていただければ、イメージしやすいかも知れません。
(図3) 高音発生部がホーン方式を採用しているユニットをホーン型同軸2Wayユニットと呼ぶ。 TANNOY社は、伝統的にこの二つの方式を組み合わせた「ホーン型同軸2Wayユニット」を音楽再現に適した方式と位置づけて、高級モデルに採用しています。今では、TANNOYのお家芸とも言えるこのホーン型同軸2Wayユニットですが、その登場はかなり過去に遡ります。著名な所では、真空管時代の同軸2Way型ホーンスピーカー(タンノイやアルテックなど)が有名だと思います。この時代のスピーカーの多くは、低出力の真空管アンプとのマッチングを考え、高能率のホーンと高能率の大口径のウーファーが組み合わされていました(図4)。大口径のウーファーの中心にホーンを納めるのは、物理的にそれほど難しくはなかったと考えられますから、理想的な点音源を目差してユニットが「同軸型」に発展していったのは、技術的に自然な成り行きだと思われます。
(図4) 大口径のウーファーを採用したホーン型同軸2Wayユニット。 そして、幸いなことに大口径のウーファーの中央にホーン型ツィーターを配置するというこの時代の「ホーン型同軸2Wayユニット」では、ツィーターの高域がウーファーのコーンで反射して引き起こされる悪影響は、ほとんど問題ではありませんでした。なぜなら、ウーファーの口径が30cm以上と十分に大きいとコーン紙のカーブが緩やかになり、中央部に搭載されるホーン型ツィーターの出口との角度の差が大きかったため、ホーンから出る音がウーファーとほとんど干渉(反射)しなかったからなのです。 ※ウーファーが十分に大きいとホーン型ツィーターからでた音は、ウーファーのコーン紙と干渉しない(図4)。 そのため高域がウーファーで反射して「音が濁る」という問題点を感じることがありませんでした。初期のアルテックの同軸2wayユニット(マンタレイホーン時代)では、ウーファーよりもホーンの開口部が突き出した形になっていますが、これもホーンから出る高音をウーファーと干渉させたくなかったからだと思われます(図5)。このように同軸2Wayユニットが成功するかどうか?は、高域がウーファーのコーン紙の影響から逃れられるか?にかかっていると言ってよいと私は考えています。
(図5) ウーファーよりもホーンの開口部が突き出た形状のホーン型同軸2Wayユニット。 しかし現在、同軸ユニットを設計する多くのメーカーが、この重大な問題についてほとんど無関心なことにはあきれるばかりです。初期のKEFのUNI-Qユニットは、メーカー側の理想的な説明とは裏腹に、良好なはずの中高域が、ベールがかかったように濁っていました。それもそのはず、UNI-Qが搭載しているツィーターは、通常のドーム型でホーン型と比べると遙かに指向性が緩やかです(横方向に高音が出ます)。その上、小口径ウーファー・ユニットのコーン紙カーブは、この高音にホーンロードを掛けるのに最適なカーブに設計されています。もし、このウーファーが「全く動かない」のならこの理想的な設計に勝るスピーカーはないでしょう。しかし、ウーファーのコーン紙は「入力される信号に応じて前後に振動」し、さらに動きを素早くするために「軽く」作られているために、ツィーターの高域と盛大に共鳴を起こします。振動するホーンと、盛大に共鳴するホーンをもつ「ホーン型ツィーター」の音が良いはずはありません。KEFと言えば、イギリスのスピーカーメーカーの老舗で過去に素晴らしい製品を送り出しているメーカーだけに、このUNI-Qの欠点を見過ごしているのは驚くべき事だと私は考えています。もちろん、現在のUNI-Q型ユニットは、初期のようなひどい欠点はありませんが、彼らが言うほど理想的には動作していないのも事実ではないでしょうか?
(図2’) ツィーターから出る音が赤い矢印の示す部分でウーファーと盛大に干渉する。 ウーファーは、前後に激しく振動しているため、高音が乱れ、音が大きく濁ってしまう。 一見、理想的に見える「同軸ユニット」ですが、それは諸刃の剣のように「功罪」を合わせ持っています。その「罪」の少なかった「ホーン型同軸2Wayユニット」ですが、最近はスピーカーの小型化の影響から小口径のウーファー・ユニットを採用するものが増えたため、ホーン・ツィーターから出る音がウーファーのコーン紙に反射して悪影響を与える事が多くなっています。 (図3’) 高音発生部にホーン方式が採用されている場合は、同じ口径のウーファーでも 15インチ以上の口径のウーファーを搭載しているTANNOYなら、これまでの説明からもおわかりいただけるようにウーファーによる高音の濁りは、ほとんど問題となりません。しかし、12インチ以下の口径のウーファーを搭載している製品では、ウーファーからの高音の反射の悪影響が避けられないのです。 ウーファーとツィーターの音が干渉を始めると、問題は複雑になります。それは、「口径が大きい=悪影響が少ない」という簡単な論理が通用しなくなるからです。なぜなら、干渉が生じるとその悪影響の大きさは、量ではなく「人間にとってそれが耳障りかどうか?」という質の問題になるからです。質の問題は、音響理論では明確になりません。ウーファーのサイズはもちろん、コーン紙の材質や厚み、表面の状態などによって、大きな影響を受けるからです。唯一それを確かめる方法は、現在の所「実際に聞いてみる」以外にはないのです。 この「ホーン型同軸2Wayユニット」の功罪を思い描きながら、「Revolution
Signature Series」の試聴記事をお読み頂ければ、この製品への理解をより深めていただけるのではないだろうかと思います。 |
|
|
試聴テスト |
|
|
試聴テストは次の機材を用いて行いました。
スピーカー Vienna Acoustics T3G
アンプ AIRBOW PS8500/Special(7.1chダイレクト入力)
CDプレーヤー AIRBOW SA10/Ultimate
試聴ソフト ノラ・ジョーンズ “Come away with me” |
|
|
|
|
Revolution Signature DC6T 接続端子は、TANNOYの高級品らしくBi-wire+アースの5端子方式が採用されている。とりあえず、いつも通りに「高域+」・「低域-」のたすき掛け接続を試してみるが、高域が突っ張った感じで固く音質が芳しくない。そこで「低域±」に繋ぎ変えると、高域のエネルギーが減少し聴きやすくなった。試しに「高域±」で繋いでみると、ハイ上がりのキンキンした音で最悪のバランスになってしまった。そこでいつもとは違うが、DC6Tには「低域に±の両方を繋ぐ」ことにする。 さらに、付属のジャンパープレートを止めてスピーカーケーブルを切って作ったジャンパー線に交換すると中高域が滑らかできめ細かくなった。念のためジャンパープレートの場合と同じ要領で接続の聞き比べを行ったが、やはりジャンパープレートで良かった「低域に±の両方を接続する」方法がベストだった。 この状態でノラ・ジョーンズを聞く。 中域の厚みとボーカル帯域の肉付きは、タンノイらしくややぼってりとして感じられるくらいの量感がある。 低域の量感は、このサイズのトールボーイスピーカーとしては標準。PMCのような、凄い低音は望めないし、B&Wなどと比べても、やや少ないかも知れない。 バスレフ方式を採用しているため、低域は少し遅れて膨らむ感じがあるが、これはこのソフトでは完全に許容範囲内で問題はなく、B&Wよりもバスレフによる低域の膨らみは小さいと感じられる。 ホーン型であるが、指向性は穏やかで帳面と横側で聞く高音の差は小さい。しかし、AUTOGRAPH-MINIと同じユニットを採用しているはずなのに、高域の繊細感、透明感、切れ味がそれに叶わないのは、なぜだろう?後ほどDC4Tとの比較で確認したいと思うが、ウーファーの口径が100mmから150mmと大きくなったこと、ウーファーの表面の材質が変わったことで、ユニットの表面に銀色のコーティングがされたことでウーファー表面からの高域が反射し、このツィーターの持つ本来の優れた音色をマスキングしてしまっているようだ。 全体的な音質バランス、質感などには申し分はないのだが、個人的には今一歩中高域の透明感とスッキリした明瞭感を望みたい。悪くはないし、長時間聞いていても聞き疲れもせず、不満のない音なのだが、やや中庸で「高域のプラスアルファの魅力(艶)」が欲しいと感じた。仕上げは美しく、サランネットの取り付け方式もマグネットになっているので、ネットを外したときに穴が見えず、AUTOGRAPH-MINI同様の高級品らしい配慮は、素晴らしい。 |
|
|
|
|
Revolution Signature DC4T DC6Tと同じ「低域に±」、「自作ジャンパー線」の組合せで試聴を開始する。アンプのボリュームは、そのままだ。 一音が出た瞬間に「音が軽い」と感じる。ちょっと冷たくジメジメとしたロンドンの街を連想させるDC6Tと違ってDC4Tの音は「晴れ」ている。ピアノの高域の音色も軽やかだし、ノラ・ジョーンズの声も一段他若々しく張りが出てくる。 ベースの音はさすがにウーファーの口径とエンクロージャー容量が小さくなったため、控えめになってしまうが、引き替えに中高域の妙なあつぼったさや突っ張った固い感じは消えている。 ギターの音色も透明感を増す。 でも、やはり低音は少ない。サイズはDC4Tのほうが大きいにもかかわらず、AUTOGRAPH-MINIをスタンドに設置して聞いたときよりも低音の量感は少ないかも知れない。もしそうだとすればスピーカーは、本当に楽器そのもので理論では良いスピーカーは作れない良い例になるだろう。スピーカーのことを古いオーディオマニアは「ラッパ(古いスピーカーは、形もラッパを思わせるホーン型が多かったこともあるだろう)」と呼ぶが、それは言い得て妙だと思う。スピーカーは、オーディオ製品の中で最も楽器に近いからである。 スピーカーの楽器性を軽視し、「ラッパ」を理論の中心にまとめてゆく国産製品やB&Wなどの音が、細かくても心に響かないと感じる事があるのは、正にその「ラッパの楽器性」を軽視しているからに他ならないと思う。スピーカーのみならず、国産オーディオ製品の多く(デジタルアンプなどはその最たる例だと思う)もオーディオ製品の楽器性=響きを考慮していないため、音が冷たかったり、音楽的な表現力に欠ける(音楽が心に響かない)事が多い用だが、それも、設計者の「経験不足(音楽性軽視)」が原因だろう。 そういう見方をするならDC4Tは、DC6Tよりもより良い楽器である。低音は足りないが、音楽的なバランスと表現力に優れ、より心地よく音楽を聞くことができると私は思う。 |
|
|
|
|
|
Autograph mini 今回のテストの締めくくりと確認のため、DC4Tと同口径の「同軸2wayホーン型ユニット」を搭載し過去のテスト結果が良好だったAUTOGRAPH-MINIを最後に聞いてみることにした。アンプやスピーカー音量などの条件は、すべて同じであるがAUTOGRAPH-MINIは、Bi-wireに対応していないので接続で音を選ぶことはできない。 気になる低音は?やはりDC4Tの方が一枚上手だった。しかし、サイズを考えるとAUTOGRAPH-MINIもかなり頑張っている。 3号館にあるAUTOGRAPH-MINIは、おなじTANNOYのTURNBERRY/SEの上に乗せて鳴らしているのだが、ソフトによっては(アコースティックな音源、特にピアノ)もの凄い低音が出るので、時としてTURNBERRY/SEを鳴らしていると錯覚をすることがある。これは嘘でも大げさでもなく、私だけではなくスタッフも同意見であることを付け加えておきたい。 低音の量感は若干減るものの、DC4Tよりもエンクロージャーが小さいAUTOGRAPH-MINIの低音は、歯切れ良い。音はDC4Tよりさらに軽やかだ。 音像は一回りコンパクトになるのだが、DC6T/DC4Tでは感じられなかった「自然な空気感(場の雰囲気感)」のようなものが感じられるようになる。これは、AUTOGRAPH-MINIの「楽器性(響きの調和)」が素晴らしく、優れているためだろう。部屋いっぱいに音が自然に広がるから、音楽を聞くときのストレスが今回テストしたスピーカーの中で最も小さく感じられた。 ノラ・ジョーンズの声は、透明度と“強さ”が増す。この“強さ”は、実在感?と言い換えればよいのだろうか?まるで本物を聞いているような“強い存在感”が感じられるようになる。ドラムのブラシ使いも明瞭感を増すし、バックの演奏も力強くなる。表現力は3機種の中でずば抜けている。 AUTOGRAPH-MINIは、そのクラシカルなデザインと裏腹に素晴らしくHiFiなスピーカーである。その上、色彩感の再現に優れ、音場再現の実在感・存在感が非常に高い。もし、「小型復刻版」というイメージがこのスピーカーの足を引っ張っているとすれば、それは残念なことである。 とにかく「心に訴える音楽性」では、現存するスピーカーでも希有なほどの存在だと思うほどだし、本当の意味でホーンの良さが表現された、まさにTANNOYらしい素晴らしいスピーカーだ。小型スピーカーをご検討の方には、是非一度お聞きいただきたいと思う。 |
|
|
|
|
|
2008年1月 清原 裕介 |
|